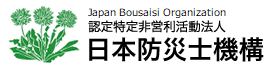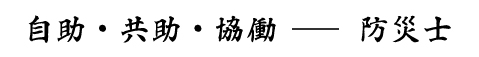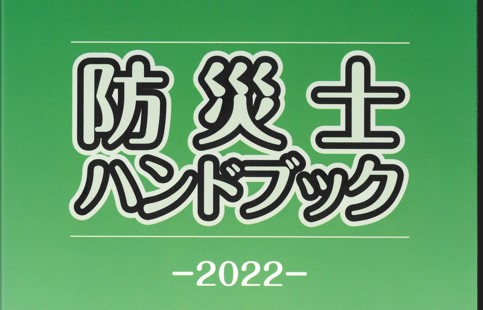防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
防災士の基本理念
防災士とは“自助”“共助”“協働”を原則として、社会の様々な場で防災力を高める活動が期待され、
そのための十分な意識と一定の知識・技能を修得したことを、日本防災士機構が認証した人です。
1. 自助ー自分の命は自分で守る。
2. 共助ー地域・職場で助け合い、被害拡大を防ぐ。
3. 協働ー市民、企業、自治体、防災機関等が協力して活動する。
日本防災士機構からのお知らせ
- すべて
- イベント
- お知らせ
- 各地の動き
- 外部団体セミナー等
- 被災地支援
- その他
-
 2024年3月6日掲載
イベント
2024年3月6日掲載
イベント
【3月11日(月)開催】巨大地震の際に東京が行うべきこと
防災でつなぐコミュニティ @大手町プレイス -
 2024年2月26日掲載
お知らせ
2024年2月26日掲載
お知らせ
木耐協オンラインセミナー(2024年4月20日)
~能登半島地震と今後の備え & 住まいの耐震対策~ -
 2024年1月10日掲載
お知らせ
2024年1月10日掲載
お知らせ
令和6年「東京消防出初式」に参加
-
 2023年10月26日掲載
イベント
2023年10月26日掲載
イベント
新潟県中越大震災20年プロジェクトについて
-
 2024年3月6日掲載
イベント
2024年3月6日掲載
イベント
【3月11日(月)開催】巨大地震の際に東京が行うべきこと
防災でつなぐコミュニティ @大手町プレイス -
 2023年10月26日掲載
イベント
2023年10月26日掲載
イベント
新潟県中越大震災20年プロジェクトについて
-
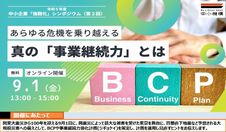 2023年8月21日掲載
イベント
2023年8月21日掲載
イベント
第2回 中小企業「強靱化」シンポジウム
~あらゆる危機を乗り越える、真の「事業継続力」とは~ -
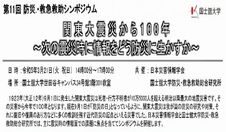 2023年2月23日掲載
イベント
2023年2月23日掲載
イベント
第11回 防災・救急救助シンポジウム
「関東大震災から100年~次の震災時に情報をどう防災に生かすか~」
-
 2024年3月6日掲載
イベント
2024年3月6日掲載
イベント
【3月11日(月)開催】巨大地震の際に東京が行うべきこと
防災でつなぐコミュニティ @大手町プレイス -
 2024年2月26日掲載
お知らせ
2024年2月26日掲載
お知らせ
木耐協オンラインセミナー(2024年4月20日)
~能登半島地震と今後の備え & 住まいの耐震対策~ -
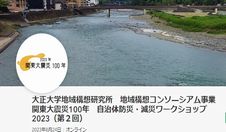 2023年8月4日掲載
お知らせ
2023年8月4日掲載
お知らせ
大正大学地域構想研究所 地域構想コンソ―シアム事業
関東大震災100年 自治体防災・減災ワークショップ2023(第2回) -
 2023年10月26日掲載
イベント
2023年10月26日掲載
イベント
新潟県中越大震災20年プロジェクトについて
-
 2023年10月26日掲載
イベント
2023年10月26日掲載
イベント
新潟県中越大震災20年プロジェクトについて
-
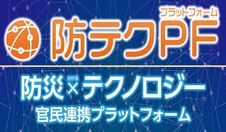 2022年9月7日掲載
お知らせ
2022年9月7日掲載
お知らせ
「防災×テクノロジー官民連携プラットフォーム」(防テクPF)を設置
-
 2018年3月29日掲載
各地の動き
2018年3月29日掲載
各地の動き
日本防災士会が地区防災計画推進会議を開催
-
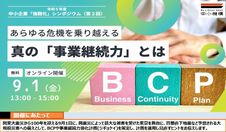 2023年8月21日掲載
イベント
2023年8月21日掲載
イベント
第2回 中小企業「強靱化」シンポジウム
~あらゆる危機を乗り越える、真の「事業継続力」とは~ -
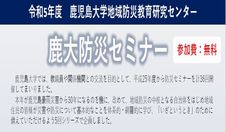 2023年9月25日掲載
お知らせ
2023年9月25日掲載
お知らせ
令和5 年度鹿児島大学地域防災教育研究センター 鹿大防災セミナー
-
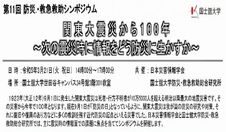 2023年2月23日掲載
イベント
2023年2月23日掲載
イベント
第11回 防災・救急救助シンポジウム
「関東大震災から100年~次の震災時に情報をどう防災に生かすか~」 -
 2023年1月19日掲載
イベント
2023年1月19日掲載
イベント
多文化共生防災セミナー~地域防災と平時、発災時の在住外国人対応について~
-
 2019年12月19日掲載
被災地支援
2019年12月19日掲載
被災地支援
栃木県佐野市、宮城県丸森町へ調査班及びボランティア活動支援のため統括監を派遣しました
-
 2018年9月11日掲載
被災地支援
2018年9月11日掲載
被災地支援
災害関連情報
-
 2018年3月29日掲載
被災地支援
2018年3月29日掲載
被災地支援
北九州豪雨災害、今も朝倉市を支援 天野 時生 防災士(福岡県)
-
 2018年3月29日掲載
被災地支援
2018年3月29日掲載
被災地支援
熊本地震、現地本部を立ち上げて2ヶ月間支援活動
-
 2023年10月6日掲載
お知らせ
2023年10月6日掲載
お知らせ
防災・減災に役立つスマートフォン向け無料アプリ
「被害予測・防災cmap(シーマップ)」のご案内 -
 2019年11月19日掲載
その他
2019年11月19日掲載
その他
日本AED財団が、みんなで作るAED N@VIを推進しています
-
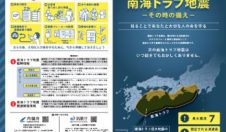 2019年7月4日掲載
その他
2019年7月4日掲載
その他
内閣府・気象庁より、リーフレット「南海トラフ地震 -その時の備え-」が発行されました。