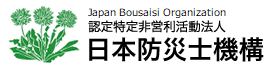防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
防災評論 第73号
山口明の「防災・安全 ~国・地方の動き~」
防災評論家 山口 明氏の執筆による、「防災・安全 ~国・地方の動き~」を掲載致します。防災対策を中心に、防災士の皆様や防災・安全に関心を持たれている方々のために、最新の国・地方の動きをタイムリーにお知らせすることにより、防災士はじめ防災関係者の方々の自己啓発や業務遂行にお役立てて頂こうとするものです。今後の「防災・安全 ~国・地方の動き~」にご期待下さい。
防災評論(第73号)【平成28年8月号】
【目次】
〔政治行政の動向概観〕
〔個別の動き〕
- 01、熊本地震 九州で文化財被害300件超(文化庁)
- 02、全国自治体庁舎3割「耐震性なし」(消防庁)
- 03、新耐震基準でも家倒壊(建築学会)
- 04、日本海溝沖、震災で高まるリスク 大津波を生む断層を調査へ(海洋研究開発機構)
- 05、首都圏直下地震で14万人派遣 全国から1都3県に救援(内閣府)
- 06、東日本大震災の火災398件 揺れで出火、半数が「電気」(日本火災学会)
- 07、地震保険支払い 阪神超す見込み(損保協会)
- 08、耐震化は待ったなしだ(消防庁)
- 09、罹災証明、ようやく手に 熊本・益城町 生活再建へ一歩(益城町等)
- 10、家の応急修理 申請進まず(熊本県)
- 11、津波被災地60ヘクタール 格安で貸し出し(仙台市)
- 12、熊本地震1か月 経済損失5,000億円規模(内閣府)
- 13、地震後 相次ぐ窃盗(警察庁)
- 14、関西自治体 熊本支援の輪(地方公共団体)
- 15、罹災証明 手続き本格化(熊本県)
- 16、熊本 土砂災害54か所(国土交通省)
- 17、家屋倒壊で死亡37人 うち20人 旧耐震基準(熊本県)
- 18、「倒壊の危険」1万2,000棟(国土交通省)
- 19、土砂災害の危険 常に斜面監視を(土木学会)
- 20、新耐震基準の木造住宅 全壊最大17棟(建築学会)
- 21、民泊を全面解禁、住宅地で営業(厚生労働省)
- 22、地下街の防災「改善を」(総務省)
- 23、消防救助隊 5,301隊に増加(消防庁)
- 24、地震速報 障害者に配慮(気象庁)
- 25、地震マニュアル「改訂が必要」(気象庁)
- 26、要援護者を訪問調査(熊本県)
- 27、四国沖など「ひずみ」強く(海上保安庁)
- 28、噴火に「保険」(損保会社)
- 29、「3日分備蓄」48%どまり(東京商工会議所)
- 30、震災関連死「県が審査を」(熊本県)
- 31、危機意識、太平洋側で高く(防災白書・内閣府)
- 32、地震の被害予測システム 「連続揺れ」の影響考慮(内閣府)
- 33、防災基本計画 政府が見直し(内閣府)
- 34、「本震→余震」の常識覆る(気象庁)
- 35、復旧費の75%補助(財務省)
- 36、全国の空き家情報集約(国土交通省)
- 37、「丸投げ」排除へ判断基準(国土交通省)
- 38、地震2か月、罹災証明待ち4万件(熊本県)
- 39、熊本「住」トラブル多発(消費者庁・国民生活センター)
〔政治行政の動向概観〕
今年に入ってから台風発生は少なかったが、8月には台風9、11号が本土に上陸、または本土をうかがう状況となり、各地で被害がでている。
海外に目を転じるとイタリア中部の丘陵地帯でM6.2と推定される地震が発生、必死の救助活動にもかかわらず、月末に至ってもなお多くの人がガレキの下に埋もれているなど、被害は拡大、すでに300人に迫る死者数が公表されている。
イタリアは日本と同じく火山、プレート境界、活断層など災害要因多重国であり、本来ならばわが国と同程度の防災体制が敷かれていても不思議はない。実際、イタリアでは過去に何回も大地震による被害を経験し、10年ほど前に発生した地震では“予知に失敗”として行政や学会の関係者が逮捕されるなど“防災珍事”も伝えられているが、国全体として本気で地震防災に対処している雰囲気が乏しく、長期的かつ地道な防災対策などに関心が向かわないことが原因の根本にある。また古い建物には耐震基準が適用されていないこと、歴史的建造物や街並み保全が優先され、対策が後手になっていることが原因である。大地震といっても熊本地震の十分の一以下のエネルギーと想定される割に被害が大きいのも、そのことが作用しているものと考えられる。防災士も国内の災害事例のみならず、折りに触れ、他国の地震等の被害実態も学び、もって自らの災害対応能力の強化に活かすという姿勢も重要であろう。
国や地方公共団体も、イタリアのみならず多くの国の災害事例にもっと関心を払った総合的防災政策を展開することが望まれる。世界標準を確立することで、防災先進国といわれる日本の防災制度(防災士を含む)や技術を他国に移転することがより円滑に進むからである。
〔個別の動き〕
1、熊本地震 九州で文化財被害300件超(文化庁)
九州地方で、多くの文化財が損壊するなどした熊本地震。文化庁によると、被害を受けた国の文化財は134件に上り、自治体指定分を含めると300件以上になるとみられる。被害の大きかった熊本城は修復には莫大な費用がかかるが、全国のゆかりのある城で支援の輪が広がっている。
被害が確認された文化財134件のうち、最多は熊本県の85件。震源地のなかった宮崎県や長崎県でも被害があった。
熊本市内にある県や市の指定文化財は72件が被災。市町村分も合わせると九州全体で300件以上に上るとみられ、件数は今後も増える見込みだという。
文化庁は震災による修復活動に、初のプロジェクトチーム(PT)を結成。担当者は「これほど大規模な損壊は前例がなく、省庁横断で対応が必要」とする。
複数の重要文化財が損壊した熊本城と縁がある城では支援活動が盛んだ。神奈川県小田原市の小田原城では耐震化工事を終えて10か月ぶりにオープンした5月1日の入場料収入を寄付するイベントを開催。熊本市へ計245万8,160円が寄付された。
熊本城を築城した戦国武将・加藤清正の主君、豊臣秀吉の居城、大阪城でも募金活動を開始している。
2、全国自治体庁舎3割「耐震性なし」(消防庁)
熊本地震で熊本県宇土市の庁舎が崩壊寸前になるなど、被災各地の庁舎がダメージを受ける中、全国の自治体庁舎の約3割が「耐震性なし」と診断されていたことが分かった。消防庁は建て替えも含めた自治体の対策を促す。
熊本地震では宇土市の庁舎が崩壊寸前になったほか、八代市、人吉市、大津町、益城町で庁舎がダメージを受け、代替施設での業務を余儀なくされている。災害対応の司令塔となるべき庁舎の被災は、人命救助や被災者の救援活動の遅れにつながる恐れがある。
調査は昨年5~6月、都道府県を通じ全ての市町村の木造建築以外の2階建てか、延べ床面積200平方メートル以上の庁舎を対象に実施した。その結果、平成26年度末現在で、9,159棟中、28.9%に当たる2,643棟は震度6強程度の地震で倒壊の恐れがあるなど、耐震性に問題があることが明らかになった。
3、新耐震基準でも家倒壊(建築学会)
熊本地震で被害が大きかった熊本県益城町の町役場周辺で、2000年の耐震基準改正以降に建てられたとみられる木造家屋400~500棟のうち4~9棟が倒壊していたという調査結果が、日本建築学会の調査報告会で発表された。施工不良や、壁の配置が十分に考慮されていなかった可能性がある、と指摘している。
日本建築学会では5月3~8日に、専門家約200人でチームを結成し、益城町役場周辺の約2,600棟の被害状況の調査を実施した。全体の7割ほどが木造家屋だったという。
1981年に改正された耐震基準は、大地震でも家屋が倒壊しないことを目指している。阪神・淡路大震災の教訓から、2000年にさらに強化されたが、「命を守るための最低限の基準」でしかない。今回の調査でも、倒壊はしなかったものの大きく壊れた全壊家屋が別に6~8棟あった。今回の集計は途中段階で、倒壊・全壊の区分などは今後精査し確定する。
倒壊や全壊していた家屋の中には、柱やはりを固定する所定のくぎが使用されていなかったり、窓などの開口部が大きくとられていたりしたものがあった。
4、日本海溝沖、震災で高まるリスク 大津波を生む断層を調査へ(海洋研究開発機構)
海洋研究開発機構は、大きな津波が生じやすい「アウターライズ地震」を起こす断層について、東北地方の日本海溝沖合で本格的な調査を開始した。東日本大震災の影響で、大地震が誘発される恐れがあり、津波の浸水域を即時に予測して、減災に生かす仕組みづくりを目指す。
アウターライズとは、海溝の外側で沈み込む海洋プレート(岩板)が盛り上がっている場所のことをいう。浅い部分が引っ張られ、断層が上下方向に動く地震が起きるとされ、揺れは小さくても海底の変動が大きいため、津波が巨大化しやすく、大震災の影響で発生リスクが高まっている。
同機構が調査するのは、日本海溝の東側で、岩手県沖から福島県沖にかけての南北約700キロ、東西約150キロの海底。日本海溝の西側に延びる大震災の震源域に隣接している。
調査は、海底下の探査や地震観測によって断層の分布を調べ、それぞれの断層が動いて地震が起きたと想定、発生する津波を計算する。沿岸の地形などを基に津波の高さや到達時間、浸水域を求め、平成31年度までにデータベースを構築することにしている。
そして、地震が起きた時、防災科学技術研究所が設置した海底地震計や津波計の観測結果から、震源断層を即座に特定し、行政側がつくる津波の即時予測システムにデータを役立てることにしている。
気象庁の津波警報と違って、沿岸の浸水範囲がすぐに分かる利点があり、住民の確実な避難につながると期待されている。当面は、東北の港周辺など3地域を予測対象とする計画だ。
アウターライズ地震は、巨大地震の後に起きやすく、明治三陸沖地震後の昭和8年に起きたマグニチュード8.1の昭和三陸沖地震がこのタイプだ。最大約30メートルの津波で、約3,000人が犠牲になった。東日本大震災にもM8級地震が懸念されており、備えが不可欠といえる。
5、首都圏直下地震で14万人派遣 全国から1都3県に救援(内閣府)
首都直下地震に備えるため政府は、発生直後に国や自治体が行う人命救助や救援物資輸送のための応急対策活動計画をまとめた。計画では、全国から最大で警察1万4,000人、消防1万6,000人、自衛隊11万人の応援部隊を動員。生存率が急激に下がる「発生から72時間」までに救助を本格化させるため、高速道路や国道など93区間を緊急輸送ルートに指定。医療ニーズへの対応では、約1,400の災害派遣医療チームを呼び寄せ、1都3県で150に上る災害拠点病院を活動拠点とする。食料などの必要物資は、被災地の要請を待たずに5,300万食、毛布34万枚などを、8か所の広域物資輸送拠点に届けることにしている。
6、東日本大震災の火災398件 揺れで出火、半数が「電気」(日本火災学会)
東日本大震災で発生した火災は岩手、宮城、福島など17都道県で計398件に上っていたことがこのほど、日本火災学会がまとめた調査で分かった。火災の内訳は、主に地震の揺れによる火災239件、津波による火災159件だった。
揺れによる火災のうち、約半数の122件は、電気器具や配電盤から出火する「電気火災」で、揺れを感知して電気を遮断する「感震ブレーカー」を設置する重要性が、あらためて浮き彫りになった。
注目されるのは、揺れによる火災の中で、電気火災が122件(51%)と多かった点だ。このうち、約100件は電気ストーブにタオルなどの燃えやすい物が落ちてきたり、落下物で電気器具のスイッチが入ったりして出火したとみられる。
なお、停電の有無に関係なく、有効な防御となる感震ブレーカーの設置率は6.6%(2013年の内閣府調査)にとどまっているのが現状だ。
7、地震保険支払い 阪神超す見込み(損保協会)
熊本、大分の両県で発生した一連の地震について、日本損害保険協会は、地震保険金の支払いが4万342件、約610億円に達したと発表した。阪神・淡路大震災に次ぐ過去3番目の規模。地震保険制度の認知度が高まってきたことが、支払件数・金額を押し上げている。
県別では、熊本県が3万3,362件、約564億円▽大分県3,143件、約23億円▽福岡県3,144件、約19億円―などとなっている。
契約内容に関する相談などを含めた事故受付件数は、すでに15万件を突破した。阪神・淡路大震災で、保険金の支払いに至った事例は6万5,427件、約783億円だった。今後、これを上回り、過去2番目の規模になる可能性が濃厚だ。
8、耐震化は待ったなしだ(消防庁)
熊本地震では、市や町の庁舎や病院など重要な防災拠点の損壊が相次ぎ、応急対応に支障が出た。
熊本県宇土市の5階建て庁舎は、4月16日の「本震」で4階の天井が崩れた。熊本地震で庁舎が使用できなくなった自治体は、八代市や益城町など5市町に上る。
患者の命に直結する病院の被災も深刻だった。災害拠点病院だった熊本市民病院は、「本震」で壁などに亀裂が入り、病院機能の維持ができなくなった。約200人の入院患者は防災ヘリコプターや救急車で緊急転院した。40を超える医療機関が一時、正常運営できなかった。
消防庁は、地震などの災害発生時に応急対策の実施拠点となる公共施設の耐震化進捗状況を毎年調査している。避難所として利用される学校や体育館のほか、警察署や消防署、病院、自治体庁舎などが含まれる。2014年度末で、防災拠点の耐震化率は全国で約88%だ。
ただし、自治体庁舎の耐震化率は最も低く約74%にとどまる。病院も約85%で平均を下回る。
自治体庁舎の耐震化工事は、財政上の理由で優先度が低く、後回しにされることが多いという。
だが、熊本地震の例をみれば、被災者の生活再建の第一歩となる罹災証明書の発行が益城町などで大幅に遅れている。他の市町でも役所機能が分散され、被災者はあちこちの窓口を訪ね歩かねばならない。高齢者の負担は小さくないだろう。
大規模災害直後に行政が機能不全になることのダメージの大きさが分かった。今回の教訓を踏まえ、自治体は予算を優先的に確保し、庁舎の耐震化を急ぐべきだ。
耐震化工事に当たっては、補助金など国の財政支援策がある。支援額の拡充はもとより、自治体が利用しやすい仕組みについても知恵を絞り、国全体で耐震化を後押ししたい。
1981年に施行された現行の耐震基準は「震度6強から7の地震が起きても、人命に危害を及ぼすような倒壊をしない」と定める。この基準は一般住宅も防災拠点も同じだ。2度の震度7が発生した今回の地震では、現行耐震基準を満たした益城町役場も被害を受けた。防災拠点の耐震基準強化の必要性も検討課題だろう。
庁舎が被災しても、被災者への対応に遅れが出ないことが肝心だ。被災直後も業務を遂行するために作るのが事業継続計画(BCP)だ。計画では庁舎の代替施設や、職員の招集体制などを事前に決めておく。
首都直下地震に備え、中央省庁で策定が進むが、地方自治体は遅れている。庁舎が利用不能となった宇土市や益城町はBCPがなかった。全国共通の課題だ。策定を急ぎたい。
9、罹災証明、ようやく手に 熊本・益城町 生活再建へ一歩(益城町等)
地震で損壊住宅が5,000棟を超えた熊本県益城町は5月20日、罹災(りさい)証明書の発行を始めた。多くの自治体は発行を進めるが、益城町は役場が被災、職員も避難所運営に忙殺され対応が遅れていた。被災者は地震発生から1か月を過ぎ、ようやく生活再建に向けた一歩を踏み出す。
罹災証明書は自治体が建物の被害状況を調べ、損壊の程度に応じて「全壊」「半壊」「一部損壊」などと判定して発行。被災者生活再建支援金の受け取りや仮設住宅の入居といった公的支援を受ける際に必要となる。
県によると、5月18日までに33市町村が計11万2,760件の申請を受けたが、発行は約3割の3万5,984件にとどまっている。南阿蘇村では5月19日に発行が始まった。益城町では4月30日から住宅や店舗、倉庫など計1万7,000棟を対象に調査を始め、5月18日までに1万662件の罹災証明書の申請があった。
益城町は、被災者の情報や建物の被害状況などの情報を一括で管理する「被災者台帳システム」を利用。同様のシステムは熊本市や南阿蘇村など14市町村でも使われている。
10、家の応急修理 申請進まず(熊本県)
熊本地震で、家屋の補修を自治体が支援する「住宅応急修理」の利用が進んでいない。半壊以上の被害が確認された熊本県25市町村への申請は計202件にとどまり、完了した工事はない。罹災(りさい)証明書の発行など、被害調査が遅れているためだ。修理額は最大57万6,000円に限られ、不満を訴える被災者も多い。熊本県によると、住宅被害は9万棟を超え、9万592棟になった。
制度は本来、1か月以内に修理を終え、避難所から自宅に戻ってもらうのが目的。修理対象は半壊以上の住宅で、仮設住宅に住む場合は利用できない。熊本より住宅被害が少なかった2004年の新潟県中越地震では約5,800件(県の独自支援除く)の利用があった。
熊本でも相談が多数寄せられている。当面7月中旬まで申請を受け付けるが、業者不足も予想され、早期に工事ができる態勢が求められる。
被災者は所得証明、罹災証明などの書類を添えて市町村に申請、審査を受ける。申請が低調な理由について、熊本市や御船町など多くの自治体は罹災証明書の発行遅れを挙げる。
▼住宅応急修理
災害救助法に基づき、地震や大雨などで大規模半壊か半壊した家屋を住めるようにする制度。主に一戸建てを想定し、全壊も修理可能な場合は利用できる。半壊は家族構成などで年収800万~500万円以下に限る要件がある。補助金ではなく、自治体が「現物給付」として修理する。対象は建物の基礎や柱、床、屋根のほか、ドアや配管、トイレ、浴室など日常生活に欠くことのできない部分。
11、津波被災地60ヘクタール 格安で貸し出し(仙台市)
仙台市は沿岸部の市有地計60ヘクタールを民間に格安で貸し出すことを決め、活用法の募集を始めた。市有地は東日本大震災の津波で浸水し、住民が内陸部の高台に集団移転した跡地。市はにぎわいの場の整備を目指しているが、商業施設などの進出は見込みにくい。市は「行政では出てこない柔軟な発想が欲しい」(奥山恵美子市長)と、異例の公募で復興につなげる。
土地は災害危険区域に指定され、住宅を建てられない0.5~38ヘクタールの大小5地区。浸水した場所で本格的な企業進出は期待できないため、市は「土地の賃料をほぼ無料に近い低額に設定する」(復興まちづくり課)。
活用法は企業や個人、NPOなどから飲食店やイベント施設などのアイデアを募集する。市は応募案をもとに活用方針などを決め2016年度中にも改めて具体的な事業計画を募る。
土地は国の交付金を使い、市が約100億円で地権者から買い上げたが、除草などの管理費が年間2億円かかる。このため、市は有効利用策を検討してきた。投資額を抑えたい起業家やNPOなどの斬新なアイデアを期待している。被災地の沿岸部では同様の集団移転跡地の利用が課題となっている。
12、熊本地震1か月 経済損失5,000億円規模(内閣府)
熊本県で震度7を記録した地震は5月14日、発生から1か月を迎える。同県などによると、交通インフラや農林水産業の経済損失は5,000億円規模で、建物損壊は8万棟を超えた。避難所などで暮らす被災者はなお1万人以上に上る。
政府は、復旧に向けた7,780億円の2016年度補正予算案を決定。インフラ再建に使う7,000億円の「熊本地震復旧等予備費」を創設。被災者生活再建支援法に基づき、被災者に最大300万円を支給する。熊本、大分両県の交通インフラの被害が3,200億円になる見通し。
13、地震後 相次ぐ窃盗(警察庁)
熊本県などでの一連の地震で、被災した住宅を狙った空き巣などの犯罪が相次いでいる。義援金の募集を装った不審な電話もあり、警察や国民生活センターは注意を呼びかけている。
熊本県警によると、震災関連の窃盗などの事件は、未遂を含め5月2日現在で34件確認された。
事件は窃盗にとどまらない。
善意につけこんで金を借り、そのままだまし取る「寸借詐欺」の典型的な手口もある。
警察庁の調べでは、「義援金」などをかたる不審な電話は全国で9件確認された。
14、関西自治体 熊本支援の輪(地方公共団体)
熊本を中心とする地震の被災地に向け、関西の自治体が支援の輪を広げている。阪神・淡路大震災の経験で得たノウハウを生かした取り組みなどで被災者をケアし、復旧や復興を後押しする。
神戸市は熊本地震の復興を支援する市民活動への助成「パートナーシップ活動助成」を始めた。NPO法人やボランティアなどを対象に最大50万円を支給する。東日本大震災の際も実施している。避難生活が長期化するなか、被災者の心のケアやまちづくりといったより専門的なノウハウが必要と判断した。
兵庫県では阪神・淡路大震災の際に避難所運営に携わった教職員らで構成する県の組織「震災・学校支援チーム(EARTH)」が、避難所となった学校58校を回っている。避難所の運営支援のほか、教職員や子どもたちの心のケア、学校再開に向けた助言を実施する。
被災者の受け入れも進める。和歌山県は要望があれば大型連休が終わるころに県内のホテル・旅館に約1,000人の避難者を受け入れられるようにする。
近畿など8府県4政令指定都市でつくる関西広域連合では「何よりも支援金を早く支給することが重要。被害認定調査を急ぐ必要がある」とする。熊本地震では家屋の応急危険度判定は大半が終わったが「罹災(りさい)証明書」発行のための被害調査はこれからだ。それがないと、被災者は被災者生活再建支援法に基づく支援金(最大300万円)を受給できない。
早期の被害調査に向けて広域連合は、被害の大きかった熊本県益城町に5府県の専門職員17人を派遣し、重点支援に乗り出した。
15、罹災証明 手続き本格化(熊本県)
熊本地震の被災地で、住宅が被災したことを証明する「罹災(りさい)証明書」の発行申請が熊本県内で4万7,000件を超えた。益城町でも受け付けが始まり、2日間で5,619件の申請があった。今後も増える見通しだが、職員の不足で発行手続きは遅れている。生活再建に影響が出る可能性もある。
罹災証明書は被災者からの申請を受けて市町村が住宅被害を調査し、「全壊」や「半壊」などと判定した上で発行する。被災者が支援を受けるための証明となる。
熊本県によると、22市町村で発行を予定している。各自治体の集計では、申請件数は熊本市が最多の計3万2,206件。ほかに御船町が2,650件、宇城市が2,500件、甲佐町が1,478件、南阿蘇村が771件など。
しかし発行は進んでいない。御船町、宇城市、甲佐町、南阿蘇村はいずれもゼロ。熊本市は即日発行できる「一部損壊」だけで、「全壊」「半壊」は「調査が必要で、まだ発行していない」。
発行には建物被害の現地調査が必要だが、職員数が足りず追いついていない。益城町は県外からの応援を含め、最大120人ほどがあたる予定。
罹災証明が必要な支援策の例
| 給付 |
|---|
| 被災者生活再建支援金、義援金など |
| 融資 |
| 住宅金融支援機構融資、災害援護資金など |
| 減免・猶予 |
| 税金、保険料、公共料金、高速道路の通行料など |
| 住宅 |
| 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理 |
16、熊本 土砂災害54か所(国土交通省)
熊本県などでの一連の地震で、土石流や急傾斜地崩壊などの土砂災害が少なくとも同県内54か所で起きていたことが、国土交通省の調査で分かった。同省は県に応急的な対策を求めた。河川では、堤防のひび割れや橋の崩落などを県内計288か所で確認した。
17、家屋倒壊で死亡37人 うち20人 旧耐震基準(熊本県)
熊本県などでの一連の地震で犠牲になった49人の死亡時の状況を分析したところ、7割超の37人が家屋の倒壊で、2割弱の9人が土砂災害で亡くなっていたことが分かった。家屋倒壊で死亡した37人中、少なくとも20人がいた家屋は、耐震基準が厳しくなる1981年6月以前に建てられたことも判明。土砂災害の9人中7人は、事前の危険性周知などを義務づけた「警戒区域」でない場所で亡くなっていた。
南海トラフ地震など巨大地震への備えが全国的な課題となる中、住宅の耐震化や災害危険箇所の洗い直しが求められている。
「家屋倒壊死」の37人のうち7人は「前震」で、残り30人は「本震」で死亡。このうち少なくとも8人は、いったん避難所に行ったり車中泊したりした後、帰宅して亡くなった。
家屋倒壊死の37人がいた34棟のうち28棟は建物が登記されていた。うち17棟(19人が死亡)が、震度6強~7程度で倒壊しないことを目標とする「新耐震基準」が建築基準法改正で導入される前に建てられた木造家屋だった。親族らが「築100年以上」と証言した同県益城町平田の1棟を含めると、少なくとも導入前の建物は18棟(20人が死亡)に上った。
18、「倒壊の危険」1万2,000棟(国土交通省)
熊本地震で被災した建物の応急危険度判定で、倒壊の恐れがあり「危険」と判定された建物が1万2,013棟に上ることが、国土交通省のまとめで分かった。
同省によると、4月29日時点で熊本県内の18市町村で判定を実施。自治体別にみると、熊本市が4,039棟で最多、益城町が3,285棟、西原村が1,362棟と続いた。調査は続いており、棟数は増える可能性がある。
危険度判定は余震による二次災害を防ぐため、自治体職員らが建物の外観や周囲の状況から判断する。倒壊したり、焼失、津波で流されたりした建物については対象外。
過去の地震では東日本大震災が1万1,699棟、阪神・淡路大震災が6,476棟、新潟県中越地震が5,243棟だった。
19、土砂災害の危険 常に斜面監視を(土木学会)
熊本地震の被災地を調査した土木学会は、阿蘇地方では河川沿いの斜面などが崩れ、梅雨に入ると土砂災害が起きる可能性があるといい、斜面や河川の常時監視などの緊急対応が必要だ、と訴えた。今後、政府や自治体などに助言する。
阿蘇外輪山の西側斜面が4月16日未明の地震で大規模に崩壊した。学会によると、梅雨の大雨でさらに土砂が崩れて河川をせき止めると、水位が上がって決壊したときに土砂が一気に流れ出して甚大な被害を及ぼす可能性がある。
上流から流れ出した土砂が川底にたまり、洪水が起こりやすくなる危険もあり、下流の地域では、川底にたまる土砂にも注意を向ける必要がある。
20、新耐震基準の木造住宅 全壊最大17棟(建築学会)
日本建築学会は、熊本地震で震度7を2回記録した熊本県益城町で、耐震基準が強化された2000年以降に建ったとみられる木造住宅のうち、最大17棟が全壊したとする調査結果を明らかにした。強い揺れが続いたことに加え、設計の不備や施工不良が原因となった可能性がある。
熊本地震の発生後、専門家が現地調査した結果を14日の報告会で発表した。調査対象となる木造住宅のうち全壊は当初51棟とみられたが、その後の検証により最少10棟、最大17棟と判断した。このうち倒壊は最大9棟で、残りは傾くなどしていた。
現行の耐震基準は1981年に導入され、木造住宅は2000年に接合部を固定する金物の規定などが厳格化された。益城町で損傷が大きかった住宅は、金物が不良だったり壁の配置が悪かったりといった傾向がみられたという。
今回の地震では、現行の耐震基準を満たした住宅なども多数全壊した。震源が広範囲に及び、同じ場所が繰り返し強く揺れたことが大きな建物被害につながった。似たような地震が他の地域で発生する懸念もあり、政府は原因となった断層帯の調査を強化する。
4月14日の「前震」、同16日の「本震」の震源となった日奈久(ひなぐ)断層帯と布田川(ふたがわ)断層帯は、不安定な状態が今も続く。日奈久断層帯の南西部、八代市や水俣市の周辺などには、ずれきらなかったひずみが残り、新たな地震の発生につながる可能性がある。
政府の地震調査研究推進本部は、これらの断層帯を改めて調査する方針だ。掘削調査や地形の観察などから過去の活動時期や地震の際のずれの大きさ、断層の分布状況などを調査する。熊本県の震源から約100キロメートル離れた大分県でも、本震の直後に大きな地震が起きた。
日本には2,000以上の活断層があるとされる。新潟県から長野県や岐阜県を経て神戸市に至る「ひずみ集中帯」など、同規模の地震が連鎖する恐れがある場所は複数ある。
震度7が2度起きた熊本県益城町を日本建築学会九州支部が調査したところ、耐震基準が厳しくなった2000年以降に建ったとみられる木造住宅51棟が全壊していたことが判明。続けて起きる地震に対して建物の耐震性をどう確保するかも、新たな課題として浮上した。
建物の土台と柱を固定する接合部が壊れていた事例もある。
21、民泊を全面解禁、住宅地で営業(厚生労働省)
政府は一般住宅に旅行者らを有料で泊める「民泊」の全面解禁に向けた原案をまとめた。マンションなどを所有する貸主がネットで簡単な手続きを済ませれば、旅館業法上の許可なしで部屋を貸し出せるようになる。いまは禁じている住宅地での営業も認める。都市部を中心に足りなくなっている宿泊施設を増やし、訪日外国人の拡大につなげる。
民泊をめぐっては厚生労働省が4月に旅館業法の政令を改正し、カプセルホテルなどと同じ「簡易宿所」の位置づけで営業できるようにした。しかし、あくまで旅館業法の規制を受けるため、米エアビーアンドビーといった仲介業者を通しても住宅地などでの民泊は違法な状態が続いている。
政府がまとめた全面解禁案は、マンションや戸建て住宅の所有者に関する規定を緩め、だれでも民泊に参入しやすいようにしたのが特徴だ。
新法では、ネットを通じて都道府県に必要な書類を届け出れば、帳場の設置などを義務づける旅館業法上の許可がいらなくなる。届け出書類には自分が登録する仲介業者のほか、税と社会保障の共通番号(マイナンバー)を記せば、住民票を添えなくてもいい。住宅地での民泊も解禁し、対象地域を大幅に広げる。
部屋の所有者が宿泊させたくないと考える客は、申し込みがあった段階で断れるようにする。ホテルや旅館など旅館業法上の施設は客が感染病にかかっている場合などを除き、宿泊を拒否できない。個人に同じルールを課せば、民泊をやってみようと思う意欲をそいでしまうと判断した。
一定の要件も課す。旅館業法の許可を得て営業しているホテルや旅館に配慮し、営業日数に上限を設ける方向だ。英国が年90泊、オランダが年60泊までに限っており、諸外国の事例を参考に日数を設定する。一度に宿泊できる人数も制限するかどうかを検討する。ドイツでは8人以内との決まりがある。玄関には民泊サービスの提供を表示することを義務づける。
ただ、条件を厳しくしすぎると、民泊事業への参入をめざす個人や企業の動きに水を差す恐れがある。営業日数を制限すれば採算を合わせるのが難しくなるため、関係業界からは反発が出そうだ。2020年までに訪日客を年間4,000万人に増やす目標の達成を妨げる懸念もあり、政府は慎重に新法の詳細を詰める。
22、地下街の防災「改善を」(総務省)
総務省は、全国の10市区にある14地下街の浸水と防火対策を抽出調査したところ、一部で不備があったと発表した。
具体的には、店舗やビル管理者でつくる安全対策の協議会に必要な関係施設すべてが参加していなかったり、緊急事態を知らせる連絡リストに漏れがあったりした。
調査対象の10市区は札幌、横浜、名古屋、大阪、神戸、岡山、福岡の各市と、東京都千代田、中央、新宿の3区。
10市区にある14地下街のうち、1か所で予防策や災害時の態勢を取り決める協議会に関係施設の一部が参加していなかった。
2か所で緊急事態を知らせる連絡リストに未登録の施設があり、災害発生の覚知が遅れる可能性があることが分かった。
23、消防救助隊 5,301隊に増加(消防庁)
消防庁は、地震などの大規模災害時に全国から被災地に派遣される緊急消防援助隊の登録数が4月1日時点で5,301隊になったと明らかにした。前年より317隊増えた。
緊急消防援助隊は阪神・淡路大震災で他地域からの応援部隊の到着が遅れた反省から1995年に発足。2015年度は5月に発生した鹿児島県の口永良部島噴火や9月の関東・東北豪雨で出動した。
政府は首都直下地震や南海トラフ巨大地震に備え、2018年度末までに6,000隊にすることを目指している。
24、地震速報 障害者に配慮(気象庁)
防災関連システム開発のアールシーは緊急地震速報を配信するスマートフォン(スマホ)向けアプリに、目や耳が不自由な人に配慮した機能を追加した。震度に応じて通知音を変えたり、色弱の人が区別しやすい色を選べたりする。熊本地震を受けて寄せられた要望に対応した。
新機能はスマホアプリ「ゆれくるコール」に追加した。通知音は視覚障害者からの要望を踏まえ、震度5弱以上と4以下で変えられるようにした。スマホ画面を見ずに、音だけで大きな地震かどうかが分かる。
各地の震度を色分けして表示する画面では、色弱の人でも区別しやすい色を選べるようにした。このほか、震度3以上の地震は発生から約1分半後に各地の震度を速報するようにした。
同社は気象庁が発表する緊急地震速報を活用。利用者が事前に設定した地点の予想震度を配信するサービスなどを提供している。今後も機能を順次追加していく方針だ。
25、地震マニュアル「改訂が必要」(気象庁)
気象庁は、最大規模の「本震」の判断基準や、余震の確率を評価する手法について「改訂が必要」という認識を示した。
過去の経験則に基づきM6.4以上であれば「本震」と判断していた従来のマニュアルの見直しに言及。前例がないような地震に備え「科学技術を総動員して対応する必要がある」と話した。
26、要援護者を訪問調査(熊本県)
熊本県内自治体は、地震後に自宅で暮らす高齢者や障害者ら要援護者の訪問調査に乗り出した。対象は数万人規模になるとみられ、専門のケアが必要な人は福祉避難所を紹介するなど対策を取る。
熊本市の調査対象は概算で、要介護3以上の高齢者約1,500人や障害者約9,000人、妊産婦など合わせて1万3,000人以上。益城町は、約1万3,000の町内全世帯を対象とし、高齢者のほか障害者約780人を調べる。
熊本市では、建物が被災した熊本市民病院の看護師と他の自治体から派遣された保健師計100人が高齢者調査を担当。障害者は市から委託を受けた民間事業者とNPO団体「日本相談支援専門員協会」が請け負う。
益城町の高齢者調査は、ケアマネジャーの団体「日本介護支援専門員協会」(東京)が被害の大きい地区からローラー作戦を展開。全国から交代で協会員が応援に入る。
自宅で暮らす要援護者は、地震の前から訪問介護などのサービスを受けていた高齢者らに比べ自治体が情報を把握しづらいのが課題となっていた。
27、四国沖など「ひずみ」強く(海上保安庁)
巨大地震発生が危惧される「南海トラフ」沿いで、プレート(岩板)のひずみが四国や静岡県、愛知県の沖合などに蓄積されているとする分析結果を海上保安庁がまとめた。ひずみの分布が明らかになるのは初めてで、地震や津波の被害予測に有用なデータとなる可能性がある。
南海トラフは、東海沖から九州沖へと延びている海側のプレートと陸側のプレートが接する境界。陸側プレートが地下深くへ沈む海側プレートに引きずられてひずみ、限界に達すると反動で大きな地震や津波を起こす。
海保は2006年度から2015年度まで、海底15か所の観測点を調査。1940年代に起きた東南海・南海地震の震源域の西側などで、強いひずみがたまっているとする分析結果をまとめた。ひずみの分布から、地震の発生時期や震源などを推定するのは難しいという。
28、噴火に「保険」(損保会社)
火山が噴火した際に一定額を支払う金融派生商品が6月から世界で初めて販売された。温泉地などの観光業者が購入すれば、風評被害での打撃を軽減する「保険」として活用できる。火山の近くに工場を置く企業などに積極的な投資を促す効果も見込める。まず富士山で商品化し、今後対象とする火山を増やす。
新商品は噴火が観測され、気象庁が噴火警戒レベル3(入山規制)以上と認定した場合に、1口年間30万円のオプション料に対して1000万円を支払う仕組み。
研究機関と協力し、富士山について過去1200年に及ぶ古文書の記述を分析して噴火の発生確率を算出。富士山は1707年の宝永噴火から約300年噴火していないが、地下ではなお火山活動が続いている。
29、「3日分備蓄」48%どまり(東京商工会議所)
東京商工会議所は会員企業を対象に実施した防災に関するアンケート調査結果を発表した。東京都が条例で定める「全従業員の3日分以上の備蓄」がある企業は飲料水で48.0%、食料品で44.7%と、いずれも半数以下だった。非常時の事業継続計画(BCP)の策定率も25.9%と低水準で、企業の災害への備えが進んでいない状況が改めて浮き彫りになった。
2011年の東日本大震災の際、街に帰宅困難者があふれた反省を踏まえ、都は2013年4月に帰宅困難者対策条例を施行。企業で働く人には事業所などにとどまり、一斉帰宅を控えてもらう方針を打ち出した。企業には努力義務として全従業員の3日分の備蓄を求め、さらに従業員以外の帰宅困難者用に10%余分に備蓄するよう呼びかけている。
同条例の認知度は67.2で前年比0.8ポイント増とほぼ横ばいだった。品目別の備蓄割合は災害用トイレが31.1%と特に低い。従業員以外のために10%余分の備蓄をしている企業は17.3%にとどまる。一時滞在施設として外部の帰宅困難者を受け入れることについては72.8%が「難しい」と回答した。理由として半数が「スペースがない」ことを挙げた。
30、震災関連死「県が審査を」(熊本県)
熊本地震による「震災関連死」の認定を巡り、南阿蘇村など熊本県内5市町村が県による審査を要望していることが分かった。市町村単位の審査では認定にばらつきが出る恐れがあり、医師や弁護士ら専門家も不足しているというのが理由だ。
東日本大震災の関連死認定率は、市町村単位の審査会に比べ、県の審査会の方が低い傾向にあった。日弁連などからは「実情を把握できるのは市町村。誤った審査は(訴訟などで)長時間、遺族を苦しめる」と異論も出ている。
災害弔慰金支給法などは、災害で死亡した遺族に500万~250万円を支給すると規定。避難中などの関連死も対象だ。関連死に該当するかどうか全国統一の基準はなく、原則として市町村の審査会を経て認定。県に審査の委託もできる。
熊本地震で県はこれまで9市町村の男女20人を「関連死の疑い」と公表。避難先での心肺停止のほか、「車中泊」後に肺梗塞と診断された例もあった。ただ9市町村とも関連死の判断基準はなく、疑い例としたのは「避難所で亡くなった」(阿蘇市)、「主治医の判断」(嘉島町)とする。
宇土市、阿蘇市、高森町、御船町、南阿蘇村が県による審査を希望した。
熊本市は「素早く判断できる」、益城町は「より遺族に近いところで審査するのが誠意」として、独自に審査会を開く方針。県は「審査を受託するか決めていない」としている。
31、危機意識、太平洋側で高く(防災白書・内閣府)
地震や台風など大きな自然災害に対する危機意識は太平洋側の住民に高く、日本海側は相対的に低い傾向であることが、内閣府の調査で分かった。太平洋側では南海トラフ地震や首都直下地震などへの警戒が高まっているためとみられる。一方、災害への備えに取り組んでいる人は4割弱にとどまっている。
本年度の防災白書の中で、全国の15歳以上の1万人を対象にした防災意識・活動に関するインターネット調査(2月実施)の概要が明らかになった。
住んでいる地域で今後30年以内に大災害が発生すると思うかを尋ねたところ、「ほぼ確実に発生する」が16%、「発生する可能性は大きい」が47%。合計で63%だった。
内閣府はこの合計値について、全国を7地域に分けて平均回答率を分析。東北から関東の太平洋側(岩手、茨城など)、関東南部(東京、埼玉)、本州の太平洋側(静岡、和歌山など)、四国と九州東岸・沖縄の4地域で70%を超えた。一方、北海道と東北の日本海側・北陸、中国と九州の東岸以外(福岡など)の2地域は50%未満だった。
地域別では最大30ポイント前後の差があったとみられる。内閣府は「東日本大震災以降、首都直下地震や南海トラフ地震など、太平洋側の被害を想定した災害の情報が頻繁に発信されてきた影響ではないか」とみている。熊本地震が発生した熊本県は50%未満の地域だった。
非常食の常備や家具の固定、防災訓練への参加といった災害への備えについては「十分取り組んでいる」が3%、「できる範囲で取り組んでいる」も34%にとどまった。
内閣府は防災意識を高めて実際の取り組みにつなげてもらうため、情報発信や職場単位などでの啓発活動を強化するとしている。
32、地震の被害予測システム 「連続揺れ」の影響考慮(内閣府)
内閣府は、地震発生時の被害予測システムに、熊本地震のように強い地震が続けて起きる「連続揺れ」の影響を盛り込むと発表した。今年度中に改良版を完成、試験運用を始める見通し。
システムは防災科学技術研究所などが開発中。地盤のデータや主な建物の構造、高さなどの情報を組み合わせ、地震が発生して10分以内に、どの地域でどのくらい建物が倒壊するかを推定する。
これまでに試作したシステムは連続揺れを想定しておらず、4月の熊本地震の際には最初の揺れの被害は精度良く推定できたが、本震発生時はうまくいかなかった。
地震で損傷した建物が繰り返し大きな揺れに襲われると倒壊の危険が増す。そのため公共施設などに取りつけたセンサーで実際の揺れを細かく計測し、連続揺れの影響を盛り込んでより正確に予測できるよう改良する。
33、防災基本計画 政府が見直し(内閣府)
政府の中央防災会議は、河川堤防の決壊で多数の犠牲者が出た昨年9月の関東・東北豪雨を踏まえ、防災基本計画を修正した。水害時に建物の2階以上まで浸水が予想される場所を自治体がハザードマップ(危険予測地図)に明記し、住民に早期避難を促すことなどが柱。各自治体はこの基本計画に沿って地域防災計画をつくる。
複数河川の氾濫や土砂災害が同時に起き、自治体が指定した避難所にたどり着くのが難しい住民もいると想定。近くの市町村に広域避難できるような態勢をつくるべきだとした。
関東・東北豪雨では、自治体が避難勧告を出すタイミングや対象区域を決めていなかったことが課題に挙がった。基本計画は、災害時に市町村が取るべき対応をまとめた手引を国が作成し、全国に配布するよう求めた。
34、「本震→余震」の常識覆る(気象庁)
「これまでの『本震―余震』型の予測手法では不十分」。熊本地震から約1か月後の5月13日、政府の地震調査委員会は余震を評価する手法を見直すことを明らかにした。
1926~95年に起きたマグニチュード(M)5.5以上の内陸直下型地震153例を分析した結果から、調査委は1998年に評価手法を作成。M6.4以上なら「本震」とみなすことにした。これに沿う形で気象庁は熊本地震で4月14日のM6.5の地震を本震と判断した。
その後、16日にM7.3の地震が発生。気象庁は14日の地震を前震、16日を本震と改めた。国内では前例に乏しい現象だが、「想定外」で片づけてよいのか。
15日未明に発生したM6.4の余震に注目する。余震は最初の地震よりマグニチュードが1ほど小さくなることが多いが、15日未明の余震は14日の前震とほぼ同じ規模だった。この時点で連鎖の可能性を疑うべきだった。
地震が別の地震を誘発する要因は大きく2つある。一つは大地震の発生で周辺の地下にかかる力が変化することだ。震源から特定の方向の領域でひずみが増え、そこにある断層で地震が起きやすくなる場合がある。もう一つは地下を伝わった地震波による活断層への刺激。ひずみがたまっていると揺さぶられた断層は動きやすくなる。
熊本地震の本震発生後、北東の阿蘇地方や大分県側にも震源域が広がった。地下の力の変化や揺れによる刺激が連鎖の引き金になったと考えられる。さらに火山帯との関連では、火山に近い地域は地震が連鎖しやすいことが分かっている。震源域となった熊本や大分は阿蘇山や九重山といった活火山があり、日本有数の温泉地も多い。
熊本や大分には、別府―島原地溝帯と呼ぶ地質構造が広がる。この地域では地盤を南北に引っ張る力が働く。地下深くでは、高温・高圧の液体が上昇しようとしている。これが地震に伴う揺れやひずみの影響で、地下の岩盤に入り込んで断層を滑りやすくした可能性がある。
九州では、過去にも地震が立て続けに起きてきた。1975年には阿蘇地方や大分県西部で、1997年には鹿児島県の薩摩地方でM6級の地震が連発した。御嶽山などがある長野県西部や伊豆地方といった火山に近い地域でも、連続的な地震が観測されてきた。
中部地方の糸魚川―静岡構造線断層帯や紀伊半島から四国を横切る中央構造線断層帯も活断層が集まる。いったん大きな地震が起きると、連動する恐れがある。2,000を超す活断層がひしめく日本では、地震の連鎖は今後も起こりうる。
1995年の阪神・淡路大震災後、危険度の高い活断層の調査は進んだ。しかし、地震発生の履歴を正確につかむのは難しい。地震を誘発させる連鎖の仕組みは未解明な部分がさらに多く、研究を重ねて知見を充実させる必要がある。
35、復旧費の75%補助(財務省)
財務省は熊本地震の復旧に向け、今月成立した約7,800億円の補正予算のうち1,023億円の使い道を固めた。熊本県や大分県で被災した中小企業の施設などの復旧について、費用の75%を国と自治体が補助する仕組みを使って事業者の負担を25%に抑える。部品の供給が停滞するなど経済への影響が大きいため、手厚い支援で中小企業の再建を後押しする。
熊本地震対策では、5月に総額7,780億円の補正予算が成立した。そのうち7,000億円分は使途が決まっていない予備費だったため、財務省が早急な対策が求められる分野を中心に第1弾の活用策を策定。
これまでは低利融資といった金融面の手当てが中心だったが、復旧費用の75%を補助金として支給する制度に400億円を拠出する。複数の事業者にまとめて支給し、地域全体の復興を加速する。
ホテルや旅館で大規模なキャンセルが相次いだ事態を踏まえ、九州全域で宿泊費を割安にする旅行券を自治体が発行するために180億円を充てる。外国人旅行客も対象とする方向だ。
36、全国の空き家情報集約(国土交通省)
国土交通省は全国の空き家や空き地の情報を集約し、購入希望者がインターネット上で条件に合う物件を見つけやすくする。地方自治体が個別に運営する「空き家バンク」の情報を一元化する。地方の人口減少や団塊世代の相続によって空き家は増え続ける見通し。税制などでの空き家対策に加えて情報提供を拡充することで、民間の不動産関連ビジネスの拡大につなげる。
空き家バンクは持ち主に物件情報を登録してもらい、購入や賃貸を希望する人に情報を提供する仕組み。国交省の調査によると68%の自治体が開設している。国交省は自治体ごとに異なる仕様を統一し、全国の物件をネットを通じて簡単に検索できるようにする。
背景には急増する空き家問題がある。全国の空き家は約820万戸と、20年で1.8倍に膨らんだ。2023年には住宅の2割にあたる約1400万戸に増えるとの予測もある。個人が持つ空き地も10年で1.4倍になった。
団塊世代の相続ラッシュや地方の人口減少で空き家や空き地はさらに拡大するとみられている。地域の防災能力や景観を損なう恐れがあるため、国や地方自治体は対応に乗り出している。
すぐに買い手や借り手が見つからないような物件は自治体への寄付を促す。東京都奥多摩町は空き家の寄付を募り、若者に固定資産税分の家賃で貸し出している。国交省はこうした先進的な自治体への支援策を検討する。
37、「丸投げ」排除へ判断基準(国土交通省)
マンションなどのくい打ち工事のデータ改ざん問題を受け、国土交通省は、実質的に施工に関与しない「丸投げ」を排除するため判断基準や、元請け業者と下請け業者の役割などを明確化することを決めた。
一連の問題の発端となった横浜市都筑区のマンションのくい打ち工事では、1次下請けが2次下請けに工事を丸投げしていた。問題発覚を受け建設業界の課題を議論してきた国土交通省の審議会では、丸投げが多重の下請け構造を生み、責任の所在が曖昧になるとの指摘があった。
丸投げは建設業法で禁じられているが、「実質的な関与の有無」の判断基準が曖昧だった。
国交省の改善対策案では、元請け業者、下請け業者ごとに実質的な関与の判断基準を明確に定め、業界への通達で周知することが盛り込まれた。
横浜市のマンションでは、工期が遅れる懸念からデータ改ざんを招いたとされるため、案には工事を円滑に進めるための指針を策定することも明記。指針では資材の納入遅延など予測されるトラブルを発注者と施工業者の間で事前に協議し、追加費用の負担や工期の延期などの対応を決めておくよう求める。
38、地震2か月、罹災証明待ち4万件(熊本県)
被災地では罹災(りさい)証明書の発行を巡る混乱が続いている。熊本県内の各自治体は迅速な発行に努めているが、家屋の被害判定結果に不満を抱き2次調査を申し込む住民が少なくない。詳しい調査には時間がかかり、完了は8月以降になりそうな自治体も。
罹災証明書は自治体が建物の被害状況を調べ、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4区分に判定して発行する。被災者生活再建支援金の受給や仮設住宅の入居といった公的支援を受ける際に必要となるが、被害の程度によって支援に差がある。判定結果に不服がある場合は2次調査を申請できる。1次調査が外観の調査のみで判断するのに対し、2次調査は屋内の被害状況まで詳しく調べる。
熊本県によると、罹災証明書は33市町村に対して計約14万6,000件の申請があったが、自治体が発行できたのは約10万3,000件。国は早期の生活再建に向けて5月中の発行を求めていたが、申請の3割、4万件余りが発行できていない。
罹災証明書を巡っては外観で判定する1次調査の結果に2割程度の人が納得せず、建物内も調べる2次調査を求めているとみられる。益城町は4分の1が2次調査に回っており「調査を終えるのに数か月はかかるのではないか」とみている。
約2,000件の罹災証明書の発行を5月末までに終えた西原村は2011年に東日本大震災を経験した宮城県石巻市などから職員の応援や助言を得ながら、2次調査を進めている。
西原村で被害判定の調査を担当する職員、坂本考幸さん(35)は「罹災証明書は生活再建の第一歩。住民に結果を納得してもらうには慎重な対応が必要だ」と自らに言い聞かせる。住民には審査基準のリストを配って自己点検を促し、経験豊富な東北地方の自治体の職員を交えた職員の実地研修も続けてきた。
だが家屋全体の被害を調べる2次調査は時間がかかる。同村によると、所要時間は1件あたり2~3時間かかることもあり、1班の職員が1日に調査できるのは3件が限度だ。申請件数が増えるなか、全ての調査を終えるのは8月以降になる可能性もあるという。判定作業を早めたいが、人手を増やそうにも審査ができる職員の数には限りがある。
39、熊本「住」トラブル多発(消費者庁・国民生活センター)
熊本地震の被災地で、賃貸住宅の契約や住宅の修理など住まいを巡る消費者トラブルが後を絶たない。中には生活再建を急ぐ被災者の気持ちを逆手にとった悪質な業者もいる。国民生活センターなどは「普段より慎重になり、各相談機関も活用してほしい」と呼びかけている。
消費者庁によると、地震が発生した翌日の4月15日からの1か月間で、消費生活センターや国民生活センターに、熊本県内から586件の地震に関する相談があった。同センターは4月末、九州地方から通話料が無料になる「消費者トラブル110番」を開設したが、6月に入っても多い日には数十件の電話があり、「需要がある限り続ける」という。
586件の相談の内容は住宅関連が7割を占めて最多で、なかでも不動産賃借についてが4割と多かった。賃貸住宅が損傷した事例では、「避難所にいるが家賃を払う必要があるか」「退去を申し出たら違約金を請求された」といった相談も多い。
同センターは「損傷の程度や契約の中身によって事情が変わる。家主と話しても解決しない場合は、専門家に相談してほしい」とする。
住宅の修理や建築に関する相談も目立つ。「ブルーシートを屋根にかけただけなのに、100万円を請求された」。ある被災者は業者に屋根の修理を頼んだところ、見積もりも明細も提示がないまま、高額な工事料金を請求された。「行政から補助金が出る」と説明する業者に屋根の修理を頼んだものの、契約後に補助は出ないと気づいた被災者もいた。
同センターは「複数の業者から見積もりを取ったり、家族に相談したりしてほしい」と呼びかける。訪問販売であれば、契約書面を受け取ってから8日以内はクーリング・オフも可能だ。
[防災短信]
- 01、繁華街の「木密」板挟み
~新宿ゴールデン街火災1か月、地域・行政両立への議論~ 2016年5月12日付
日本経済新聞(夕刊) - 02、収益で被災地支援ジャンボくじ発売
~1等5億円、ミニジャンボも~ 2016年5月12日付 産経新聞 - 03、熊本県内33万泊キャンセル
~九州全体では70万件、被害140億円以上 熊本県・九州観光推進機構~ 2016年5月14
日付 産経新聞 - 04、大型建築倒壊 訴訟の動き
~多くが旧基準「既存不適格」~ 2016年5月14日付 産経新聞 - 05、自治体「復興」手探り
~熊本地震「未知の仕事」山積み~ 2016年5月15日付 読売新聞 - 06、地震被害想定50m単位
~杉並区、首都直下に備え都より細かく~ 2016年5月12日付 日本経済新聞 - 07、簡易宿泊所、進む転居
~川崎11人死亡火災 違法状態施設なお~ 2016年5月16日付 日本経済新聞(夕刊) - 08、活断層の脅威 放置
~熊本県市町村 庁舎使えず生活支援滞る~ 2016年5月21日付 日本経済新聞 - 09、阿蘇大橋再建に数年
~国土交通省代行事業、別ルート検討へ~ 2016年5月19日付 日本経済新聞(夕刊) - 10、エクアドルなお2.9万人避難
~M7.9地震「70年で最悪の悲劇」~ 2016年5月17日付 日本経済新聞 - 11、罹災証明なく先進めず
~熊本地震1か月、暮らし再建に支障~ 2016年5月15日付 日本経済新聞 - 12、避難所解消メド立たず
~熊本地震1か月 住宅確保など課題 首長アンケート~ 2016年5月15日付 読売新聞 - 13、罹災証明 欲しくても
~熊本県益城町 人手不足 滞る発行~ 2016年5月01日付 朝日新聞 - 14、熊本地震 補正7,780億円
~政府閣議決定 予算審議入り~ 2016年5月14日付 日本経済新聞 - 15、招いた移住者 被災で動揺
~熊本地震、益城町など転出懸念~ 2016年5月04.日付 日本経済新聞 - 16、「空き巣」防げ 消防団も巡回
~熊本地震後、被害40件近く~ 2016年5月06日付 日本経済新聞 - 17、家の応急修理 申請進まず
~熊本地震 罹災証明の発行遅れ~ 2016年5月22日付 日本経済新聞 - 18、「次」への警戒解けず
~断層に割れ残り 動きの予測困難、東北大、名大等~ 2016年5月23日付
日本経済新聞 - 19、口永良部島 帰島は8割
~爆発的噴火から1年 鹿児島県~ 2016年5月30日付 日本経済新聞(夕刊) - 20、業者が談合認める
~東日本大震災復旧で仙台地裁初公判~ 2016年5月25日付 日本経済新聞(夕刊) - 21、完売マンションの建築確認取り消し
~避難施設不備 建築主が都を提訴~ 2016年5月29日付 日本経済新聞 - 22、熊本地震は直下型
~首都圏、リスク意識 行政へ相談・グッズ完売~ 2016年5月30日付 日本経済新聞 - 23、生活保護 高齢世帯50%超
~厚生労働省 単身は9割~ 2016年6月01日付 日本経済新聞(夕刊) - 24、宮城沿岸 急速に高齢化
~女川37%、気仙沼35% 移住促進が必要~ 2016年6月04日付 日本経済新聞 - 25、防災リーダー 大学が育てる
~岐阜大、愛媛大、弘前大、高知大等~ 2016年6月01日付 日本経済新聞 - 26、高齢者ケア 機能せず
~福祉避難所受け入れわずか~ 2016年5月21日付 日本経済新聞 - 27、熊本城の天守閣 3年後までに再建へ
~鉄筋化、国が積極支援~ 2016年6月10日付 日本経済新聞 - 28、震災5年 宮城の高校に専門学科
~県立多賀城高校、僕ら未来の防災リーダー~ 2016年5月13日付
日本経済新聞(夕刊) - 29、仮設住宅入居始まる
~熊本地震 発生から52日~ 2016年6月06日付 日本経済新聞 - 30、仮設商店街 移転し再開
~宮城県石巻市 本格復興にあと数年~ 2016年6月05日付 日本経済新聞
【参考文献】
- 1、 2016年5月12日付 産経新聞
- 2、 2016年5月14日付 産経新聞
- 3、 2016年5月15日付 読売新聞
- 4、 2016年5月 UGMニュース
- 5、 2016年5月 UGMニュース
- 6、 2016年5月 UGMニュース
- 7、 2016年5月12日付 日本経済新聞
- 8、 2016年5月20日付 毎日新聞(社説)
- 9、 2016年5月20日付 日本経済新聞
- 10、 2016年5月22日付 日本経済新聞
- 11、 2016年5月19日付 日本経済新聞(夕刊)
- 12、 2016年5月14日付 日本経済新聞
- 13、 2016年5月03日付 朝日新聞
- 14、 2016年5月03日付 日本経済新聞
- 15、 2016年5月03日付 日本経済新聞
- 16、 2016年4月29日付 朝日新聞
- 17、 2016年5月01日付 朝日新聞
- 18、 2016年5月01日付 日本経済新聞
- 19、 2016年5月01日付 日本経済新聞
- 20、 2016年5月15日付 日本経済新聞
- 21、 2016年5月13日付 日本経済新聞(夕刊)
- 22、 2016年4月12日付 日本経済新聞(夕刊)
- 23、 2016年4月12日付 日本経済新聞(夕刊)
- 24、 2016年5月07日付 日本経済新聞
- 25、 2016年5月29日付 日本経済新聞
- 26、 2016年5月21日付 日本経済新聞
- 27、 2016年5月24日付 日本経済新聞
- 28、 2016年5月27日付 日本経済新聞
- 29、 2016年5月27日付 日本経済新聞
- 30、 2016年5月26日付 日本経済新聞(夕刊)
- 31、 2016年5月31日付 日本経済新聞(夕刊)
- 32、 2016年5月31日付 日本経済新聞(夕刊)
- 33、 2016年5月31日付 日本経済新聞(夕刊)
- 34、 2016年5月30日付 日本経済新聞
- 35、 2016年5月30日付 日本経済新聞
- 36、 2016年6月06日付 日本経済新聞
- 37、 2016年6月10日付 日本経済新聞
- 38、 2016年6月14日付 日本経済新聞
- 39、 2016年6月11日付 日本経済新聞