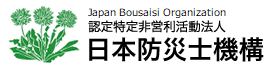防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
防災評論(第107号)
山口明の防災評論(第107号)【2019年6月号】
山口明氏による最新の防災動向の解説です。
〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。
1、防災情報5段階統一<レベル4で全員避難>
〈解説〉
2019年5月29日から、かねてよりの懸案であった防災情報を整理して5段階の警戒レベルに対応させて統一的に発表する仕組みの運用が開始された。これまで水害、土砂災害が切迫した場合でも気象台は大雨警報、河川側は氾濫警戒情報、土木側は土砂災害警戒情報として、自治体(市町村)は避難勧告といった風に様々な用語で危険情報が出されるため、受け止る住民は各々の関連性や危険度がどの程度なのか分かりにくいという指摘はあった。2018年7月の西日本豪雨ではこの弱点が露わになり、的確な住民避難に結びつかず多くの犠牲者を出した。
今回の運用開始はこの反省等をふまえ2019年3月に出た中央防災会議の報告書に基づく措置で、レベル1からレベル5にかけて切迫度・危険度は高まる。市町村が発令する「避難準備・高齢者等避難開始」はこれまでも様々な誤解やトラブルがあったが、レベル3に分類された。勿論この段階で高齢者や体の不自由な人は避難をはじめなければならないことは従来と同じである。
また、「避難勧告」と「避難指示(緊急)」は共にレベル4とされた。理論的にはより切迫度が高くすぐにでも避難しなければならないとされる「避難指示(緊急)」は「避難勧告」より重いとされるが、これまで両者の違いや運用実施の差は余り感じられず、勧告が出ても次の指示を待てばよいと考え、逃げ遅れる人がいたり混乱した。そこで勧告と指示の違いによらず両者を同じレベル4に統一して誤解をなくすよう努める。
5分類の詳細は別表のとおりであるが、今後はこのレベル区分の普及が課題である。防災士は防災に関する重要な制度改革としてこの新分類について理解を深めるとともに、一般住民に対し啓発してゆく役割があるといえるだろう。また学校教育においてはこの学習を必須のものとして国民に早期の浸透を図ってゆくこと、そのために教員に防災士の資格を取ってもらうことも非常に重要である。
<関連図>

出典 内閣府大臣官房政府広報室 暮らしに役立つ情報より引用
2、JRが海底地震観測網導入<巨大地震早期検知>
〈解説〉
JR各社は従来「新幹線早期地震検知システム」を運用して地震発生時の早期減速、停止を図ってきた。このシステムは陸の地震計と気象庁の緊急速報を組み合わせたもので、初期微動(P波)を検知し、地震規模や震央を算出して主要動(S波)が到達する前に緊急ブレーキを作動させるものである。2004年の新潟県中越地震の際も浦佐駅付近走行中の上越新幹線がこのシステム作動で緊急停止し、車両は脱線したが横転は免れ、乗客乗員に死者もなく全員生還できた。
しかしJRはこの地震で新幹線車両が脱線したことを重く見、その後もいかに早く列車を止めるかに注力してきたが、JR東日本は2017年11月から、またJR東海と西日本は2019年4月から新たに海底地震観測網の活用をはじめている。これによって停車までの時間を、南海トラフ地震の場合で最大15秒、日本海溝型地震では30秒短縮できる見通しだ。15秒の短縮といっても馬鹿にはできない。東海道新幹線の最高速度は285km/h(2019年5月現在)、だから、最高速度の場合15秒間で1km以上走ることとなる。地震を感知して非常ブレーキを作動させることで、この距離を大幅に短縮することが可能となる。
さらに検知だけでなく、ブレーキシステムの改良も重要である。JR東海が2020年7月に営業運転を始めるとしている最新新幹線車両「N700S」では停止までの距離を2800Mと、従来から1割近く縮めることができる。
地震調査委員会等における地震発生事前予測(評価)も空振りばかりが続く日本の地震学会。いつごろ地震が到来するかはっきりとしない。瞬時は分析に頼るのではなく、地震発生後の適切な行動がより重要であることは個人でも鉄道事業者でも変わりない。
3、防災訓練のあり方<正常化偏見とその打開>
〈解説〉
どこの自治体でもそうであるが、防災訓練の一般的な姿は、住民による消火器の放出訓練にはじまって、地震体験車(起震車)や消防ハシゴ自動車などをグランドに集め、さらには地元消防団が消防技法を披露(消防自動車や小型消防ポンプなどからいかに美しく規律正しく放出するかを競う訓練)をするなどが普通の光景となっている。“楽しんで防災訓練に参加する”という流れの中で年々娯楽性が強まっているように見える防災訓練だが、その内容に正常化偏見が潜んでいるように感じられる。
一般に訓練は学校や公園のグランドなどを利用して行われることが多いが、平常時ならともかく災害時にはそれらの状態は今見ている姿とは全く様相を異にするという点がまず第一に挙げられるが、避難所として活用されているならまだしもそれら公園等にたどりつく道路等が災害で閉塞されている場合はまず道路啓開を先決問題として対応しなければならないのだ。道路交通インフラが通常との前提で防災訓練をすることは阪神・淡路大震災で見られたようにまさに正常化偏見のワナに陥っているといわざるを得ない。
消防装備や技法がいかに立派でも道路啓開が成らないと使いものにならない。最近でも2018年9月の台風21号では列島各地で1600本以上もの電柱や樹木が倒れ、復旧と消防・警察活動に大きな遅れと支障をもたらした。消防や警察にも一部重機を持つ部隊(ハイパー隊)が創設されているがまだ浸透していないし、それらも使いこなす要員も不足している。そこで民間活動力、つまり、建設会社等の持つ建機も合わせて出動訓練し、道路啓開がいかに重要かを示すことも有益ではないだろうか。
もちろん共助意識の高まりにより各自治体と地元建設会社が有事の際の協定の中で、建機の出動を取り決めていることが多くなったが、一般にはあくまで協定文章の中の世界に止まり、消防などとの合同訓練まで実施している自治体は少ないと思われる。行政と建設会社等が一体となって道路啓開などのメニューを含む訓練が日常的に行われるようになると建設業界の社会貢献の評価も高まり、ひいては建設業界や建設機器レンタル業界の中からも防災士を取得する人が増えることも期待される。
<関連図>

出典 国土交通省 道路啓開計画より引用
4、堰堤一辺側からの脱却<進化する砂防>
〈解説〉
2018年は西日本豪雨をはじめとして広範囲に豪雨が襲い、消防庁が集計をはじめた1982年以来最も多くの3450件もの土砂災害が発生した。〈関連図〉のとおり、平年とこれまでの各年の平均値とすると、その3~4倍の土砂災害があった異例な年であった。しかし、今後も地球温暖化の進捗など気象変化の激化によりますます豪雨による土砂災害が増えてゆくと思われる。
これに対し国や自治体は全国に60,000基以上の砂防ダム(堰堤)を配置して土砂の下流への流出を阻止しようとしてきた。しかし近年の予想をはるかに超える集中豪雨は、これまでのタイプの砂防ダムだけでは災害発生をしっかりと抑止することが難しくなり、砂防ダムの想定を上回る雨量のため土砂と一緒に流れ込む大量の流木をくい止めることができなくなってきた。2017年九州北部豪雨における大量の流木被害に加え、2018年の西日本豪雨では砂防ダムを突破して上流から押し寄せた流木が橋に引っかかって水をせき止め、これが道路にあふれて被害を拡大させた(広島県坂町など)。もはや砂防行政は土砂のみならず流木をも巻き込んだ「砂木防行政」になりつつある。
この原因の一つとして国内の砂防ダムの大半が土砂だけを溜めることを目的とした「不ろ過型」といわれるタイプであることが挙げられる。土石流を防ぐため上流から突進する土砂だけを受け入れたダムはすぐに満杯になり、土砂より比重が軽い流木は越堰して下流に流れ落ち、民家に衝突し道路を閉塞して集落の孤立化、復旧遅れの大きな要因となる。このような事案が相次いだことから2016年4月に砂防基本計画策定指針が改訂され、新造される砂防ダムには原則流木を捕捉できる“ろ過構造”を採用することが決まった。しかし新造分のみの対策では既に建造されている「堰堤」の危険性は解消しない。そこで国土交通省は2017年から既存堰堤を活用する方策も強く打ち出している。その一つが「張り出しタイプ」といわれるタイプで従来のように堰堤の水通しに手を付けず、その上流側に直接取り付けるものだ。このほかハード対策だけでなく、二次災害防止だけを目的に絞った準ソフト対策として注目されているのが柔構造物の設置である。強靭ワイヤネットなどがその代表格で短期間で設置できるうえ、救助活動を行うための安全支援ツールとしても、また避難勧告などの早期解除にも効果があるとされる。
いまや砂防はひとり中山間地だけの問題ではなくなってきた。防災士の所在する集落近くにも砂防ダムがある所が多い。災害時にダムに近付くのは危険性だが、平常時に見学し、どのように自分の集落が守られているかやその形状に異常がみられないかなど見識を養っておくことは防災士にとって重要な実践活動といえよう。
<関連図>

出典 国土交通省 平成30年の土砂災害発生件数が確定しました~平成30年は過去最多件数を記録~より引用
5、ノートルダム寺院火災<文化財の防災対策>
〈解説〉
本年4月に発生したフランス・パリのノートルダム寺院火災。歴史的にも文化的にもさらには観光的にも有名な施設の火災でありフランスのみならず世界に衝撃が走った。防火関係者がこの事故報告に接したとき第一に不審に思ったのは石造建築物なのにどうしてこんなに激しい火災に見舞われたのかという点であったが、すぐに当該焼失部分が尖塔とその周辺の「小屋組」と呼ばれる屋根の木造部分であることが判明、同様の火災はナント大聖堂(1972年)、ニューヨーク大聖堂(1984年)でも発生しており、この種の建造物ではそれほど特異な事案ではなかった。
日本では歴史的建造物といえば殆どが純木造であるため、その防火対策は欧米より厳しく徹底している。1949年に法隆寺の金堂が燃えて壁面が燃焼したのを契機に1950年には文化財保護法が施行され、さらに焼失当日の1月26日は文化財防火デーとして消防庁、文化庁合同で訓練するほか、各地の文化財でも自治体レベルで訓練が行われる。さらに国宝や重要文化財に指定された建造物には消防法で消火器と自動火災警報装置の設置が義務付けられている。また文化庁はスプリンクラー設備やドレンチャー設備(水幕設備)導入に対して補助を出している。それでも小寺院や神社などが時折火災に合うが、殆どが放火によるものである。
フランスは先進国であるが消防制度はしっかりしていない。人口の集中するパリとマルセイユには本格的消防はあるものの軍の一部としての行政権限しか持たず、したがって日本の消防が持つような強力な予防、査察権限はない。そのことが直接今回の火災に結びついたとはいえないまでも、事故発生から2カ月以上経っても未だにはっきりした出火原因の究明がなされてないのは遺憾である。再建にばかり目がゆくフランス政府やノートルダム寺院であるが、他に多くの文化遺産を抱える同国だけにしっかりとした文化財防火の事前予防対策を打ち出してほしい。
[防災短信]
以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。
- 01、乱気流、温暖化で変化~海洋研究開発機構 発生頻度を予測解析~
2019年3月31日付 日本経済新聞 - 02、2018年災害損失世界25兆円~米保険会社、西日本豪雨、台風21号など列挙~
2019年2月15日付 日本経済新聞(夕) - 03、富士山大規模噴火降灰 神奈川10㎝、都心1㎝~中央防災会議検証結果~
2019年3月23日付 日本経済新聞 - 04、自然災害や温暖化・気候変動、事業リスクに~米電力大手 PGE破産を申請 加州の山火事で~
2019年3月19日付 日本経済新聞 - 05、水害保険 首都圏上げも~荒川、利根川大規模水害で保険金2兆円~
2019年3月22日付 日本経済新聞 - 06、屋形船に防火安全指導~東京消防庁 過去10年間に4件火災発生~
2019年3月29日付 日本経済新聞(夕) - 07、海の「救急隊」創設~海上保安庁 応急処置拡充~
2019年4月3日付 日本経済新聞 - 08、火山警戒地域市町村、避難計画策定半数割る~内閣府 2014改正活火山法十分浸透せず~
2019年4月5日付 日本経済新聞 - 09、地方道4500km 国が復旧代行~国土交通省 災害に備え事前指定 迅速復旧へ~
2019年4月5日付 日本経済新聞 - 10、南海トラフ政府指針「警戒避難1週間」に困惑~自治体、企業、住民対応の難しさ語る~
2019年3月20日付 日本経済新聞 - 11、2019年度都道府県予算「重点」は災害対策トップ~日経調査 広島10.6%、岡山8.5%増~
2019年4月29日付 日本経済新聞 - 12、「復興・防災庁」創設盛る~公明党 参院選公的
~2019年4月18日付 日本経済新聞(夕刊) - 13、震災伝承施設192件登録~国土交通省東北北地整他「震災伝承ネットワーク協議会~
2019年3月29日付 日本経済新聞 - 14、地震・警報時の緊急会見に手話通訳~気象庁 国内5弱以上の地震策に~
2019年3月26日付 日本経済新聞 - 15、27道府県で調整組織~行政、社協、NPO 大災害に広域連携~
2019年3月27日付 日本経済新聞 - 16、原発テロ対策遅れで停止~原子力規制委 川内原発1号機、来年3月以降停止~
2019年4月24日付 日本経済新聞 - 17、河川氾濫 ネットで確認 国土交通省3700カ所にカメラ設置へ~
2019年4月9日付 日本経済新聞 - 18、桜島噴火 マグマ急上昇~東北大観測 過去3回の過程を解明~
2019年4月9日付 日本経済新聞 - 19、2019年度の異常気象 気流変化が原因か~英オックスフォード大調査、ジェット気流に異変~
2019年5月5日付 日本経済新聞