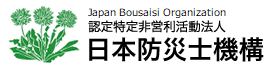防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
防災評論(第119号)
山口明の防災評論(第119号)【2020年7月号】
山口明氏による最新の防災動向の解説です。
〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。
1、感染症対策と自衛隊の活用<必要な体制づくり>
〈解説〉
今の日本の危機対応の仕組み(公助)では、地震、風水害などで大規模災害が発生したとき、又は発生するおそれがあるときは警察、消防、自衛隊などいわゆる公助実力部隊が連携して事態に当たることが当然視されている。しかしこの連携の仕組みも昔からあったわけではない。伊勢湾台風の反省から創設された災害対策基本法、そして阪神大震災での貴重な教訓などから、法制度や実践、実行体制が格段に整備され、今日ではこれら関係機関が協働するのはごく当たり前のように思われている。
しかし現在なお猛威をふるっている新型コロナウイルス感染症対策については「病気は厚生労働省」という従来の行政の仕切りを撤廃するだけの発想力、想像力が政府には欠けており、それが初動のミスにつながった。2月に起きたダイヤモンドプリンセス事件は、今日のコロナ禍の端緒ともいうべき防疫対策であったが、解決までに長期間を擁し、その間に船内感染が拡大、人権侵害ではないかとの不満や批判が国内外から殺到し、日本の名誉と評価を落としめる事となった。ようやく全員下船(全員検疫終了)ができたのは3月下旬を待たなければならなかった。
直面した厚生労働省ではあれだけの特殊で大規模な危機対応を一省庁である厚生労働省で仕切るのは無理と述懐する。
もっとも横浜港での防疫活動に厚生労働省の医官や検疫官など医療・公衆衛生関係者だけが従事したわけではない。防衛省は2月~3月にわたり延べ2,700人の自衛官を派遣した。
直前の武漢からのチャータ機による帰国邦人支援のため既に災害派遣されていたところに、当該クルーズ船の任務も急遽追加された。しかし神奈川県知事からの災害要請もない中での支援(自主派遣)であった。自衛隊員は全員防護服で作業するなど厚生労働省より高いレベルの防護体制を敷いて対処し結果的に自衛官の感染はゼロであった。一方、DMAT(災害派遣医療チーム)も活動したが、法令上の根拠も曖昧なまま県庁内の対策本部でトリアージ(患者の振り分け)など医療機関手配に大活躍した。だが、その後「臨時検疫官」として船内に送り込まれると感染者が発生、本来ボランティアとして交代制を前提にしたDMATは機能不全に陥った。ある隊員はクルーズ船内にまで押し込まれた今回の事案について今後DMATが不完全な知見現場に見境なく投入される危惧を訴える。
感染症対策は一人厚生労働省だけの仕事では及ばないことは政府・自治体関係者はこの事件を契機にに思い知らされた。
今後内閣官房を中心に今回のような任務とどう体系づけて法制化してゆくか真剣な検討がぜひとも必要である。
<関連図>
ダイヤモンドプリンセス号

出典:https://www.photo-ac.com/main/search?q=%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%97%E3%83%AA%E3%83%B3%E3%82%BB%E3%82%B9&sl=ja&qt=&qid=&creator=&ngcreator=&nq=&srt=dlrank&orientation=all&sizesec=all&mdlrlrsec=all
2、在宅避難の目安<安全な自宅といえるのは?>
〈解説〉
今年も梅雨前線の長期化・大規模化もあり、6月~7月にかけ熊本県をはじめとする全国各地で大規模災害が発生、多くの犠牲者(令和2年7月豪雨による被害での死者、行方不明者合計86名。8月4日時点)を出したが、コロナウイルス蔓延というかってない異常事態の中多くの困難が指摘された。コロナ対策として注目されているのが“在宅避難”である。災害時の避難といえばこれまで一般的には自治体が指定する体育館・公民館などの「避難所」がコロナの“3密”状況になる恐れがあり、これを避けるためにこれまで以上に在宅での避難が重視されるようになっている。しかしもともと在宅が危険だからということで避難所開設が制度化されているので、安易に在宅を勧めることは逆に安全を妨げることにもつながりかねない。日頃から万一のときに備え在宅避難が可能かどうか一人一人や家族が常にチェックし心構えを持っておくことが求められる。
専門家によると在宅避難できる安全な自宅といえる為には次の条件が備わっていることが必要であるとされる。
(1)日常生活に必要不可欠な備蓄品の確保(医療用品や薬を含む)又はそのサービスをある程度容易に供給されること
(2)被災家屋が災害発生後迅速に修理、復旧できる状況にあること。
(3)近隣の住民同士の助け合いがスムースに運ぶかどうか地域の連携が保たれていること。
(4)いざというときに自宅建物から応急仮設住宅等に移動できる環境にあること。
そして何より大切なことは当該家屋自体が安全であること(通常時の安全よりやや落ちるが人命や健康にただちに脅威にならない程度の安全確保)である。風水害に備えハザードマップで浸水想定区域や土砂災害警戒区域に住宅が建っていないことを確認しておく必要があるがより細かい安全確認手段として災害時の対応を専門家の助言を受けつつ、地域コミュニティでつくる「地区防災計画」の活用が最近クローズアップされてきている。地域での防災士も多く参加するこの地区防災計画づくりを通じ、より一層地域の絆を深め実効ある在宅避難対策にすべきであろう。
<関連図>
出典:内閣府防災情報のページ
http://www.bousai.go.jp/fusuigai/typhoonworking/pdf/dai3kai/siryo2.pdf
3、「稲むらの火」その後<震災ガレキを活用した堤防工事>
〈解説〉
1854年太平洋トラフの激震により安政南海地震が発生、その時広村(現広川町)の庄屋であった濱口梧陵が村人を救うため一刻の猶予もならないとして燃やしたとされる稲むらの火は防災関係者にとって余りにも有名な逸話である。この物語の詳細な点まで史実かどうかは議論のあるところであるが、少なくとも濱口が防災事案、とりわけ地震・津波対策に精魂込めていたことは事実であり、その証拠として現地には濱口が率先して築いた広村堤防が今も残されている。今年は濱口が生まれてから200年に当たるが、この堤防に関し新資料が広川町内の民間住宅から発見された。この古文書の中で広村堤防(国史跡)について「堤防の敷地は、安政南海地震で破壊された民家などの廃棄物(震災ガレキ)を兼ねており、それを堤防の盛土として活用した」という表現があるのが確認された。
この古文書では「稲むらの火」のクライマックスともいえる濱口が自宅屋敷敷地内にあった稲むらを燃やして非難を促したというエピソードは書かれていなかったが、築堤については多く記述がある。即ち
①先ほど述べた堤防用盛土として震災ガレキが利用されたこと。これは近年東日本大震災で見られたような手法の先駆けともいえる。
②濱口築堤の狙いとして単なる津波予防策だけではなく、震災により多くの村人が家財や仕事を失い、途方に暮れていたところ、その復興対策として私財を投げうって濱口がこの事業を起こしたこと。つまり濱口は地域の復興にまで心を寄せていたことが証明されている。
広村堤防は安政南海のあと約90年後の昭和南海地震で、広川町に約4~5メートルの津波が襲来したが、これにより多くの住宅等が被害を免れたとしてその土木工事としての堅牢性も高く評価される。なお当該古文書は和歌山県立文書館のホームページで公開されている。(タイトル「渋谷家文書」)防災士もぜひ一読するようお勧めしたい。
<「稲むらの火」とは>
内閣府防災情報のページには次のように紹介されている。
(以下引用)
「稲むらの火」の原作は、ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)が明治30(1897)年に発表した短編小説「A Living God」(生き神様)です。明治29年6月に発生した明治三陸地震による津波で数多くの命が失われたというニュースを知ったハーンは、伝え聞いていた安政南海地震の際の梧陵の偉業をヒントに、この小説を書き上げたと言われています。広村の隣町の湯浅町出身の小学校教員であった中井常蔵はこの小説に深く感動し、それを子どもにも伝えたいと考え、昭和9(1934)年文部省の教材公募にハーンの小説をもとに執筆した「稲むらの火」を応募し、採択されました。この作品は昭和12年から10年間にわたって小学5年生用の国語読本に掲載されました。また、平成23年度から使われている小学5年生用国語教科書に濱口梧陵の伝記が掲載されています。
(引用終わり)
詳しくは内閣府防災情報のページ:特集津波防災の日
http://www.bousai.go.jp/kohou/kouhoubousai/h26/76/special_01.html
[防災短信]
以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。
- 01、原発 巨大噴火への対応~原子力規制委、停止基準見送りへ~
2020年4月27日 日本経済新聞 - 02、日本は複合災害に備えよ~自然災害、コロナウイルスそして熱中症 地域防災計画なども参考に~
2020年5月26日 日本経済新聞 - 03、京アニ火災 義援金33億円異例の税優遇へ~国税庁 災害義援金の制度適用~
2020年5月28日 日本経済新聞 - 04、特別警報「解除」表現見直し~気象庁 台風19号受け「警報に切り替え」に~
2020年5月29日 日本経済新聞 - 05、改正都市再生法が成立 国土交通省 防災推進と快適都市創立へ~
2020年6月4日 建設産業新聞 - 06、災害に強い官公庁施設づくり~国土交通省 6月にガイドライン策定~
2020年6月4日 建設産業新聞 - 07、海面上昇加味した設計を~国土交通省、農林水産省、海岸施設の温暖化対策の骨子案まとめる~
2020年6月4日 建設産業新聞 - 08、「在宅避難」自治体呼びかけ~各自治体 大雨の時期 避難所に感染リスク~
2020年6月5日 日本経済新聞(夕刊) - 09、大川小遺族に殺害予告容疑~宮城県警 高知県の教員逮捕~
2020年6月5日 朝日新聞 - 10、コロナ「複合災害」に備え~避難所、ザコ寝で感染の恐れ 段ボールベッドや仕切り~
2020年6月6日 日本経済新聞 - 11、大雨特別警報の基準一部変更へ~気象庁 地中の雨量で土砂災害判断~
2020年6月7日 朝日新聞 - 12、豪雨復旧で贈収賄疑い~福岡県警、朝倉市係長など逮捕 復旧工事に謝礼100万円~
2020年6月14日 日本経済新聞 - 13、震災遺構VRで体験~気仙沼市伝承館をネットで無料公開~
2020年6月17日 日本経済新聞 - 14、災害拠点病院向けBCP策定指針~東京都 大規模災害発生に向け指針改正~
2020年6月17日 建設産業新聞 - 15、水害時の都営住宅協定締結~東京/都と足立区 空き家活用~
2020年6月17日 建設産業新聞 - 16、大震災被災県に財政特例措置要求~復興庁 コロナで復興遅れ懸念~
2020年6月17日 建設産業新聞 - 17、首都圏水害被害2.6倍に~2014~18年平均459億円 国土交通省~
2020年6月17日 日本経済新聞 - 18、三浦半島で謎の異臭~立命館大「南海トラフ地震の予兆か?」~
2020年6月19日 週刊ポスト - 19、避難所運営3つの壁~各自治体「場所の確保」「物資の不足」「厳しい暑さ」~
2020年6月20日 日本経済新聞 - 20、大規模水害に備え、避難施設を増強へ~国土交通省自治体への財政支援へ~
2020年6月23日 日本経済新聞 - 21、コロナ影響で温暖化ガス減~JAXA 衛星データを分析~
2020年6月26日 日本経済新聞(夕刊) - 22、山小屋救え 支援の輪~登山愛好家によるクラウドファンディング コロナ休業で登山道保全に不安~」~
2020年6月26日 読売新聞(夕刊)