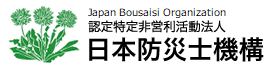防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
防災評論(第137号)
山口明の防災評論(第137号)【2022年1月号】
山口明氏による最新の防災動向の解説です。
〈解説〉とあるのは山口氏執筆による解説文、〈関連記事〉はそのテーマに関連する新聞記事の紹介です(出典は文末に記載)。防災士の皆様が、引用、活用される場合はご留意の上、出典を明示するようお願いします。
1、軽石噴火と海底火山
〈解説〉
2021年8月から1月にかけて海底の自然災害による予期せぬ被害が相次いでいる。8月中旬に小笠原諸島の海底火山が大噴火を起こし、それによって噴出した大量の軽石が広範囲に流出、小笠原から1,000キロ以上も離れ、普段全く関連性がない沖縄や奄美など南西諸島に流れ着き、当地の漁業(軽石と言う名の通り水中に浮遊する異物であるところから漁船など船舶エンジンに目詰まりを生じさせ、出漁できなくなる)への打撃やまた沿岸生物の軽石呑み込みによる障害や、海岸線に漂着した軽石の層が繰り返し放映されることなどから観光への悪影響を生じさせた。
その後、軽石群は海流に乗って一部は再び東方海域に転じ、伊豆諸島にも出現が確認された。この海底火山噴火は陸上での噴火も含めてなお明治以降の噴火としては最大規模であったと推測される。学者によると陸上火山でも軽石噴火は江戸時代には観測されており、有名な富士山宝永噴火(1707年)においては100キロ以上離れた東京(江戸)でも軽石が降り注いで、街中が降雪に遭ったように白灰で染まったという。
年が明けると日本の遥か南東約8,000キロに位置するトンガ諸島(王国)付近の海底火山が大爆発を起こし、同諸島に大量の降灰をもたらし、通信・交通の途絶状態を引き起こしたに止まらず、大気を大揺動させる「空振」現象も伴って津波が発生、気象庁の目測誤りもあり、準備が不十分なうちに日本列島にも津波が到達、最高変異1メートルを超す津波高を記録した地域も数か所に及び、その波高に達しなかった場所でも漁船など小型船舶の倒壊や転覆などの被害が相次ぎ、予想を超す災害規模となった。小笠原沖の海底火山爆発は噴煙17,000メートル高に達し、一方トンガ沖では約40万トンの二酸化硫黄(SO2)
が放出され、噴煙の高さは成層圏(16キロメートル)以上に達したと見られている。
これら二つの火山災害から防災士など地域安全に係わる関係者に対しては、今後に活かすべき教訓として次のことが指摘できる。第一には既存の防災領域を超えた観察と対応が必要ということである。日本の場合領海内の火山は実効支配の及ばない北方領土を含み111あるが、そのうち富士火山帯に属する海底火山は13もある。
しかし、これまでその挙動については海上関係機関を除きあまり関心が払われてこなかった。次に火山活動と津波、軽石等二次災害との関係により注意を払わなければならないということである。これまで津波といえば地震発生時、噴火といえば火山灰や噴石、溶岩といった思考パターンが余りにも支配的であった。専門家のみならず、一般の防災関係者でも広い視野での洞察力が求められる。
2、長周期地震動階のより周知を
〈解説〉
2021年10月7日の夜の首都圏での地震では再び長周期地震動が観測された。長周期地震動の特徴はいうまでもなく揺れの周期が長いため遠方までその揺動が伝わりやすく、かつガタガタと揺れる短周期波動に比べ揺れる時間が長い傾向がある。都市の高層化、マンション化によってかつての大地震では意識されなかった長周期地震動の影響が大きくクローズアップされている。
かつて2004年の新潟県中越地震ではじめて注目された長周期地震動の被害。震源から約200キロメートル離れた港区六本木ヒルズでも大きな揺れを感じた。また2011年の東日本大震災では新宿高層ビル群のキャスター付きの家具が激しく動いたほか、大阪臨海部の高層ビルにも被害が及ぶなど、その影響は列島の広範囲に及んだ。
東日本大震災での長周期地震動被害を受け、気象庁は2013年から新たに長周期地震動階級の試験運用を開始、さらに2019年からは当該階級の本格運用を始めている。この階級によると東日本大震災での階級は東京都心で4、2021年10月の首都圏地震ではやはり都心で2であった。(表参照)
問題はせっかく運用しているこの階級について余り知られていないことにあろう。長周期、短周期の別なく日本独特の地震の強さを示す「震度」については長い観測の歴史を経てすっかり国民の間に定着している。阪神淡路大震災を契機として国、地方協働で震度計が全国に張りめぐらされ、テレビや携帯電話でも地震が発生するとほぼ時間をおかないで揺れの大きかった地域の震度が発表され、防災士はもとより一般住民、また関係行政機関や実働機関においてはそれを目安として応急活動を展開することができるようになった。
しかし場合によっては短周期よりも甚大な被害を及ぼすおそれのある長周期の挙動にももっと周知と注意を払うべきであろう。震度だけに頼っていては長周期の本当の影響は分からない。大地震に襲われたとき、ただちに揺れや被害を感じなかった地域においても長周期の情報はどうなのか、防災士として地元の気象台とのチャンネルを活かした情報収集が図れるよう、日ごろから気象機関との連携を深めておくことが重要であろう。

出典:気象庁ホームページ
3、富士山レーダーの設置から60年
〈解説〉
「台風」という用語は明治末期に中央気象台(今の気象庁)の予報課長が英語のタイフーン(tyhoon)の訳として発音のよく似た「颱(たい)」(現在は略字となって「台」)を当てて考案したのが由来といわれている。台風は台湾をよく襲う災害だからそういう名前になったとか、英語は日本語の翻訳という説は誤りで、英語(タイフーン)は元々中国語からその音を取ったものとされる。つまり元をたどれば台風の語源は中国にあり、中国も日本に劣らず台風被害が多かったことを示している。
枕草子の時代には「野分(のわけ)」という優雅な名称で呼ばれていた台風だが、その被害は甚大であった。1828年に九州と四国で死者2万人超を出した「シーボルト台風」(シーボルトの隠し持っていた日本地図<禁制品>が発覚したことから明治になって命名)、遡れば1281年に襲来した元寇軍14万人の大半が海のモクズと消えた「弘安の神風」などが歴史上有名である。戦前から昭和中期(「敗戦期」)に至るまでの近代日本においては台風は災害として最も大きな被害を度々もたらしており、その犠牲者(死者、行方不明者)は1,000人を超えるということはザラであった。だが1960年を境にして、その後の日本における台風被害は激減し、他の諸国が台風、ハリケーン、サイクロンなど大型低気圧の襲来により大被害を未だ出している場合がある中で、特筆すべき存在となっている。(表参照)
これは1961年、今から60年前に多額の費用と労力をつぎ込んで開設された富士山頂レーダーの設置をはじめとする気象観測技術・体制の飛躍的な進歩、ダム建設、防潮堤・河川堤防の整備などの治水公共事業の思い切った増強など各般の施策総動員して台風被害に立ち向かった行政の対策の成果によるところが大きい。加えて伊勢湾台風を契機として防災法制度の抜本的整備が実現し、今日防災士はじめ関係者がよりどころとする「災害対策基本法」が成立・施行されたことにより体系的な防災対策の推進が始まったことも大きい。
こうしてわが国の防災対策は戦後の混乱期である第一期を脱し、安定の第二期を迎えることになるのだが、この間の成果が余りに大きかったことから国民の間に逆に行政依存度が増し、「防災は国や地方(公助)がやるもの」との意識がまん延し、やがてその考え方の大転換を迫る阪神淡路大震災(1995年)を迎えることとなる。

[防災短信]
以下は、最近の報道記事の見出し紹介です。
- 1、ラニーニャで寒い冬に~気象庁 西日本では低温の公算大、後半は気温の急変も~2021.10.27 日経夕刊
- 2、熱海土石流で強制捜査~静岡県警 盛土関係先を業務過失致死容疑など~2021.10.28 日経
- 3、崩落現場、掘削の先端~岐阜県警 リニア工事死傷事故 業務過失致死傷疑いも~2021.10.28 日経
- 4、乗務員判断でドア開けず~京王線事故 停車位置ずれ転落回避~2021.11.2 日経
- 5、避難情報発令「難しい」66%~内閣府 自治体を調査 空振りを懸念~2021.11.4 日経
- 6、熱海土石流で百条委員会~熱海市議会 原因や責任を究明~2021.11.5 日経
- 7、注意喚起方針に改善余地~富士急行第三者委員会中韓報告 ハイランドコースター事故で見直し求める~2021.11.5 日経
- 8、「津波防災の日」各地で訓練~鹿児島県、和歌山県等 南海トラフ地震に備え~2021.11.5 日経夕刊
- 9、軽石南関東まで影響恐れ~海洋研究開発機構 沖縄漁業、観光に打撃 本州の漁協警戒強める~2021.11.6 日経
- 10、火災保険実質値上げへ~損害保険各会社、割安な10年契約廃止~2021.11.10 日経
- 11、気候変動「どう教えれば・・・」~栃木県、東京都、悩む教員ノウハウ足りず 専門人材、授業で指導も~2021.11.11 日経
- 12、「地球規模の緊急事態」7割~国連開発計画(UNDP) 18歳未満の認識度調査 18か国対象 日本は81%~2021.11.11 日経
- 13、不明者公表 48時間以内~静岡県 災害時に 熱海土石流を教訓~2021.11.13 日経夕刊
- 14、「気温上昇1.5度以内追求」COP26閉幕 石炭火力は段階削減 新興国の反発強く~2021.11.15 日経
- 15、災害報道のあり方討議~日本新聞協会大会「正確な報道と公正な論評」決議~2021.11.16 日経
- 16、老いる水道管 進まぬ対策~厚生労働省 耐用年数ごえ全国13万km 人口減がもたらす更新の壁 2021.11.21 日経
- 17、修繕必要な橋 全国20000箇所~国土交通省建設後50年経過橋梁は全体の32%2021.11.21 日経
- 18、「復興防災公園」隈研吾氏が設計~倉敷市真備町地区、西日本豪雨で被災、2023完成予定~2021.11.22 日経夕刊
- 19、帰宅困難者 足りぬ収容力~日経調査「想定の5割未満」が半数 三大都市圏民間受け入れ課題も~2021.11.23 日経
- 20、滞留把握仕組み整わず~日経調査 把握システムなし29市区中17市区 混乱時対応後手の恐れ~2021.11.23 日経
- 21、公共建築物建替え、更新費に苦心 2021.11.24 日経