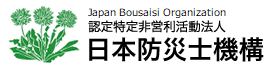防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
防災評論(第90号)
山口明の「防災・安全 ~国・地方の動き~」
防災評論家 山口 明氏の執筆による、「防災・安全 ~国・地方の動き~」を掲載致します。防災対策を中心に、防災士の皆様や防災・安全に関心を持たれている方々のために、最新の国・地方の動きをタイムリーにお知らせすることにより、防災士はじめ防災関係者の方々の自己啓発や業務遂行にお役立てて頂こうとするものです。今後の「防災・安全 ~国・地方の動き~」にご期待下さい。
山口明の防災評論
防災評論(第90号)【平成30年1月号】
【目次】 〔政治行政の動向概観〕 〔個別の動き〕
- 01、猛烈な台風 日本で増加(気象庁)
- 02、ゲリラ豪雨 鉄道影響軽く(鉄道総研)
- 03、火災警報音 屋外でも(消防庁)
- 04、進まぬ堤防整備(会計検査院)
- 05、私学の耐震化 9割届かず(文部科学省)
- 06、ドローン全天候型、政令市で導入へ(消防庁)
- 07、自治体の避難所施設 92%が耐震化完了(消防庁)
- 08、電気ストーブ火災 27人死亡(NITE)
- 09、家計赤字世帯 6割に倍増(NGO・復興庁・文部科学省)
- 10、冬山登山 高校が計画書(スポーツ庁)
- 11、熊本地震事故 新幹線 防止設備なく脱線(運輸安全委)
- 12、豪雨多発で浸水時の救助強化(消防庁)
- 13、災害時に避難者の位置をスマホで把握(内閣府・総務省)
- 14、火災警報器の設置率 全国平均81.7%(消防庁)
- 15、民法規定で解体 持ち主所在不明の空き家(大田区)
〔政治行政の動向概観〕
本年(2018年)に入り通常国会が開会したが、野党が四分五裂し、しかも特に政策対案が無い状況ではその論戦は低調なものとなろう。当面大きな災害もなく、北朝鮮の脅威も平昌オリンピックを控え動きが見られない中、平穏に推移するとみられていた防災分野で1月末から2月にかけ、立て続けに大きな災害が発生した。
1つは1月23日に噴火した草津白根山の水蒸気爆発で、1名の自衛隊員が噴石の直撃を受けて死亡した。次いで、月末の深夜には札幌の“共同住宅(アパート)”で発生した火災で、その“住宅”に居た11人もの高齢者等が亡くなる惨事となった。この種の火災はこのところ相次いで報告されており、その背後には困窮者を大量発生させる社会格差の増大と高齢化の進行があり、その意味で単に火災事故に止まらず日本の置かれた現状を映す鏡と言わざるを得ない。いつも類似火災が起きるたびに消防法規制が甘いのではないかとの議論が巻き起こるが、これには2つの大きな壁があることを指摘したい。
1つは個人の住宅に対し経済的にも社会的にも過度な設備規制はできないということである。
2つめにはこの種の“住宅”が果たして通常の住宅といえるのかどうか、消防の公助力では厳密な設定が困難という問題である。札幌市だけでも類似の“住宅”は数十にのぼるという。
特に2つめの課題について防災士も普段から危険な住宅の存在に注意し、消防と連携して情報提供に努めることが1つの解決策になるのではないだろうか。今回火災に見舞われた“住宅”でも入居者への食事の提供や簡単な介護などをしていたという証言もある。もしそうであれば、この施設は“住宅”ではなく有料老人ホームとなり、より厳しい規制がかかることになる。
火災は災害のうちでも命に係る重大な事案である。防災士の眼が地域や高齢者の安全を守る力となることが期待される。
〔個別の動き〕
1、猛烈な台風 日本で増加(気象庁)
地球温暖化が進み、平均気温が現在より約3度上昇した場合、日本の南海上に到達する猛烈な台風が増加する可能性が高いとの研究結果を、気象庁気象研究所が発表した。
研究の結果、木が引き抜かれたり、電柱が倒れたりするような最大風速59メートル以上の猛烈な台風の発生は、世界全体では減少するが、海域ごとに見ると状況は異なることが判明。熱帯域でできて日本の南数百~千キロほどの海上に到達するものは増える一方、フィリピン周辺では減少することが分かった。
現在、南海上に到達する猛烈な台風は10年に3回ほどだが、将来は10年に5回程度になる恐れがあるという。
温暖化によって台風が成長しやすい海水温となり、上昇気流が起きやすくなるのが理由とみられる。
2、ゲリラ豪雨 鉄道影響軽く(鉄道総研)
鉄道総合技術研究所は局地的に大量の雨が降る「ゲリラ豪雨」による鉄道運行への影響を軽減するシステムを開発した。レーダーによる豪雨予測に基づき、線路付近で浸水が起こりそうな地域などを分析。鉄道会社に対し、列車の適切な停止位置や乗客を誘導しやすい避難場所を示す。鉄道会社の協力を得ながら検証し、早期の実用化を目指す。
システムは埼玉大学、山口大学と開発した。ゲリラ豪雨が発生すると中小河川が急に増水したり線路周辺が冠水したりし、列車の運行に影響する恐れがある。
システムではレーダーで予測した降水量などをもとに、川の水位変化や浸水が起きそうな地域を最小1メートル単位で解析。列車が進入して立ち往生しないよう、どこで停車したらよいか、避難が必要な場合はどこに誘導すべきかなどを示す。ゲリラ豪雨の発生1時間前に、鉄道会社に提示するのが目標だ。運転の再開も円滑に進められるとみている。
鉄道会社の多くは約10キロメートルごとに設置された雨量計の数値に基づいて運転を調整している。雨量計の間隔より狭い範囲で降るゲリラ豪雨への対応が課題だった。
3、火災警報音 屋外でも(消防庁)
消防庁は、飲食店などの火災をすぐ把握するため、火災警報器の音声を屋外で鳴らす仕組みの普及を検討する。飲食店が不在でも近所の人が気づき、119番や初期消火できるようにする。
2016年12月に起きた糸魚川市の大火では、ラーメン店の店主がこんろの火を消し忘れたまま外出して出火、強風で木造住宅密集地に燃え広がった。営業時間外の飲食店は不在になりやすく、火元となるこんろなどを扱うため、消防庁は地域ぐるみで被害拡大を防ぐ仕組みが必要と判断した。
想定しているのは、店の中と外に火災警報器をそれぞれ設置し、店内で煙や熱を感知すると、無線でつないだ屋外の警報器も連動するシステム。
消防庁は、飲食店と隣接する住宅にある警報器を連動させる仕組みも検討している。糸魚川市などで行うモデル事業の一部で屋外にも警報器を設置、警報音が聞こえる範囲や風雨の影響を検証する。
4、進まぬ堤防整備(会計検査院)
会計検査院がまとめた2016年度決算の検査報告で、水害を防ぐための堤防整備が進んでいない実態を指摘した。税金の使い道に厳しい視線が向けられる中、会計管理の徹底が求められそうだ。
国土交通省の河川改修事業による堤防の整備状況の検査では、整備や橋梁の改築が進んでいない場所が全国24か所にあることが分かった。このうち秋田県の雄物川では豪雨災害時の治水機能が不十分だったため、7月の大雨の際に洪水が起き、住宅や農地に浸水被害が出た。
検査院は、土地の権利者などの同意が得られず用地取得が進まないことなどが原因としている。国交省は「緊急性の高いものから順次調整を行い、橋梁の架け替えや堤防のかさ上げを行っている」とする。v
東京電力福島第1原子力発電所事故関連では、初動対応に当たった警察官らの健康管理支援システムが活用されていなかった。事故直後に復旧作業に携わった警察官や消防、自衛隊員ら約10万人の被曝(ひばく)線量などのデータを集め、健康管理や研究に生かす目的で量子科学技術研究開発機構が整備した。
実際にデータを提供したのは警察関係者645人分。消防、自衛隊員の被曝線量は低いことが判明し、両組織からは提供されなかった。機構はデータ提供の見込みがなくなった2014年10月以降も事業を見直さず、システムの保守契約などを締結。検査院は計27契約(約1億2,919万円)を不当と認定した。
5、私学の耐震化 9割届かず(文部科学省)
文部科学省は、全国の幼稚園から高校までの私立学校で、震度6強の揺れでも倒壊の恐れが少ない建物の比率は2017年4月1日時点で、前年同期比2ポイント増の88.4%だったと発表した。別の調査で、98.8%だった公立小中学校に比べて約10ポイント低く、遅れが目立った。
耐震改修に対する支援制度で、公立小中学校に比べ高校以下の私立学校の補助率が低いのが一因となっている。
文科省は都道府県に対し、補助制度を充実し、耐震化を急ぐよう要請する方針だ。
学校別では、中高一貫の中等教育学校が98.3%で最も高い。小学校97.3%、中学校95.9%、幼稚園・認定こども園88.4%、高校87.0%だった。
6、ドローン全天候型、政令市で導入へ(消防庁)
消防庁は大雨や強風など過酷な気象条件のもとで飛行できる「全天候型ドローン(小型無人機)」を2018年度から全国10の政令市に導入する方針だ。2017年7月の九州北部豪雨では国のプロジェクトの一環で開発中のドローンが初めて災害現場に投入された。民間でも開発が進んでおり、人が近づけない危険な災害現場で、孤立地域にいるけが人などの情報の迅速な把握が期待されている。
今後の課題は画像を警察・消防などに迅速に届ける通信システムだ。
一般的にドローンが通信に使っている2.4ギガヘルツ帯の周波数は無線LANなどの干渉を受けやすく、構造物や樹木などに遮られて電波が途切れやすい。実際、九州北部豪雨の被災地で撮影した画像を災害対策本部などに送信できず、被害状況をリアルタイムでは確認できなかった。
総務省は2016年8月、ドローン用の周波数として169メガヘルツ帯を認めた。田所教授は九州北部豪雨直後にこの周波数を使ったドローンの遠隔制御に成功したと発表。障害物の影響を受けにくい特性があり「飛行状況を安定的に把握できる」という。今後は画像転送機能の向上も目指す。
7、自治体の避難所施設 92%が耐震化完了(消防庁)
消防庁は、災害時に対策本部や避難所として使う自治体の公共施設のうち、震度6強の揺れでも倒壊の恐れが少ないと確認された耐震化建物は2017年3月末時点で92.2%だったと発表した。1年前に比べて1.3ポイント増えた。施設別にみると、市役所や町村役場など「庁舎」は81.3%と低く、改修や建て替えが遅れている。
2016年4月の熊本地震では一部自治体の庁舎が損壊し、代替場所が二転三転した。庁舎は厳しい財政事情から学校などに比べて後回しになっているとみられるが、被災時の代替庁舎を決めていない自治体もあり、消防庁は早期の対応を求めている。
調査は全国18万2,337棟が対象。現在の耐震基準が導入された1981年以前の建設は8万6,006棟あり、耐震診断の未実施が8,371棟、診断後に改修していない建物が5,903棟あった。
施設別の耐震化率は、学校の校舎や体育館など文教施設が98.1%と最も高く、消防本部・消防署所の90.4%、診療施設の89.6%が続いた。
都道府県別にみると、東京の98.8%が最高で、次いで静岡と愛知が97.1%。逆に広島は81.0%と最も低かった。
8、電気ストーブ火災 27人死亡(NITE)
製品評価技術基盤機構は、電気ストーブの誤った使い方で、布団や洗濯物が燃えるなどした火災や事故が2017年3月までの5年間で434件起き、27人が死亡していたと発表した。事故を防ぐためストーブ近くに可燃物を置いたり、就寝時に使用したりしないよう呼び掛けた。石油やガスストーブを含む事故全体のうち、電気ストーブは約半数を占めた。
電気ストーブ事故の約6割で火災が発生しており、死亡事故の8割超は使用者が60代以上だった。高齢になるほど事故が起きやすい傾向がある。
2014年1月には静岡県で、就寝中の70代男性が火災で死亡。布団が電気ストーブに触れたとみられる。同年2月には徳島県で、30代女性が脱衣場を暖めようと電源を入れたまま離れ、部屋を焼く火災が発生した。
9、家計赤字世帯 6割に倍増(NGO・復興庁・文部科学省)
2011年の東日本大震災で被災し、経済的に困窮した状況にある宮城県石巻市と岩手県山田町の計約400世帯のうち、震災6年後も家計が赤字だったのは約6割で、震災前の約3割から倍増したことが、NGOの調査で分かった。
被災に伴う失職や自宅再建費の負担増などが原因。今も多くの被災者が経済的問題を抱えている実態が明らかになった。
NGOは2市町で子供の進学資金を支援。今年2~5月、支援を受けた世帯にアンケートし、396世帯から回答を得た。
震災前に借金や預貯金の切り崩しなどで家計が赤字だったと答えたのは116世帯(29.3%)。一方、震災から6年後の家計が赤字と答えたのは239世帯(60.4%)に上った。回答者のうち337世帯(85.1%)が一人親世帯だった。
赤字になった理由は「震災と病気を機に、夫が無職になり収入が激減」「震災債務に追われ、再建した店も家も売却準備をしている」などだった。経済状況の悪化を理由に、子供の学習塾や習い事を断念した世帯も約4割あった。
また、復興庁は、東日本大震災の避難者が全国で7万9,310人になったと発表した。前回調査に比べ2,556人減り、震災から6年8か月で8万人を下回った。震災直後の避難者数は推計47万人。
避難先は47都道府県の1,054市区町村。都道府県別では、福島が最多で1万8,770人、次いで宮城の1万1,084人だった。岩手は9,584人で、初めて1万人を下回った。
施設別に見ると、仮設住宅や民間賃貸住宅などで暮らす人が5万9,553人、親族・知人宅に身を寄せている人が1万9,483人、病院などが274人。
さらに、文部科学省は、東日本大震災の影響で以前の居住地とは別の地域の学校に転校した小中高校生が5月1日現在で、昨年より2,360人減の1万5,314人となったと発表した。東京電力福島第1原発事故により多数の住民が避難している福島県からが1万836人で最も多かった。
被害が大きかった岩手、宮城、福島から他の都道府県に移った児童生徒は岩手200人、宮城1,049人、福島6,948人。3県の児童生徒の受け入れ先は新潟858人、山形774人など。
10、冬山登山 高校が計画書(スポーツ庁)
栃木県那須町で2017年3月に県立大田原高山岳部などの登山講習中に起きた雪崩事故を受けて、スポーツ庁は冬山登山の事故防止策をまとめた。「冬山登山」の定義を明確化したほか、冬山で活動する高校などに計画書の事前提出を求めた。教育委員会や高等学校体育連盟(高体連)には提出された計画の安全性を審査する組織の新設を促している。
事故防止策では原則禁止としている「冬山登山」について、時期に関わらず降雪、吹雪、なだれなどが起きる可能性がある環境で実施する活動と定義した。これまで冬山状態でも「春山講習」として実施する例があったことを踏まえて定義を明確化した。
その上で冬山登山を例外的に実施する際の条件や留意点を示した。実施する高校や高体連は、ルート、装備、緊急時の対応などを具体的に記した計画書を作成する。都道府県教育委員会などは登山の専門家などを含む審査会を設置して、高校などが作った計画を吟味する。安全性に課題があるときは改善を指示する。
全国高体連の調査によると同連盟の登山専門部に加盟する高校生の数は2017年度に1万574人で10年で5割増えた。一方、経験豊かな顧問は不足するなど事故防止の課題はまだ多い。
11、熊本地震事故 新幹線 防止設備なく脱線(運輸安全委)
熊本地震で九州新幹線が脱線した事故で、運輸安全委員会は、現場の地盤が軟らかかったことなどで揺れが増幅したことが原因とする報告書を公表した。現場には車輪の揺れを物理的に抑える「脱線防止ガード」が未設置だったが、設置していれば脱線しなかったと指摘。JR九州に地震リスクを踏まえて脱線防止対策を一層推進するように求めた。
事故は2016年4月14日午後9時26分ごろ発生。6両編成の回送列車が熊本駅(熊本市)の南を時速約80キロで走行中、運転士が衝撃を感じて非常ブレーキをかけたが脱線した。当時乗っていたのは運転士だけで、けがはなかった。
報告書によると、現場の震度は6弱~6強だったとみられる。現場は地盤が軟らかかった上、車両が高架橋上にあったことで地震による揺れが増幅し、車両が横揺れしやすい振動数となった。24ある車軸のうち22軸が脱線し、ずれ幅は3~57センチだった。車両や線路には問題はなかった。
JR九州は地震の揺れを感知した場合、車両に非常ブレーキがかかるシステムを導入していたが、震源から現場までの距離が短く、列車の速度を十分に抑制できなかった。同社は九州新幹線の走行区間で地震が懸念される場所では脱線防止ガードを導入していたが、脱線現場は未整備だった。
一方、安全委のシミュレーションでは、脱線防止ガードを設置した場合は脱線を防げたと判明。報告書は高速で走る新幹線の脱線は大きな被害を招く恐れがあるとして、同社に対して新幹線沿線にある活断層の存在を考慮してガードの設置計画を見直すよう求めた。同社は事故後に現場周辺など計17キロの区間に脱線防止ガードを設置した。
12、豪雨多発で浸水時の救助強化(消防庁)
消防庁は、豪雨で浸水があった場合の消防隊員による救助体制の強化を図ることにし、安全で効率的な救助手順や必要な機材を盛り込んだ全国統一のマニュアルを来年の春までに作成することにした。
2017年7月に発生した九州北部の豪雨など、近年、死傷者を伴う豪雨が多発している。統一マニュアルはこうした集中豪雨や台風、高潮、津波に伴う浸水を想定している。そして、流れが急な河川や都市部の洪水といった「流水域」と、池や沼、地下空間などの「静水域」に分類して、救助方法や装備について検討を行うことにしたものである。
マニュアルでは夜間や濁流時の対応、車内から助け出す際の注意点、隊員の安全対策も明記することにしている。水害対策車、成人が乗っても水に沈まない担架など先進的な機材についても取り上げることにしている。
浸水被害が大きい場合、全国の消防本部で構成する緊急消防援助隊が出動する。援助隊に登録している消防本部には、水害対策車など車両計3台、情報収集に役立つ小型無人機「ドローン」計10機を配備することにしており、2019年度以降も装備の充実を目指す。
13、災害時に避難者の位置をスマホで把握(内閣府・総務省)
政府は、地震などの大規模災害時にスマートフォンや携帯電話の位置情報から避難者の居場所を把握する実証実験を行っている。避難者がどこに何人移動したかを素早く把握し、車中泊の人も含めて、食料などの物資提供や自治体の人員配置といった支援に生かすのが狙いで、数年以内の実用化を目指す。
2016年の熊本地震では、余震の不安から学校の体育館など、指定された避難所ではなく、車中泊を選ぶ避難者が多く出て、行政の支援が行き届かないことが課題になった。
実証実験は、膨大に蓄積された“ビッグデータ”を災害対応に活用する取り組みの一環として行われる。一般的にスマホや携帯電話の位置情報は基地局に送られ、都市部では250メートル、地方では500メートルの範囲で所有者の位置を把握できる。そこで、NTTドコモ、KDDI、ソフトバンクの携帯大手3社が協力、避難者が持っているスマホや携帯電話の位置情報を基地局でキャッチし、プライバシーを保護するため匿名データに処理した上で、災害発生から12時間以内に自治体へ提供することにするものである。
14、火災警報器の設置率 全国平均81.7%(消防庁)
消防庁はこのほど、住宅用火災警報器の設置率の調査結果をまとめたが、それによると、全国設置率81.7%(6月1日現在)で、前年同月比で0.5%増加していることが分かった。
都道府県別にみると、設置率が高いのは、①福井県94.6%、②鹿児島県89.1%、③宮城県88.9%、④東京都88.6%、⑤石川県87.9%、となっている。反対に設置率が低いのは、①沖縄県57.5%、②佐賀県71.1%、③群馬県71.8%、④栃木県73.2%、⑤茨城県74.0%、の順だった。
15、民法規定で解体 持ち主所在不明の空き家(大田区)
東京都大田区は持ち主の所在が分からない空き家を民法の規定を活用して解体した。放置された空き家は倒壊の恐れや景観・ごみ問題など周辺への影響が大きく、行政も対応を迫られている。空き家対策特別措置法施行を受けて行政代執行で空き家を取り壊す例が出つつあるが、民法の規定を使う例は珍しいという。
活用したのは民法の「不在者財産管理人」と呼ぶ規定。管理人が建物の解体や敷地売却などの手続きを一括してできる。持ち主の所在が分からない場合、特措法では略式代執行という手続きで空き家を解体できる。ただ管理人選任が認められるならば民法の規定を使うほうが迅速で費用の回収もしやすいという。都内では世田谷区がこの方法を使った例がある。
解体したのは景観などから「特定空き家」と判定済みの田園調布にある物件。持ち主調査の過程でみつかった資産から解体費用を出したため区の負担はなかった。
[防災短信]
- 01、常磐線 待望の再開
~富岡―竜田間 原発事故から6年半 JR東日本~ 2017年10月21日付 日本経済新聞 -
02、原発事故、生活再建進まず
~住民に諦めと無力感 被災4町村~ 2017年10月21日付 日本経済新聞 - 03、災害研究 東大が世界一
~背後に東日本大震災~ 2017年11月21日付 日本経済新聞 -
04、中間貯蔵施設が稼働
~2017年10月 大熊町~ 2017年11月20日付 日本経済新聞 - 05、ペルーから津波 実はなかった?
~16世紀の東北転記ミス指摘~ 2017年11月18日付 日本経済新聞(夕刊) - 06、民泊解禁前に独自規制を準備
~住宅地での制限検討 新宿区・大田区~ 2017年11月10日付 日本経済新聞 - 07、利用者情報生かされず復旧長引く
~東急 池尻大橋駅の送電線ショート運休~ 2017年11月16日付 レスポンス - 08、国交省 補正予算7,271億を防災・減災に
~2017年度~ 2017年12月19日付 建通新聞 - 09、三井不動産 施工3社提訴
~横浜傾斜マンション 計459億円請求~ 2017年11月29日付 日本経済新聞 - 10、九州豪雨 避難所ゼロに
~福岡・大分両県 1,200人なお仮住まい~ 2017年11月27日付 日本経済新聞 -
11、民泊監視法案成立へ
~2017年臨時国会 観光庁~ 2017年11月27日付 日本経済新聞 - 12、安全確認指示怠った疑い
~笹子事故 当時のNEXCO中日本社長ら8人送検~ 2017年12月01日付 日本経済新聞
【参考文献】
- 01、2017年10月27日付 日本経済新聞(夕刊)
- 02、2017年10月30日付 日本経済新聞
- 03、2017年11月07日付 日本経済新聞
- 04、2017年11月09日付 日本経済新聞(夕刊)
- 05、2017年11月16日付 日本経済新聞
- 06、2017年11月20日付 日本経済新聞
- 07、2017年11月20日付 日本経済新聞
- 08、2017年11月25日付 毎日新聞
- 09、2017年11月29日付 日本経済新聞
- 10、2017年11月29日付 日本経済新聞
- 11、2017年11月30日付 日本経済新聞(夕刊)
- 12、2017年11月 UGMニュース
- 13、2017年11月 UGMニュース
- 14、2017年11月 UGMニュース
- 15、2017年12月01日付 日本経済新聞