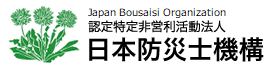防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
防災評論(第92号)
山口明の「防災・安全 ~国・地方の動き~」
防災評論家 山口 明氏の執筆による、「防災・安全 ~国・地方の動き~」を掲載致します。防災対策を中心に、防災士の皆様や防災・安全に関心を持たれている方々のために、最新の国・地方の動きをタイムリーにお知らせすることにより、防災士はじめ防災関係者の方々の自己啓発や業務遂行にお役立てて頂こうとするものです。今後の「防災・安全 ~国・地方の動き~」にご期待下さい。
山口明の防災評論
防災評論(第92号)【平成30年3月号】
【目次】
〔政治行政の動向概観〕
〔個別の動き〕
- 1、水道管耐震率なお38%(厚生労働省)
- 2、少ない女性消防士 採用を(消防庁)
- 3、マンホールふた 耐用年数超過300万個 老朽化の恐れ(日本グラウンドマンホール工業会)
- 4、二重ローン対策 3年延長(復興庁)
- 5、消防に機動部隊創設(東京都)
- 6、「臨時情報で避難」6割(南海トラフ沿岸地市町村)
- 7、AIで火山活動分析(東工大・京大)
- 8、衛星データを「京」で処理(理研・気象庁研)
- 9、「南岸低気圧」沿岸を通過(気象庁)
- 10、噴火避難計画 2/3不十分(内閣府)
- 11、十和田火山 噴火で原発に降灰も(青森・岩手県)
- 12、ストーブ火災 風呂周り124件死者4人(消防庁・NITE・厚生労働省)
- 13、予測難しい水蒸気噴火(気象庁)
- 14、北海道沖でM9級地震「切迫」(地震調査委)
〔政治行政の動向概観〕
最近は九州霧島連峰の新燃岳が爆発的噴火を繰り返し、気象庁が噴火警戒レベルを引き上げる事案があったが、概して自然災害については低レベル、平穏で推移している。しかし、人為的事件については国内外でさまざまな激震があり、その行方に目が離せない毎日が続く。 国内では学校法人への国有地払い下げ問題が連日国会で取り上げられ、財務省元担当局長の国会証人喚問までセットされたが、例によって証言内容は真相究明には程遠く、マスコミが騒ぐほど事態の進展はみられていない。そもそもほかの重要案件を差し置いて血道をあげなければならない問題なのかということを別にしても、国会がやるべきことは検察まがいの犯人捜しではなく、国有財産や公文書管理の制度的在り方やその管理体制にチェックを入れるべきで、それらは勢い地味となってもやり遂げなければならない必要課題である。その意味では防災の分野と同じく着実な制度改善に向けての努力が必要なのである。 一方、国外については東アジア情勢に重大な変化が起きている。国際社会からの度重なる制裁に窮地に追い込まれた北朝鮮の3月末電撃的に北京を訪問、中国の支援を取り付けようと躍起になっている。これで北朝鮮をめぐる国際情勢はにわかに流動化を強めた。韓・米の動きと合わせ、一見東アジアに平和の風が吹き始めたように見えるが、その本質は北朝鮮の焦りにあると考えなければならない。今後の動向によっては、同国が“暴発”する恐れがむしろ強まっており、そうなれば日本の安全に重大な影響が出る。深刻な人為災害にならないよう日本政府は同国への対応に難しい舵取りを迫られている。地域の防災士にとっても、こうした人為災害となるリスクに関しても、決して余所事でない情勢にあることをよく認識して、身の回りの安全に配慮していく姿勢が求められる。
〔個別の動き〕
1、水道管耐震率なお38%(厚生労働省)
震度6程度の地震に耐えられる主要な水道管の割合が2016年度末時点の全国平均で、38.7%だったことが厚生労働省の調査で分かった。2015年度末に比べて1.5ポイントの増加にとどまった。国は2022年度末までに50%にする目標を掲げているが、自治体の財政状況や技術者不足などから達成は難しいとみられている。 導水管や送水管などの基幹的な水道管の総延長は約9万9千キロ。このうち継ぎ目が壊れにくい耐震管や、地盤が強く耐震性が高いと確認されたのは約3万8千キロだった。 震度6程度の揺れに耐えられる水道管の割合を都道府県別にみると、神奈川県(67.2%)が最も高く、最も低い秋田県(22.8%)とは3倍近い差があった。 耐震化が進まない背景には、人口減少で水道料金の収入が下がり続け、設備投資の余裕がない自治体の厳しい財政状況がある。また、団塊世代の大量退職によって水道事業の技術者は30年前と比べて約3割減っており、ノウハウの継承が課題となっている。人口が少ない自治体では水道事業を数人の職員で担っているケースもある。
2、少ない女性消防士 採用を(消防庁)
消防庁は、女性の消防士を増やそうと、採用が進んでいる消防本部の人事担当者らをアドバイザーとして自治体などに派遣する制度を始めた。女性消防士は2017年4月1日現在、4,240人で全体のわずか2.6%。男性の仕事というイメージの払拭、家庭との両立支援が課題で、採用促進や職場環境の整備を助言する。 消防士は正式には「消防吏員」と呼ばれる。階級を持ち、消火や救急、査察、指令センターなどの業務を行うが、女性がまったくいない本部も目立つ。消防庁は、2026年4月までに女性の割合を5%へ引き上げる目標を掲げている。女性が増えれば、子供や高齢者ら多様な住民のニーズによりきめ細かく対応できるからだ。 ただ両立支援のほか、トイレや仮眠室といった女性用施設が少ないといった課題もある。消防庁が設けた検討会は報告書で「女性が働く職場というイメージが希薄」と指摘している。
3、マンホールふた 耐用年数超過300万個 老朽化の恐れ(日本グラウンドマンホール工業会)
下水道用マンホールのふたのうち、国の定める標準耐用年数を過ぎて老朽化の恐れがあるものが、全体の2割に当たる約300万個に上るとみられることが業界団体の推計で分かった。劣化の進み具合はまちまちだが、使い続ければ表面がすり減ってスリップ事故が起きるなどの危険もあるという。 業界団体は主なメーカーでつくる「日本グラウンドマンホール工業会」(東京)。全国に設置されている下水道用ふたは約1500万個とみられ、市町村が管理。国土交通省は「老朽化したふたの規模は不明」とした上で「危険性のあるふたが一定数あるかもしれず、各自治体は計画的に交換してほしい」と呼び掛けている。 ふたの標準耐用年数は車道部で15年、歩道部30年が交換の1つの目安とされる。下水道は高度成長期に集中的に整備された経緯があり、同工業会が交換ペースなどから推計したところ、現時点で設置から30年を超えたふたが約300万個残っている計算になるという。 ふたの多くは金属製で、道路のアスファルト部分よりも滑りやすい。表面にデザインされた模様もすり減ってくるため、老朽化が進むほどスリップの危険性は高まる。 トラックの大型化に伴い、幹線道路に置くふたの強度基準は1995年に25トン対応に引き上げられたが、それ以前は20トン対応が主流。20トン対応を使い続ければ、強度不足で破損の恐れもある。 ゲリラ豪雨時に下水道管内の水圧が急激に高まり、下水が噴き上げてふたが勢いよく飛ぶケースが各地で起きているが、古いふたには「飛散防止装置」が付いていないことも、交換が求められる理由になっている。
4、二重ローン対策 3年延長(復興庁)
与党は東日本大震災で被災した企業などの二重ローン対策を3年間延長する法案を、通常国会に提出・成立した。震災前の債権の買い取りなど、被災企業への支援決定の期限を2021年3月末まで延ばす。経営基盤がなお弱い再建途上の企業の資金繰りを支えることで、被災地の産業復興に万全を期す。 2012年に政府が設立した「東日本大震災事業者再生支援機構」の設置法改正案を議員立法で提出、同機構は、被災前の借金が残る中で工場の再建などで新たな借金が必要になった被災企業を金融支援する。事業再生計画をつくったうえで被災前の債権を金融機関から買い取るほか、一部の債務免除、出資やつなぎ融資なども手掛ける。支援件数は2017年11月末時点で729件。 支援決定件数は2013年をピークに減少傾向にある。集落の高台移転などに時間がかかり、これから仮設の店舗や工場から出て本格的に再建を進める中小企業もある。東京電力福島第1原子力発電所の事故の影響を受ける企業からは、風評被害を訴える相談がなお続いている。 政府も2018年度予算案で、機構の財務基盤を強化するため100億円の出資を盛り込んだ。2020年度までを「復興・創生期間」と位置づけ、被災地の自立支援に全力を挙げる方針を示している。
5、消防に機動部隊創設(東京都)
東京都は2018年度から、爆破テロや大規模災害への対応に特化した「統合機動部隊」(仮称)を東京消防庁に創設することを決めた。2020年の東京五輪・パラリンピックに向け、テロや災害への対策強化を目指す一環で、2018年度予算案に約2億3千万円を計上する。 都は、指揮官が乗り込んで直接現場で指示を出すことのできる「指揮統制車(コマンドカー)」を導入。これまでは対策本部からすべての指揮命令が出される仕組みだったが、災害現場で消防隊や救急隊に直接指示できるようにし、きめ細かく対応できるようになる。 指揮統制車には周囲を映せるカメラや、現場の消防車などが搭載するカメラから送られてくる映像を映し出すモニターなども装備する。 装甲や強化ガラスなどを備え、爆発に耐えられる「救出救助車」も新たに整備する。
6、「臨時情報で避難」6割(南海トラフ沿岸地市町村)
南海トラフ地震の津波で大きな被害が予想される139市町村にアンケートを実施したところ、地震発生の可能性が高まったとする臨時情報を政府が発表した場合、6割超の91市町村が避難勧告などの発令を検討すると回答した。臨時情報は予知と違って確度が低く、国は現状では避難の呼びかけまでは求めていない。だが、多くの自治体は、住民生活に影響が出ても安全を最優先とせざるを得ないと考えていることが明らかになった。 アンケートは、気象庁が昨年11月から「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を始めたことを受け、津波避難対策を強く求められている1都13県の139市町村に実施。臨時情報への対応やその理由などを尋ね、全市町村が回答した。 避難勧告などの発令については、「検討する」91▽「検討しない」48だった。検討する自治体のうち、40市町村が状況次第で避難勧告や避難指示の発令も選択肢に入れるとする一方、30市町は「避難準備・高齢者等避難開始」にとどめる対応を視野に入れている。残る21市町村は具体的な発令内容の回答がなかった。 南海トラフ地震は東海、東南海などの震源域があり、それぞれマグニチュード(M)8級、連動すると最大M9の地震が懸念される。臨時情報は主に①想定震源域内でM7級以上の地震②東海地方で異常な地殻変動――の場合に発表される。 「検討する」と答えた市町村のうち、①では35市町村が避難指示か避難勧告の発令を検討すると答え、②は8市町村にとどまった。 「検討しない」とした市町村に理由を尋ねると、住民生活の混乱を懸念する声(30市町村)が最も多かった。「避難勧告を出すほど確度の高い情報ではない」(神奈川県茅ケ崎市)という趣旨の意見も目立った。 「検討する」とした市町村は「津波到達まで数分と想定され、何もしないわけにはいかない」(静岡県伊豆市)などと切迫した事情を抱えるが、勧告を発令できる期間は「3日程度」の回答が多く、長期の避難呼びかけは難しそうだ。 政府は臨時情報への対応を示したガイドラインを策定する予定。ただ、策定時期のめどは立っておらず、市町村から作業を急ぐよう求める声が高まっている。 臨時情報は大きな地震や地殻変動といった前兆とみられる現象をとらえて発表するが、精度は低い。気象庁も認めているように、世界の地震記録から単純計算すると、前兆の可能性がある地震がマグニチュード(M)7級の場合、1週間以内に同規模以上の大地震に見舞われる確率は2%程度だ。前兆現象が地殻変動のケースだと、大地震の発生確率を示すことすら難しい。 臨時情報が「空振り」に終わる可能性が小さくないだけに、市町村としてはなおさら悩ましいと言えよう。
7、AIで火山活動分析(東工大・京大)
東京工業大学と京都大学は、火山活動を人工知能(AI)で詳しく分析する手法を開発した。大量のデータから特徴を見つける「深層学習」を使い、観測データから爆発的な噴火が起きた時期などを精度よく見分けられるようにした。新手法を生かせば、観測体制が不十分な火山も含めて各地の火山活動の予測に役立つと期待する。 研究には桜島(鹿児島県)の2009~2016年の観測データを用いた。火口方向などの地盤のひずみ、揺れなどのデータが含まれている。4年分をAIの学習・検証用とし、残り4年分を分析などに充てた。 100分ごとに分けたデータをAIで調べ、その中から特徴を見つけ出した。爆発的な噴火が起きたタイミングを8~9割の確率で見分けられるようになった。長期間の観測データから、爆発的な噴火がいつ起こるかを予測する研究などに役立つという。 従来、爆発などの火山活動は地盤のひずみや傾き、揺れなどを測る機器などのデータをもとに人手で分析しており、手間がかかった。新手法が確立すれば、観測データをもとに火山活動が把握でき、警戒や防災に生かせると研究チームはみている。
8、衛星データを「京」で処理(理研・気象庁研)
理化学研究所と気象庁気象研究所などは、気象衛星「ひまわり8号」による雲の観測データをスーパーコンピューター「京」に取り込み、台風の急速な発達や豪雨発生を高精度に予測する技術を開発した。気象庁は予報業務に応用することを検討する方針で、大雨や洪水のリスクをいち早く正確にとらえ、防災に役立つと期待される。 ひまわり8号は赤外線による観測で雲の高さや厚さのデータを10分ごとに集めている。このデータをスパコンに直接取り込み、気象予測に利用できるようにした。 2015年で最も強く発達した台風13号と、鬼怒川の氾濫をもたらした同年9月の関東・東北豪雨の観測データを使って検証した。台風の中心気圧が下がって強くなる過程や雨雲の位置を実際の観測に近い形で予測できた。 豪雨についても大雨の位置や範囲の予測精度が上がり、鬼怒川の流量の急増を従来より早く捉えられた。 気象庁は現在、1時間ごとに気象予測を更新しているが、10分ごとの更新による新しい天気予報の可能性を示した。
9、「南岸低気圧」沿岸を通過(気象庁)
1月22日夜から関東南部に大雪をもたらした原因は、日本列島沿岸に接近した「南岸低気圧」が関東上空の寒気と重なったためとみられる。低気圧のコースや寒気の有無などで雨か雪かが変わるが、気象庁は「今回は雪が降りやすい条件がそろった」と話す。 南岸低気圧は温かく湿った空気を伴い、関東沿岸近くを通過した場合、低気圧の北側では降水帯が形成されて雨になりやすい。 気象庁によると、今回の低気圧は21日に中国・上海付近で発生。日本列島の太平洋沿岸を北東へ進み、22日夜に伊豆諸島を通過した。この際上空1,500メートル付近のマイナス3度以下の寒気が関東南部まで南下したため、雨ではなく雪になったという。 南岸低気圧の影響で首都圏が大雪となったのは、2014年2月以来。この時は都心で積雪27センチを観測した。それ以前にも2013年1月に8センチ、2006年1月に9センチを記録した。
10、噴火避難計画 2/3不十分(内閣府)
国が火山災害警戒地域に指定した全国49火山の延べ155市町村のうち、2017年6月時点で計画の策定を終えたのが51市町村にとどまっていることが分かった。約3分の2の自治体が未策定で、草津白根山の噴火で被害が出た群馬県草津町も策定していなかった。 死者・行方不明者63人を出した2014年9月の御嶽山(長野・岐阜両県)噴火後、避難計画の策定は義務化されたが、対策が徹底されていない状況が浮かび上がった。 国は2015年に活火山対策特別措置法を改正。火山災害警戒地域に指定された49火山の周辺自治体に対し、避難計画を策定して地域の防災計画に反映させたうえ、ホテルやスキー場などの集客施設も避難確保計画を作成するよう義務づけた。 自治体による避難計画には情報伝達のほか、避難経路や避難場所など6項目を盛り込む必要がある。内閣府防災担当によると、全項目の策定を終えたのは延べ155市町村のうち51市町村(2017年6月時点)。草津白根山に近い群馬、長野両県内の対象5町村のうち策定済みは嬬恋村のみだった。 草津町は1983年の白根山噴火以降、火口に近いレストハウスを鉄筋コンクリート造りに建て替え、山頂付近に13個のシェルターを整備して警戒してきたが、町は「気象庁などから本白根山を警戒するようにとの指摘はなく、噴火する山ではないという認識だった」(総務課)と困惑する。 噴火警戒レベル1(活火山であることに留意)の那須岳や日光白根山を抱える栃木県では、いずれの市町村も避難計画の策定を終えていない。 同レベル1の岩木山(青森県弘前市)の麓で旅館を営む男性(40)は噴火への備えをしていない。草津白根山の噴火を知り、「避難ルートなどを考える必要があるのかもしれない」と話した。
11、十和田火山 噴火で原発に降灰も(青森・秋田県)
青森、秋田両県は、県境に位置する十和田火山の被害想定を初めて公表した。大規模噴火時は十和田湖にある火口から30キロ圏に火砕流が達し、数十万人が避難対象になると推定。青森県の下北半島に集中し、いずれも30キロ圏外にある原発などの原子力施設には、火山灰が積もる可能性があるとした。 活火山の十和田火山は1万5千年前に巨大噴火が発生。その後は千~3千年ごとに噴火し、平安時代の915年には、1990年代に長崎県で起きた雲仙・普賢岳噴火の約9倍に相当する規模のマグマ噴火があった。 被害想定は過去のデータから、最悪の場合は平安時代と同規模で、噴煙の高さが20~30キロの噴火が起きると予測している。高温の火山灰やガスなどが斜面を流れ下る火砕流は、青森、秋田、岩手3県の17市町村に到達する恐れがあるとした。 日本原燃の使用済み核燃料再処理工場(青森県六ケ所村)や東北電力の東通原発(同東通村)などがある下北半島に火砕流は達しないが、風向きによって火山灰や軽石などの降下物が10センチ以上積もると推定した。
12、ストーブ火災 風呂周り124件死者4人(消防庁・NITE・厚生労働省)
脱衣場や浴室に置いたストーブが火元となった建物火災が、2016年までの5年間に全国で124件あり、死者が4人出ていたことが、消防庁のまとめで分かった。冬場の入浴時に急激な温度差を和らげようと脱衣場にストーブを置く家庭が多いが、衣類など燃えやすいものも多く、関係機関は注意を呼びかけている。 消防庁によると、2012~2016年の5年間の建物火災のうち、脱衣場や浴室のストーブが原因となった火災は計124件。そのうち死者は4人、負傷者が44人出ている。使われたストーブの種類別では、電気が79件と全体の6割を超え、石油が42件、まき・ガスが3件だった。 製品評価技術基盤機構(NITE)の実験では、電気ストーブにタオルが触れてから約6分40秒後に発火が確認された。担当者は「火を使わない電気ストーブは危険性を感じにくいが、燃えやすいものが触れれば火事になりうる」と注意を呼びかけている。 厚生労働省の調査によると、入浴中の事故死は年間約1万9,000人に上り、気温が下がる12~2月の冬場に入浴中の急死は多発している。 背景の1つには、寒い脱衣場から浴槽に入ることで急激な温度変化にさらされ、血圧が急激に上下して失神や心筋梗塞などを起こす「ヒートショック」があるとみられる。その予防策として、脱衣場や浴室を電気ストーブで暖めている家庭がある。
13、予測難しい水蒸気噴火(気象庁)
草津白根山の本白根山(群馬県)が1月23日噴火し、1人の死者と11人の負傷者を出した。気象庁は「水蒸気噴火の可能性が高い」との見解を発表した。火山の噴火には大きく分けて3種類あるが、水蒸気噴火は特に前兆を捉えることが難しいとされる。2014年に多数の死傷者を出した御嶽山(長野・岐阜県)の噴火も同じ水蒸気噴火だった。 水蒸気噴火は地下にたまっていた地下水が沸騰して瞬間的に大量の水蒸気に変わり、周囲の岩や土砂などを吹き飛ばす噴火だ。急に圧力が上がったりすると、それまで安定していた地下水が水蒸気のガスになり、爆発的に膨れあがる勢いで周囲の岩などを一気に吹き飛ばす。 今回の本白根山の噴火は水蒸気噴火の可能性が高い、と気象庁は説明している。噴火で飛んできた岩石や火山灰を調べると、もともと本白根山にあった岩石が吹き飛ばされたもので、新しいマグマが地下から噴き出したときにできる成分が見つからないからだ。 噴火には3種類あるが、水蒸気噴火以外の2種類の噴火には直接マグマが関わっている。「マグマ噴火」ではどろどろに溶けたマグマが地上に噴き出し、「マグマ水蒸気噴火」は地下水が熱いマグマに触れて沸騰、水蒸気に変わるために起きる。このためマグマ噴火やマグマ水蒸気噴火の時は、吹き飛ばされた火山灰などにマグマから生じた成分が混じっている。 しかし水蒸気噴火はマグマから岩盤などを通して伝わった熱で間接的に地下水が温められるものの、マグマは直接噴火には関わらない。そのためマグマの成分が見つからなければ、水蒸気噴火が起きた可能性が高くなる。 噴火に直接マグマが関わっているかどうかは、噴火の前兆の捉えやすさにも関わっている。マグマ噴火やマグマ水蒸気噴火は、数か月前から数日前に、異常現象が前兆として起こることが多い。噴火直前に地下でマグマが袋状の塊になった「マグマだまり」が膨らむと、地面が膨らんだり、山の斜面の角度が変わったりする。これらの地殻変動は、全地球測位システム(GPS)などで捉えられる。 マグマだまりからマグマが上がってくると、マグマの通り道で岩石が壊れて小さな地震が起こる。地下のマグマやガスが動くと、火山性微動と呼ばれるわずかだが特徴的な揺れも起こる。これらは地震計で検知できる。 だが水蒸気噴火ではマグマ噴火などに比べて規模が小さく、何らかの異常は起こるが、噴火口の近くでないと捉えられない。今回は、警戒されていた火口とは別の場所で噴火が起きたため、周囲に観測機器も少なく前兆を捉えられなかった。 2014年の御嶽山では水蒸気噴火だけで次第に活動は収束した。しかし水蒸気噴火が起きた後にマグマが上昇し、新たな噴火につながった例もある。1991年に43人の死者・行方不明者を出した雲仙・普賢岳では1990年11月に水蒸気噴火が起きた後、約半年後にマグマ噴火が始まった。 マグマ噴火になると、地上に噴き出したマグマは溶岩になる。数キロメートルから数十キロメートルの高さになった噴煙が崩れると、火砕流になることがある。火砕流は雪崩のように崩れた岩に火山灰とガスが混じって時速70~110キロメートルの速さで山腹を流れ下る。噴火現象のなかでも最も危険といわれ、雲仙・普賢岳の死者も火砕流にのまれて犠牲になった。 火山の地下で起こっている活動は単純ではない。3種類の噴火のタイプも噴火で噴き出した火山灰などの特徴をもとに分類したもので、火山内部の活動を必ずしも反映したものではないとする説もある。
14、北海道沖でM9級地震「切迫」(地震調査委)
政府の地震調査委員会が2017年12月に公表した北海道東部沖の地震評価は、これまで同地域で考えられていなかったマグニチュード(M)9クラスの超巨大地震を想定に入れた。東日本大震災で想定外の揺れと津波に襲われた教訓を背景に、過去の地震で起きた津波による堆積物の調査や震源域の見直しなどをもとに最大限のリスクを算出。超巨大地震は「切迫している」と警鐘を鳴らした。 評価の対象となった北海道東部沖には、日本列島が位置する陸のプレートの下へ、太平洋プレートが沈み込む千島海溝がある。太平洋プレートが陸側のプレートを引きずりこもうとするため、陸と海の境界付近にひずみがたまり、過去に何度も大規模な地震が発生している。 地震調査委は過去の震源地や海底地形の変化などから北海道東部沖の震源域を「十勝沖」「根室沖」「色丹島沖および択捉島沖」の3つに区分。それぞれの震源域で個別に発生する地震に加え、複数の震源域が連動して地震を起こすリスクも考慮した。 東日本大震災では、岩手県沖から茨城県沖にまたがるいくつもの震源域が連動して超巨大地震が引き起こされた。これと同様に、北海道東部沖でも複数の震源域が連動した超巨大地震が起こり得ると評価した。 こうした超巨大地震を新たに想定したのは、過去の津波堆積物の調査が進んだことも理由だ。北海道大学などの北海道東部での津波堆積物の調査結果から、超巨大地震は過去6,500年の間に最多で18回発生したと判断。直近の発生は約400年前で、この時、北海道東部の太平洋側では沿岸から4キロメートル内陸まで大津波が押しよせ、津波は高さ20メートルを超えたとの報告もある。 千島海溝で超巨大地震が起こると、北海道だけでなく東北地方まで影響が及ぶ危険もある。津波や揺れの想定が見直された場合、東北地方沿岸部の原子力施設や自治体などは防災対策の練り直しを求められる可能性もある。
[防災短信]
- 1、図上訓練で防災力向上
~東大などがプログラム 新宿区~ 2018年2月02日付 日本経済新聞 - 2、追悼行事、相次ぐ取りやめ
~阪神・淡路大震災から21年 関係者高齢で限界~ 2018年1月16日付 神戸新聞 - 3、土砂崩れで13人死亡
~米加州 山火事で樹木焼失~ 2018年1月10日付 日本経済新聞(夕刊) - 4、米国、自然災害の被害額最高
~2017年、34兆円 ハリケーン相次ぐ~ 2018年1月10日付 日本経済新聞 - 5、ヤミ民泊排除 自治体動く
~大田区、京都市、大阪 観光客など、犯罪誘発の恐れ~ 2018年1月09日付 日本経済新聞 - 6、火砕流1.8キロ先に到達か
~草津白根山噴火、火口2か所 1メートル噴石も~ 2018年1月25日付 日本経済新聞 - 7、全国50火山 常時監視
~気象庁「噴火速報」出せず 判断材料のカメラ映像なし~ 2018年1月24日付 日本経済新聞 - 8、大雪の都内 220人搬送
~首都高10時間以上立ち往生~ 2018年1月23日付 日本経済新聞(夕刊) - 9、水道管が凍結「水出ない」
~厳しい冷え込みの都内 水道局に2,130件のクレーム~ 2018年1月26日付 日本経済新聞 - 10、阪神・淡路大震災23年
~看護師、被災者つなぐ 復興住宅訪ね心身ケア~ 2018年1月18日付 日本経済新聞 - 11、「帰宅困難」外国人が訓練
~六本木ヒルズ 森ビル~ 2018年1月18日付 日本経済新聞 - 12、刑法犯 3年連続戦後最少
~警察庁 2017年は91万件~ 2018年1月18日付 日本経済新聞(夕刊) - 13、荒れる人工林 水源地ピンチ
~東京都多摩川上流 土砂流入し、水質悪化~ 2018年1月15日付 日本経済新聞 - 14、緊急地震速報 再び誤報
~気象庁「技術的限界も」~ 2018年1月06日付 日本経済新聞 - 15、操縦士「2人乗り」後押し
~消防庁 防災ヘリの安全強化~ 2018年1月13日付 日本経済新聞
【参考文献】
- 1、 2018年1月01日付日本経済新聞
- 2、 2018年1月07日付 日本経済新聞
- 3、 2018年1月08日付 日本経済新聞
- 4、 2018年1月10日付 日本経済新聞
- 5、 2018年1月11日付 日本経済新聞
- 6、 2018年1月14日付 日本経済新聞
- 7、 2018年1月15日付 日本経済新聞
- 8、 2018年1月18日付 日本経済新聞
- 9、 2018年1月23日付 日本経済新聞(夕刊)
- 10、 2018年1月25日付 日本経済新聞
- 11、 2018年1月25日付 日本経済新聞
- 12、 2018年1月26日付 読売新聞
- 13、 2018年2月02日付 日本経済新聞
- 14、 2018年2月02日付 日本経済新聞