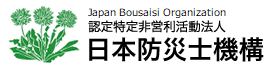防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
防災評論(第93号)
山口明の「防災・安全 ~国・地方の動き~」
防災評論家 山口 明氏の執筆による、「防災・安全 ~国・地方の動き~」を掲載致します。防災対策を中心に、防災士の皆様や防災・安全に関心を持たれている方々のために、最新の国・地方の動きをタイムリーにお知らせすることにより、防災士はじめ防災関係者の方々の自己啓発や業務遂行にお役立てて頂こうとするものです。今後の「防災・安全 ~国・地方の動き~」にご期待下さい。
山口明の防災評論
防災評論(第93号)【平成30年4月号】
【目次】 〔政治行政の動向概観〕 〔個別の動き〕
- 1、2つの地震混同か 緊急地震速報(気象庁)
- 2、噴火避難計画2/3不十分(内閣府)
- 3、住宅の耐震診断「実施せず」52%(内閣府)
- 4、火山監視 専門家足りない(気象庁)
- 5、困窮者住宅の防火強化(厚生労働省)
- 6、災害補償付き住宅ローン 金利0.035~0.5%上乗せ(市中金融機関)
- 7、消防広域化の期限延長(消防庁)
- 8、交通死亡事故 高齢運転者 高止まり(警察庁)
- 9、保険の加入率 自転車は6割(警察庁)
- 10、倒壊の恐れ 2割低下(東京都)
- 11、スプリンクラー設置1割満たず(厚生労働省)
〔政治行政の動向概観〕
4月は東アジア国際情勢にとって劇的な変化の月となった。地域の不安定要因の中核であった北朝鮮が突如態度を急変させ、韓国、米国との対話に乗り出したのである。世間やマスコミは北首領のこの融和的行動に肯定的であるが、日本を取り巻く安全保障上の懸念はむしろ増大の方向にあると冷静に事態を直視する必要がある。つまり、米韓と北の対話がうまく運んだ場合は在韓米軍の撤退により、日本は半島の敵性国と直面する危機に、さらにその背後にいる中国を含んで日本包囲網が形成され、孤立を深めることとなる。逆に対話がうまく行かなかった場合は事態はより深刻化し、北による暴発はもはや不可避になるかもしれない。朝鮮半島の安定は今も昔も日本にとって生命線であることに変わりなく、この点、政府のみならず国民も十分認識して国際社会の安全を守っていく必要がある。 日本列島内に目を移すと、九州耶馬渓付近で発生した突然の土砂崩れにより6人の尊い命が失われた。これまでも大小数えきれないほどの土砂災害に見舞われてきた我が国土であるが、今次災害は従来とは異なる常識外れのものとなった。すなわち降雨や地震の起きていない状況で大規模な土砂崩れが発生した点である。現場を見る限り特に変わった地形、斜面ではない中、全国津々浦々に同様の災害は起こりうるのか?防災に携わる者はこれまでの常識にとらわれず、しっかりと現場の分析と対策を講じるべきであろうし、防災士はこれからの動向に十分注意して見守り、自らの周辺に同様の災害が起きりうるのかどうか、的確な判断が下せるようさらに学習を深めていかなければならない。
〔個別の動き〕
1、2つの地震混同か 緊急地震速報(気象庁)
1月5日午前11時2分ごろ、茨城県南部で震度3の地震があった。気象庁によると、震源地は茨城県沖で、震源の深さは約40キロ。地震の規模はマグニチュード(M)4.4と推定される。 また、同11時2分ごろ、石川県で震度3の地震があった。震源地は富山県西部で、震源の深さは約20キロだった。地震の規模はM3.9と推定。いずれの地震も津波の心配はない。 気象庁は関東地方や福島県で強い揺れが予想されるとして緊急地震速報を発表したが、大きな揺れは観測されなかった。気象庁は異なる地域で同時に起きた2つの地震を処理した結果、1つの大きな地震として解析した可能性があるとみて調査している。緊急地震速報は最大震度5弱以上が予測される場合に発表される。
2、噴火避難計画2/3不十分(内閣府)
国が火山災害警戒地域に指定した全国49火山の延べ155市町村のうち、2017年6月時点で計画の策定を終えたのが51市町村にとどまっていることが分かった。約3分の2の自治体が未策定で、草津白根山の噴火で被害が出た群馬県草津町も策定していなかった。 死者・行方不明者63人を出した2014年9月の御嶽山(長野・岐阜両県)噴火後、避難計画の策定は義務化されたが、対策が徹底されていない状況が浮かび上がった。 国は2015年に活火山対策特別措置法を改正。火山災害警戒地域に指定された49火山の周辺自治体に対し、避難計画を策定して地域の防災計画に反映させたうえ、ホテルやスキー場などの集客施設も避難確保計画を作成するよう義務づけた。 自治体による避難計画には情報伝達のほか、避難経路や避難場所など6項目を盛り込む必要がある。内閣府防災担当によると、全項目の策定を終えたのは延べ155市町村のうち51市町村(2017年6月時点)。草津白根山に近い群馬、長野両県内の対象5町村のうち策定済みは嬬恋村のみだった。 草津町は1983年の白根山噴火以降、火口に近いレストハウスを鉄筋コンクリート造りに建て替え、山頂付近に13個のシェルターを整備して警戒してきたが、町の担当者は「気象庁などから本白根山を警戒するようにとの指摘はなく、噴火する山ではないという認識だった」(総務課)と困惑する。 噴火警戒レベル1(活火山であることに留意)の那須岳や日光白根山を抱える栃木県では、いずれの市町村も避難計画の策定を終えていない。 県危機管理課の担当者は「特にロープウエーで移動する場所など人が歩けない場所で避難経路を確保するのは難しい」と課題を語る。
3、住宅の耐震診断「実施せず」52%(内閣府)
内閣府は、防災に関する意識を調べる世論調査の結果を公表した。住宅の耐震診断の状況を今回の調査で初めて聞いたところ「実施していない」が52%と半数を超えた。このうち「実施する予定がある」と答えたのは4%にとどまった。「実施している」は28%だった。耐震診断についての理解が浸透していないのではないかとみられる。 住宅を耐震化するには、耐震診断で地震に対する強度を調べた上で耐震改修工事をする必要がある。国土交通省は2025年をめどに耐震性を有しない住宅をおおむね解消する目標を掲げている。「すでに診断を実施し、耐震性を有していた」人は25%。「診断を実施していないが、今後の実施予定は分からない」と答えた人は30%だった。 どちらにも該当しない人を対象に耐震改修工事の予定を聞いたところ「改修または建て替えをするつもりはない」が38%に上った。「予定がある」「今後必要がある」は合わせて14%だった。 一方、大地震が起こった場合に心配なことを聞いたところ「建物の倒壊」が73%に上り、2013年12月の前回調査から7.8ポイント上昇した。地震に備えた対策は「自宅や家財を対象に地震保険に加入している」が46%で前回調査から7.7ポイント増えた。
4、火山監視 専門家足りない(気象庁)
火山の監視や防災対策を担う専門家の不足が深刻化している。2014年の御嶽山、1月23日の草津白根山と死傷者が出る噴火が発生。気象庁は観測態勢の強化を進めるが、国内に111ある活火山の監視を担える専門家は約80人にとどまる。1人の研究者が複数の火山を掛け持ちして観測している状態で、世代交代も進まないという。 北海道大地震火山研究観測センターは24時間態勢で監視が必要な50の「常時観測火山」のうち、北海道駒ケ岳や有珠山など5火山や道内外の他の活火山を観測している。所属の研究者はわずか3人。火山性微動が確認された場合はデータを分析し、気象庁に情報提供するなど即時対応が求められる。 火山学の専門家は、観測データを分析して気象庁などに助言したり、自治体の火山防災協議会のメンバーとして避難計画を検討したりするなど、防災で重要な役割を担っている。文部科学省によると、国内の火山研究者はこの数年80人程度で推移する。 火山はそれぞれ特徴が大きく異なり、本来は1つの山を専門に観測するのが望ましいとされる。だが、研究者の数は全国に111ある活火山の数を下回り、1人の研究者が複数の火山を観測、研究する場合が少なくない。 数年後には多くの火山研究者が定年退職を迎える。将来に向けた人材育成は急務となっている。 また、草津白根山の本白根山の噴火で、気象庁は自治体などから情報提供を受けながら噴火速報を発表できなかった。同庁は近く、噴火の目撃情報があれば、噴火速報を出せるよう運用改善する。 気象庁はこれまでカメラや職員による直接確認を速報発表の条件としていた。今後は自治体や消防、研究機関などから目撃情報が寄せられた段階で速報を出すように改める。 噴火速報は24時間監視している50の「常時観測火山」が対象となっている。
5、困窮者住宅の防火強化(厚生労働省)
政府は、生活保護受給者らの住まい確保など、低所得者の生活再建に関する各法律の改正案を閣議決定した。生活困窮者の自立支援を掲げる札幌市の共同住宅で1月31日深夜、11人が死亡する火災が発生。同様の火災は各地で相次いでおり、防火態勢のチェックや避難通路の確保など規制を強化する。2020年度からの実施を目指す。 高齢や病気で働くことができない生活保護受給者らは、家賃滞納などへの懸念から民間住宅への入居を断られやすい。こうした人たちの受け皿として、NPO法人などが運営する無料・低額宿泊所やシェルターが各地に広がるが、貧困ビジネスの温床になったり、安全性や質に問題があったりすると指摘されていた。 自治体に届けられた無料・低額宿泊所は全国に約530か所あり、約1万5千人が暮らす(2015年6月時点)。現在も①避難通路の整備、消火器の設置②個室の広さは7.43平方メートル以上――などの指針があるが、法的な強制力はない。このため社会福祉法を改正し、具体的な防火態勢の最低基準を定め、下回る場合は自治体が改善命令を出せるようにする。 また生活困窮者自立支援法の改正では、宿泊所やシェルターの利用者が社会的に孤立しないよう、NPOなどのスタッフが訪問して通院や服薬の確認をしたり、日常生活の相談に応じたりする事業を新設する。 このほか子供の貧困対策も拡充する。生活保護世帯の子供が大学などに進学する際に、一時金(親元を離れる場合は30万円、同居の場合は10万円)を支給。自治体が実施している学習支援事業の対象を現在の小中学生から高校中退者や中卒者に広げる。
6、災害補償付き住宅ローン 金利0.035~0.5%上乗せ(市中金融機関)
災害による自宅の損害に備えるには、火災保険や地震保険に加入するのが一般的だ。ただ、火災保険は地震や噴火による火災や津波などは原則、補償の対象外だ。地震保険は地震による火災や津波、家の倒壊などを対象にするが、受け取れる保険金はセットで加入する火災保険の半額までと上限もある。 火災保険や地震保険に加入したうえで、被災時に自宅の住宅ローンと新たに住まいを確保するコストの二重負担を回避したり、生活再建資金を確保したりできるタイプの住宅ローンが増えている。「自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン」などと呼ばれる。 2017年2月に開始され、導入する銀行が増えている。住宅ローン契約時に適用金利に0.035~0.5%を上乗せしたり、5万円程度の事務手数料を支払ったりすることで利用できる。 補償を受けるには被災時に自治体が発行する「罹災(りさい)証明書」を提出する。全壊なら24か月、大規模半壊なら12か月分といった具合に、損害の規模に応じて返済相当額が払い戻される期間が決まる。 ただ、払い戻される条件は金融機関ごとに異なる。自宅の被災だけで受け取れるタイプもあるが、受け取るには住宅ローンの返済自体は続ける必要があり、滞ると払い戻されなくなるタイプもある。借り入れ前に条件を確認しておこう。 対象となる災害が金融機関ごとに異なる点にも注意したい。 対象物件も異なる。新生銀行は新築の戸建て住宅のみが対象で住宅ローンの借入期間が25年以上あることなどの条件がある。 火災保険や地震保険の保険金は非課税だが、このタイプの住宅ローンの中には返済相当額が「雑所得」とみなされるものが多い。会社員の場合、給与以外の所得が20万円を超えると確定申告が必要となる。
7、消防広域化の期限延長(消防庁)
消防庁は、複数の消防本部を統合して広域化する取り組みの期限を6年延長し、2024年4月1日までにする。再編が十分に進んでいないためだ。今後、10年後の消防体制や広域化の進め方を再検討するよう、都道府県に要請。統合に伴う費用の財政支援は継続する。 消防庁は当初、2012年度末を期限に、本部ごとの管轄人口を30万人以上とする目標を掲げていたが、本部の設置場所や財政負担を巡る調整が難航。期限を今年4月まで延ばし、管轄人口に関係なく広域化を進めてきたが、今でも約730ある本部のうち、管轄人口10万人未満は全体の約6割を占める。 広域化は、災害時の大量動員、機材の効率的な更新がしやすくなるメリットがあり、人口減少が進む中、消防庁は「将来も持続できる体制の確立には広域化が最も有効」としている。 各消防本部は今夏までに、人員や施設の現状を分析。都道府県単位で消防本部のあり方を議論し、2019年度中に広域化推進計画を改定する。
8、交通死亡事故 高齢運転者 高止まり(警察庁)
2017年に全国で起きた75歳以上の高齢ドライバーによる交通死亡事故は418件で、前年から41件(8.9%)減ったことが警察庁のまとめで分かった。全体に占める割合は12.9%と同0.6ポイント減にとどまり、4年連続で13%前後と高止まりが続く。 2017年の交通事故による全体の死者は5.4%減の3,694人で68年ぶりに過去最少を記録した。取り締まり強化や安全対策などにより過去最悪だった1970年(1万6,765人)の5分の1近くに減った。 これに対し、高齢ドライバーによる死亡事故は2016年までの5年間、年458~471件と横ばい傾向。2017年は件数、割合とも2年ぶりに減ったが、依然高い水準にある。 2017年に死亡事故を起こした高齢ドライバーのうち、免許更新時などに認知機能検査を受けた385人では「認知症の恐れ」(第1分類)と「認知機能低下の恐れ」(第2分類)の判定が49%の計189人に上った。2015~2017年の受検者全体の割合(計約32%)を大きく上回り、認知機能の低下で事故の可能性が高まる傾向がうかがえた。 2017年3月には認知機能検査を強化した改正道路交通法が施行。第1分類と判定された場合に医師の診断が義務づけられ、約半年で697人が認知症と診断され免許の取り消し処分などを受けた。 75歳以上の運転免許証の自主返納は進み、2016年比1.5倍の25万2,677人と過去最多を更新した。75歳以上の免許証の保有者は2017年末で540万人。10年前の2007年末(283万人)の2倍近くに増え、今後も増加が見込まれている。
9、保険の加入率 自転車は6割(警察庁)
2017年に自転車がぶつかるなどして歩行者が死亡・重傷となった事故のうち、自転車側の損害保険の加入率は60%にとどまった。警察庁の調査で明らかになった。過去には事故を起こした小学生の保護者が9千万円を超す賠償を求められたケースもあり、注意が必要とされる。 歩行者の死亡・重傷事故は299件発生。自転車側の運転者は若い年代が多く、24歳以下が過半数を占めた。内訳は10代が全体の37%と最多で、20~24歳が12%、9歳以下が2%だった。 警察庁によると、保険の加入率は19歳以下の71%に対し25歳以上では56%。家族の自動車保険や火災保険の特約として加入し、就職や結婚で独立後に対象から外れるケースもあるとみられる。
10、倒壊の恐れ 2割低下(東京都)
東京都は、地震発生時の建物の倒壊や火災の危険性について地域別に5段階評価した「危険度測定調査」の結果を公表した。危険度が最も高い「ランク5」は85地域(全体の1.6%)となった。建物の耐震化や防災公園の整備などで、都全体の防災力は高まっているとはいえ、木造住宅が密集する地域は高い危険度と判定された。 都によると、「ランク5」は荒川区や足立区などの地域が多く、古い木造住宅が密集しているうえに、地盤が緩く建物が倒壊する恐れがあり、危険度が高い傾向にある。 荒川区は耐震基準が強化された1981年以前に建てられた住宅に戸別訪問したり、町内会で説明したりして、建て替えや住み替えの助成制度についての説明を繰り返している。 前回調査では、町屋4丁目の倒壊の恐れがある建物は1ヘクタールあたり約26棟だった。耐震改修などの効果もあり、今回は約20棟に改善した。 都によると、2番目に危険度が高い「4」は287地域(5.6%)、「3」は820地域(15.8%)、「2」は1,648地域(31.8%)、「1」は2,337地域(45.2%)だった。生活道路が混雑している中野区や杉並区の一部地域では、前回調査よりも危険度が高く評価された。 都全体では、耐震性の高い建物への建て替えや耐震改修などで建物倒壊の恐れは前回調査から2割低下。延焼を食い止める道路の整備などで、火災の危険も4割程度下がっている。 都内の住宅耐震化率は2015年時点で83.8%で、都は2020年度末までに95%以上とする目標を立てている。 地震に関する地域危険度測定調査は、1975年から5年に1度ペースで実施しており、2013年9月以来で今回が8回目。防災意識の向上や震災対策を進める地域の選定への活用が狙い。都内の最も弱い地盤で震度6強に相当する地震の強さを想定。都内5,177町・丁目ごとに「建物倒壊危険度」や「火災危険度」のほか、避難や消火活動・救助活動の困難さを加味した「総合危険度」をランク付けした。
11、スプリンクラー設置1割満たず(厚生労働省)
無料低額宿泊所は社会福祉法に基づく施設で、無料あるいは低額で生活困窮者に宿泊場所を提供する。厚生労働省によると、2015年6月時点で全国に537施設あり、1万5,600人が利用。約半数が入居前の状況がホームレスで、約3割が施設に4年以上入居している。 スプリンクラー設置は義務づけられていないが、493施設(91.8%)が未設置だ。施設運営者が建物を所有していないケースがほとんどで、運営者が勝手に手を加えられない事情がある。 一方、社会福祉法などに規定がなく、生活保護受給者が2人以上利用するなどしている施設は全国に1,236施設。中でも北海道が307施設と4分の1を占めている。
[防災短信]
- 1、避難指示解除も人口6割止まり ~福島県内10市町村、学校・病院……遠い復旧~ 2018年2月12日付 日本経済新聞
- 2、噴火へ備え 首都圏でも ~マスク備蓄など降灰対策 埼玉、東京など~ 2018年1月30日付 日本経済新聞
- 3、津波試算2002見送り ~福島第一原発、経産省東電反発で~ 2018年1月30日付 日本経済新聞(夕刊)
- 4、韓国火災、死者は37人 ~院内スプリンクラー無く 韓国保健福祉省発表~ 2018年1月27日付 日本経済新聞
- 5、草津白根山は水蒸気爆発 ~マグマ成分見つからず、火砕流1.8km先に到達か 気象庁~ 2018年1月25日付 日本経済新聞
- 6、十和田火山 噴火で原発に降灰も ~青森、秋田両県被害想定公表 30キロ圏に火砕流も~ 2018年1月25日付 日本経済新聞
- 7、重度うつ 死亡リスク4倍 ~東日本大震災、宮城県調査~ 2018年2月10日付 毎日新聞
- 8、災害時の避難所地図情報 QRコードですばやく把握 ~品川区 シートを街路灯に掲示~ 2018年2月21日付 日本経済新聞
- 9、原発事故の一律賠償3月末終了 ~福島県、募る不満 震災前の暮らし、ほど遠く~ 2018年2月19日付 日本経済新聞
- 10、大雪で救助要請 県に伝えず ~福井県警 男性が死亡~ 2018年2月11日付 日本経済新聞
- 11、震災の教訓忘れないで ~仙台市 防災フォーラムを開催~ 2018年2月18日付 日本経済新聞
- 12、除染土処理 安全性を検証 ~環境省 茨城・栃木で測定~ 2018年2月01日付 日本経済新聞(夕刊)
- 13、台湾地震 救助打ち切り ~死者16人 損壊ビル解体へ~ 2018年2月12日付 日本経済新聞
- 14、矯正施設の一部耐震不足 ~刑務所・少年院、老朽化の波 法務省~ 2018年2月10日付 日本経済新聞(夕刊)
- 15、避難計画の不備認める ~札幌火災 運営会社~ 2018年2月05日付 日本経済新聞(夕刊)
【参考文献】
- 1、 2018年1月05日付 日本経済新聞(夕刊)
- 2、 2018年1月25日付 日本経済新聞
- 3、 2018年1月28日付 日本経済新聞
- 4、 2018年2月01日付 日本経済新聞
- 5、 2018年2月09日付 日本経済新聞(夕刊)
- 6、 2018年2月10日付 日本経済新聞
- 7、 2018年2月13日付 日本経済新聞
- 8、 2018年2月15日付 日本経済新聞(夕刊)
- 9、 2018年2月15日付 日本経済新聞(夕刊)
- 10、 2018年2月16日付 日本経済新聞
- 11、 2018年2月23日付 日本経済新聞