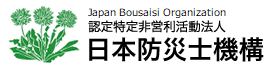防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
防災評論(第95号)
山口明の「防災・安全 ~国・地方の動き~」
防災評論家 山口 明氏の執筆による、「防災・安全 ~国・地方の動き~」を掲載致します。防災対策を中心に、防災士の皆様や防災・安全に関心を持たれている方々のために、最新の国・地方の動きをタイムリーにお知らせすることにより、防災士はじめ防災関係者の方々の自己啓発や業務遂行にお役立てて頂こうとするものです。今後の「防災・安全 ~国・地方の動き~」にご期待下さい。
山口明の防災評論
防災評論(第95号)【2018年6月号】
【目次】
〔政治行政の動向概観〕
〔個別の動き〕
- 1、被災地以外で13%消化(地方自治体)
- 2、余震の恐怖など 関連死因の4割(熊本県)
- 3、南海トラフ「ゆっくり滑り」広範囲で(海洋研究開発機構)
- 4、改正道路法、老いる地下配管 メンテ義務づけ(厚生労働省)
- 5、衛生チーム、災害派遣(厚生労働省)
- 6、津波避難の計画進まず(消防庁)
- 7、災害廃棄物の処理 プッシュ型に転換(環境省)
- 8、災害時誘導に電子看板(消防庁)
- 9、手話で災害情報発信(気象庁)(139市町村)
- 10、支援物資情報 自動で集約(内閣府)
- 11、災害時の取り組み例示(東京都)
- 12、位置情報精度 正確さ要求(国土交通省)
- 13、全車両に防犯カメラ(JR東日本)
- 14、長周期耐震 新たな検証方法(日本建築構造技術者協会)
- 15、南海トラフ 避難策議論(中央防災会議)
- 16、中古住宅に「安心R」マーク 国の品質基準スタート(国土交通省)
- 17、「不急」救急出動 集計へ(消防庁)
- 18、川の水位 データ一括管理(国土交通省)
- 19、災害時派遣へチーム(気象庁)
- 20、「臨時情報」対応で初 南海トラフ想定し訓練(国土交通省)
〔政治行政の動向概観〕
今年はこれまでの間大きな自然災害が無い恵まれた年と思われていたが、初夏に入り事態は暗転した。6月に入り突然大阪北部で大地震があり、最大震度6弱という大阪府はじまって以来の揺れを記録、ライフラインや鉄道の復旧が大幅に遅れたりして、改めて都市災害に対する備えの脆さや課題が浮き彫りになった。なかでもプール脇のブロック塀が折れるようにして全面的に上部が道路側に崩落、直下に居たとみられる小学生(9)が命を失うという痛ましい事故が発生した。このショッキングな事故をマスコミは連日大きく取り上げ、このブロック塀を長年放置してきた高槻市教委を激しく攻め立てている。確かに点検のたびに潜在的危険性を見逃してきた市教委の対応のまずさ、判断の甘さはあろうが、その背後にある制度的、構造的な不都合についてももっと幅広くとらえて世間への警鐘を鳴らすのが報道の使命と思われる。 ところで、大阪では次期万国博覧会の開催権を巡ってロシア、アゼルバイジャンの各都市と激しく争っている最中であり、11月にも最終投票が行われるとされている。その最中での地震であり、“オオサカ”の名は別の意味で広く海外に知られることとなった。“フクシマ”の時もそうだったが、地震災害に不慣れな国が多い中で日本での地震報道は大きな注目を集める。今回は震度6弱の激しい揺れが大阪北部の人口密集地で発生したにもかかわらず、死者は5名、大きな建物崩壊やインフラの大破壊も無く、月末には市民生活はほぼ正常化している。これほど被害が軽微だったのはやはりわが国が長い間営々と地震防災対策、地震に強い街づくりに取り組んできた成果であると言ってよいが、本来そのようなプラスの面も取り上げるべき本邦報道がほとんど「危険、不安、支障」の一色となっていることに大きな危機感を覚える。これらの報道を目にした外国人が、東日本大震災の時のようなわが国や大阪の忌避行動に走らないとも限らない。いつまでも近視眼的で改善がない日本のメディアであるが、自分たちの報道ぶりが日本国民のみならず全世界から注目されていることをもっと認識して適切な行動を取っていく必要がある。 一方、大阪北部地震の記憶もまだ生々しい今月上旬、西日本全域を豪雨が襲い、行方不明者を合わせ犠牲者200人を超す大惨事となった。はっきり言って報道の姿勢は地震に比べその立ち上がりは緩慢で、“どうせ水害だから”と高を括っていたフシが伺える。その後、被害の全容が明らかになるにつれ、行政対応や報道ぶりも日に日にテンションは上がってきているが、何と弁明しても初動の対応遅れがこの惨状を引き起こしたことは間違いない。 亡くなった多くの人が高齢者であり、また、水死(溺死と思われる)だったことを考えると、これまでの新潟豪雨災(2004年)などの教訓は活かされていない。 地球温暖化の影響で、明らかに集中豪雨時の雨量は2倍増、3倍増となっている。行政も報道もその事実を直視し根本的対策を練る必要があり、その場合防災士など民間防災力をもっと活用する方途も真剣に検討されるべきであろう。
〔個別の動き〕
1、被災地以外で13%消化(地方自治体)
東日本大震災の復興予算のうち、地方自治体の支出額の13%強が被災地以外で使われていたことが分かった。東京都の1,287億円を筆頭に55自治体が100億円以上を支出、6年間で全く使っていないのは12町村だけだった。防災対策など全国で活用できる制度設計にしたことで、復旧復興に直接関係のない支出につながった。 2011~16年度の自治体支出額を集計して分析した。政府は2011~20年度の10年間で32兆円の復興予算を確保、国直轄事業などを除くと、自治体が使った額は6年間に17兆6,400億円だった。 震災の被害が大きかった特定被災団体(9県と227市町村)以外が2兆7,900億円を使い、都道府県から市区町村へ渡った予算の重複分を除くと13%強になる。 復興予算は所得税への上乗せなど25年間の復興増税や日本郵政株の売却益などを財源にしている。被災地以外が使えるのは、震災の教訓をいかす「全国防災事業」が盛り込まれたためで、どの自治体でも使える仕組みになった。津波被害対策(愛知県)や消防庁舎の建設(横浜市)のほか、学校の耐震化(大阪府東大阪市)などに使われた。 2011年度は林道整備などにも費やされた。2015年度で全国防災事業は終了したが、予算を繰り越している自治体では、2016~17年度も復興予算の支出が計上されている。
2、余震の恐怖など 関連死因の4割(熊本県)
熊本県は、2016年4月の熊本地震で昨年末までに震災関連死と認定された197人の原因や生活環境の集計結果を新たに公表した。認定の際の報告書に基づき複数回答を分類した結果、地震のショックや余震の恐怖による肉体的・精神的負担が4割を占めた。 関連死は益城町が、70代の女性1人を認定したと発表し、204人(熊本県201人、大分県3人)となった。地震の犠牲者は、直接死50人と2016年6月の豪雨災害で亡くなった5人を合わせ、計259人。 原因については複数回答で、249件を分類。避難所などでの生活の負担が74件、医療機関の機能停止などによる初期治療の遅れが43件、電気などのインフラの途絶による負担が13件と続いた。
3、南海トラフ「ゆっくり滑り」広範囲で(海洋研究開発機構)
海洋研究開発機構は、南海トラフ巨大地震の想定震源域で「ゆっくり滑り」と呼ぶ現象が広い範囲で繰り返し起きている可能性があると発表した。海底に沈めた地震計などの観測データを分析して分かった。巨大地震発生の仕組みなどの解明につながるとみている。 南海トラフでは、海側のプレート(岩板)が陸側プレートの下に沈み込んでおり、ひずみに耐えきれずに境界が急にずれると巨大地震が起こる。ゆっくり滑りは境界がゆっくり動き、人は揺れを感じない。
4、改正道路法、老いる地下配管 メンテ義務づけ(厚生労働省)(JR東日本)
老朽化した地下の配管が破損し、道路が陥没する事故を防ぐため、国土交通省は、配管の維持管理をガスや上下水道の事業者に義務づける。怠った場合は道路を管理する国や自治体が是正命令を出し、従わない事業者には罰則が科せられる。管理者に安全対策を促し、事故防止につなげる。 現行の道路法には、国や自治体が事業者に補修を命じる権限はなく、老朽化した配管の破損による陥没事故の多発につながっている。 国交省が通常国会に提出した改正案では、道路の下に配管や通信ケーブルを敷設したガス会社などの事業者に適切な維持管理を義務づける。上下水道の場合は市町村などが維持管理義務を負う。点検の頻度や具体的な方法については今後、省令で定める。必要に応じて事業者に管理状況を報告させ、事業所への立ち入り検査もできるようにする。 道路を管理する国や自治体が維持管理を十分にしていないと判断すれば、補修や更新作業を命じる。命令にも従わない場合は30万円以下の罰金か6月以下の懲役を科す。 水道管や下水管は高度成長期に整備がされ、老朽化が全国各地で進んでいる。国交省によると、地下配管の老朽化が原因とみられる道路の陥没事故件数は2015年度で2,896件、2016年度で2,872件あった。各年度で配管の内訳をみると、下水道が2,000件以上と大半を占める。 今回の道路法改正案では、歩行者や車いすの安全な通行確保のため、歩道の無電柱化も進める。「幅が著しく狭い歩道」であると道路管理者が判断した場合、電気事業者に対して電柱の設置を制限できるようにする。落下事故を防ぐため、ビルなどの看板についても維持管理を義務づける対象とする。
5、衛生チーム、災害派遣(厚生労働省)
厚生労働省は、大規模災害時に被災地に派遣する「災害時健康危機管理支援チーム」(DHEAT)の運用を開始すると発表した。医師らで構成し、保健所などで衛生対策を担う。同日、詳細を定めた活動要領を都道府県などに通知した。感染症などによる被災者の二次的な健康被害を防ぐのが狙い。 DHEATは医師や保健師、管理栄養士らで構成。被災地の保健所や行政機関の関連部署で、ボランティアや支援物資の受け入れを調整したり、感染症の拡大防止にあたったりする。被災者を直接支援する災害派遣医療チーム(DMAT)と違い、主に被災自治体の職員を支援する。 派遣部隊は1班5人程度とし、職員が順次交代しながら数週間~数か月ほど被災地で活動する。要請があったときに1か月程度の派遣ができるよう、平時から職員の編成などを決めておく。 DHEATの創設は、2011年の東日本大震災で保健所が被災して支援物資を迅速に分配できなかった経験がきっかけ。厚労省は2016年度からDHEATの候補者向けの研修を開始。2017年度末時点で全国約1,200人が受講するなど各都道府県が準備を進めている。
6、津波避難の計画進まず(消防庁)
消防庁は、津波で被害発生の恐れがある全国672市区町村のうち、自治会単位など地区ごとの細かい避難計画や地図が全域で作成されているのは、昨年12月時点で15.9%の107団体だったとの調査結果を発表した。市区町村ごとの避難計画は93.8%に当たる630団体が作成していた。 地区ごとの計画は、自治会や自主防災組織などが主体で作り、避難先や経路を盛り込む。市区町村単位の計画作成が進み、地区計画はこれからの地域が多い。避難の混乱を防ぐには詳細な地区計画が有効として、取り組みを促している。 消防庁によると、市区町村の一部エリアだけを対象に地区計画を作成していたのは16.4%、未作成は67.7%で、このうち約半数は今後作る予定という。 一方、市区町村単位の計画は、東日本大震災を教訓にした津波対策推進法で自治体の努力義務になっている。避難指示・勧告の発令基準や情報の伝達方法、避難場所などを記載している。 調査は、海岸線があるか、海岸線がなくても津波の遡上で被害が予想される市区町村が対象。群馬、山梨など8県は該当がなかった。
7、災害廃棄物の処理 プッシュ型に転換(環境省)
環境省は、大規模な地震や豪雨で出る災害廃棄物について、自治体などからの要請を待たずに、国主導で処理支援を始めることにした。方針を定めた対策指針を改定、公表する。被災地での情報収集を進めやすいよう、連携体制をあらかじめつくり、備えと初動を強化する。 支援物資の提供や、応援要員の派遣を国主導で先回りする「プッシュ型」と呼ばれる手法を災害廃棄物処理にもあてはめる。災害時には、片づけごみやがれきなどが大量に出る。南海トラフの巨大地震では最大約8.2億トン(東日本大震災の約16倍)、首都圏直下地震でも最大約1.1億トン(同約5倍)発生するとされる。だが、自治体は避難所など被災住民への対応で忙しく災害廃棄物対策が遅れたり、広域処理が必要だったりする可能性がある。 改定指針では、災害発生時の対応や事前の備えを自治体任せにせず、環境省が「司令塔機能を果たす」とし、広域連携の計画づくりを進める。被災地の実態を正確・迅速に把握するため、東北や関東など8つの地域ブロックで、出先の地方環境事務所などが軸となり、情報収集や連絡調整を強化する。自治体への財政支援も盛り込んだ。 また、災害時の処理に注意が必要な廃棄物として、東日本大震災後に普及が拡大している太陽光パネルや蓄電池を挙げた。感電などの恐れがあるため、ゴム手袋やゴム長靴を着用して処理にあたるよう呼びかけている。
8、災害時誘導に電子看板(消防庁)
2020年東京五輪・パラリンピックを控え、消防庁は、火災や大地震が起きた際、訪日外国人や障害者を避難誘導するための指針を公表した。多言語による案内のほか、電子看板で情報が一目で分かるよう工夫したり、簡単な日本語で呼び掛けたりする。交通機関や旅館・ホテルなどに活用を促す。 最近は地方を訪れる外国人も多く、施設側の対応がどこまで進むか課題になる。 具体的には、防災センターなどからの一斉放送は、日本語の後に原則として英語で流し、利用状況に合わせて中国語や韓国語も使う。災害の発生場所や被害状況、避難経路に関する案内は、視覚的にすぐ理解できるよう電子看板、スマートフォンアプリを活用する。 「今の場所にいてください」「今すぐ逃げてください」といった外国人でも理解しやすい日本語の表現も例示。慌てて建物から出ようとする人や、エレベーターに閉じ込められた場合の対応訓練も求めている。
9、手話で災害情報発信(気象庁)
災害発生時の現状把握が難しい聴覚障害者に必要な情報を円滑に発信するため、気象庁は、緊急記者会見の内容を手話で同時通訳する「手話通訳」の導入に向けた検討を始めた。国の会見での手話通訳は現在、首相と官房長官のみ。同庁は今後、手話通訳士らの意見や要望を聞いた上で、早ければ今秋にも運用を始めたい考えだ。 同庁は、震度5弱以上の地震発生時のほか、津波注意報や大雨など特別警報の発表時、火山が噴火した際などに緊急記者会見を開いている。手話通訳の導入後は、会見者の横に手話通訳士に立ってもらい、双方をテレビの中継画面に映すことを想定している。会見が休日や深夜、未明になることもあるが、聴力障害者情報文化センターによると、手話通訳士は今年3月現在、全国で3,601人が登録されており、急な派遣にも対応が可能だという。 会見を行う予報官らの説明には「線状降水帯」「逆断層」「火砕流」などの専門用語が多用され、通訳には難しさも伴う。このため、東京手話通訳等派遣センターは「難解な用語については、新しい手話表現も工夫したい」としている。 厚生労働省によると、昨年3月現在、国内の聴覚障害者(平衡機構障害も含む)は約45万人。土砂崩れや洪水の音、消防車のサイレン、防災無線などが聞こえずに水害や火災に巻き込まれる恐れがあり、いかに迅速に防災情報を伝達するかが課題となっている。 2015年から会見への手話通訳導入を要望してきた全日本ろうあ連盟は「緊急時は音声以外の情報の有無が生死を分ける。今後も字幕での説明などリアルタイムで伝わる情報発信を求めていきたい」としている。
10、支援物資情報 自動で集約(内閣府)
政府は、大規模地震などの発生に備え、被災した市町村や避難所と支援物資に関する需給情報を自動的に集約・共有できるシステムを開発する方針を固めた。現場が必要とする支援物資の状況を国が把握することで、被災地へ迅速に無駄なく届ける狙いがある。2018年度中にも新システムの運用を始めたい考えだ。 政府が被災地のニーズを把握するシステムは現在、都道府県との間で構築されている。しかし、市町村が各避難所の情報をまとめるまで都道府県が待つ必要があるほか、必要な支援物資の書き込み方が統一されていなかったため、政府が品目や数量を把握するまでに手間取ることが少なくなかった。 新システムは、支援物資の情報を都道府県だけでなく、市町村や避難所、物資供給に関する協定を市町村と結んでいる民間企業とも共有できるようにする。災害時には避難所に新システムを使用できるタブレット端末を配布することで、避難所単位の「需要」の把握が可能となる。 また、発送された支援物資の「供給」の状況も一目で確認できるようにしたい考えだ。輸送拠点など目的地に届いた場合は、システム上で表示が「発注」から「対応済み」に変わる仕組みを検討している。 このほか、菓子パンやカップ麺、衣類などの生活必需品(男女別)など支援要請品目に関する全国統一のリストも作成する。これにより、現場が選択して数量を記入すれば自動的に集計できることになる。 政府は2016年4月の熊本地震で、民間が開発した同様のシステムを試験的に導入。避難所ごとのニーズ把握がリアルタイムで可能となるなど効果があったことから、全国的に活用できるよう開発することを決めた。 政府は、指定避難所ではない場所で身を寄せ合う被災者を携帯電話の位置情報で把握するシステムの開発も進めており、2020年の東京五輪・パラリンピック前の実用化を目指している。こうしたシステムにより、支援物資と支援者の動きを把握することで、被災者への迅速で効率的な支援体制を構築したい考えだ。
11、災害時の取り組み例示(東京都)
首都直下地震の発生が懸念される中、都は2020年東京五輪・パラリンピックを見据えて2018~20年度の防災対策をまとめた「セーフ・シティ東京防災プラン」を策定した。 同プランは「区部・多摩地域における地震」「島しょ地域における火山噴火」など、4つの災害シナリオを作成。シナリオごとに「建物の耐震化、更新」「飲料水や備蓄品の確保と輸送」など、あらかじめ行うべき取り組みを例示した。 また、「都営住宅の耐震化100%」や「住民参加による防災訓練参加者数1,200万人」、「全区市町村で避難所管理運営マニュアル策定」などの目標値も明記した。
12、位置情報精度 正確さ要求(国土交通省)
国土交通省は、交通事故発生時に消防などに自動通報する「救急通報システム」の性能基準を定める。道路運送車両法に基づく保安基準を7月にも改正。全地球測位システム(GPS)による車両の位置情報の精度に基準を設定し、負傷時にハンズフリーで音声通話ができる装備などを求める。 救急通報システムは自動車が衝突してエアバッグが開くと、自動的にオペレーターを通じて消防に事故の発生を通報する。GPSの普及などに伴い、乗用車への設置が進む。 性能基準案は、迅速な救助につなげるため、事故車両の位置情報に正確さを要求。周囲に障害物がない平たんな場所で事故が起こった場合に、実際の位置とGPSが示す情報のずれを15メートルまでとする。 電波状況が悪いビル街や山間地域などでは40メートルまでの誤差を許容範囲と定める。事故の発生時刻や車両の登録番号を自動通知する機能も求める。 また、運転者らが重傷を負い、両手が使えない状況でも音声通話ができるようにすることを基準案に盛り込み、バックアップの電源の設置も必要とする。基準案は今後、販売される新型車には2019年7月から、既存の車種には2021年7月から適用される予定。 日本の救急通報システムは、日本緊急通報サービス(東京・港)「ヘルプネット」が2000年から業務を開始。トヨタ自動車の「レクサス」で標準装備されるなど普及が進み、会員数は100万人を突破した。ドイツの自動車部品メーカー「ボッシュ」も2016年から、日本で救急通報サービスに進出している。
13、全車両に防犯カメラ(JR東日本)
JR東日本は、2018年度以降に投入するすべての電車に防犯カメラを設けると発表した。痴漢など、電車内での迷惑行為の抑止を狙う。 防犯カメラは通勤車両では基本的に1つの車両に4台を設ける。特急の場合、客室の前後に2か所設置する。カメラはドアの上部に取り付け、作動中であることを表示するステッカーを貼る。 JR東日本は埼京線と新幹線の車内に防犯カメラを設置済み。新幹線も含めて約1万2千両分を保有しており、更新期を迎えた車両から順次、防犯カメラ付きに置き換える。山手線では5月から防犯カメラを搭載した車両を投入し、2020年までに全50編成に設置する。
14、長周期耐震 新たな検証方法(日本建築構造技術者協会)
南海トラフ巨大地震に伴う長周期の揺れに備えて、超高層ビルの耐震設計で安全性を検証する方法を日本建築構造技術者協会関西支部が独自にまとめた。柱や梁(はり)などの部材ごとに細かく調べて「損傷が建物に残っても、倒壊しないで人命を守る」ことを確認する。 60メートルを超す建物については従来、長周期地震動対策として、1秒に80センチの揺れを想定して耐震性をチェックしてきた。国土交通省は南海トラフ巨大地震に備えるため関東、大阪、中京、静岡で耐震対策を強化。昨年から建物や場所によっては2倍の揺れを想定することになった。 今回の検証法は、この見直しに対応して作った。通常は、想定する最大の揺れに対して、建物の各階の変形が一定に抑えられることなどを検証して安全性を確認しているが、揺れが大きくなると変形を抑える設計での対応が難しくなる。そこで、建物の変形が大きくなった場合に、部材がどうなるかを詳細に解析して確認する方法をまとめた。
15、南海トラフ 避難策議論(中央防災会議)
マグニチュード(M)9クラスの南海トラフ巨大地震を巡り、政府の中央防災会議の作業部会は、発生可能性が高まった際の住民避難や企業活動のあり方などについて議論を始めた。予知が困難となり、発生が確実ではない段階での臨時情報の発信へと対応を見直す中、自治体や企業にどこまで具体的な方向性を示せるかが焦点となる。 作業部会は年内に報告書を取りまとめる方針。 初会合を開催したのは「南海トラフ沿いの異常な現象への防災対応検討ワーキンググループ」。 国は、東海地震の予知は「発生数日前に可能」として対策を進めてきたが、中央防災会議の作業部会が2017年9月に「現在の科学的知見で予知は困難」と報告。国は同年11月から、南海トラフ全体の震源域で前震などの現象が確認された場合に「地震発生の可能性が相対的に高まった」との情報を流す運用を始めている。 だが、情報発信後の適切な避難方法や企業活動のあり方などは明示されていない。 初会合で「暫定的に対応している現在、万が一異常な事態が起きれば社会が混乱する。」「不確定性のある情報にどう対応するか、具体的な方向性を少しでも早くまとめていく」との意見が出た。 南海トラフ巨大地震の事前対応について、国は津波被害が特に大きいとされる高知、静岡両県と中部圏をモデル地区に指定。2017年11月以降、地震の発生が確実でない段階での情報発信への対応について課題を検討している。 静岡県は40年前から東海地震に備えた具体的な対策を練ってきたが、国が「予知は困難」と判断したため見直しを迫られた。 「住民すべての避難はやり過ぎか」「空港や港を平常通り利用することは妥当か」など地震の発生が確実でない段階での対応を検討。県幹部からは「災害が起きなかった時に、どこまで避難生活を我慢できるのかといったバランスが難しい」などと声が出ている。 企業も判断を迷う。国が中部圏の大企業に聞き取り調査したところ、製造業や百貨店などの24社すべてが「(発生可能性が高まったという)情報が出ても操業を続ける」と回答した。 これまでの対策は、鉄道や金融などを含む各企業が強制的に営業を止めることになっていたが、今は何も示されていない。自社だけ操業停止すれば経済的損失を生むのではないか、との懸念が影を落とす。
16、中古住宅に「安心R」マーク 国の品質基準スタート(国土交通省)
2018年4月から中古住宅の物件広告に「安心R住宅」マークを付けられるようになった。国土交通省がつくったルールに基づく品質表示で、優良ストック住宅推進協議会など複数の登録業界団体が認証実務を担っている。 マークが付く物件は、震度7の地震でも人命に関わるような倒壊はしないとされる「新耐震基準」を満たす。具体的には新耐震基準が義務づけられた1981年6月以降に建築された物件か、それ以前の物件のうち耐震診断で耐震性が確かめられたものだ。 マークがない物件でも新築年を見れば新耐震かどうか分かるが、柱や梁(はり)といった重要な構造材が腐食していると耐震性能も下がりかねない。屋根や外壁のメンテナンスが十分でなければ雨漏りが発生している可能性もある。 こうした不安の払拭のため、安心R住宅はあらかじめ専門家によるインスペクション(建物状況調査)で構造上の不具合や雨漏りがないか調べる。買い主が望めば、購入後に不具合が見つかった際に修理費用が出る「既存住宅売買瑕疵(かし)保険」も付けられる。 さらにリフォームに関する情報提供も義務づけられた。登録団体がリフォームの統一基準を設け、物件ごとに具体的なリフォーム提案とその費用を示す。 リフォーム案が提示され、費用の見積もりが示されれば買い主も安心して住宅購入に踏み切れそうだが、現場では実務負担の重さを指摘する声も出ている。工務店業界には「提案づくりに協力しても必ずしも工事受注にはつながらない」との見方があり、マーク普及の障害になる可能性も指摘されている。 また、大手の不動産仲介会社はここ数年、構造上の不具合や雨漏り、設備の故障といった中古住宅のリスクをカバーする独自の補償制度を競って整えてきた。このため、いまのところ安心R住宅の登録団体に名乗りを上げていない。 登録団体の第1号となった優良ストック住宅推進協議会にしても、もともと大手住宅メーカー10社の施工物件を対象に「スムストック」という独自の品質規格を運用している。 安心R住宅は中古住宅の購入希望者に一定の安心感を与える制度だが、実際にマークを付けた住宅が本格的に流通するまでにはまだまだ時間がかかる。当面は不動産会社が買い取ってリフォームしたうえで売り出す「買い取り再販」の物件などが先行しそうだ。
17、「不急」救急出動 集計へ(消防庁)
消防庁は、救急車出動の必要性が低かった件数を2019年から集計する。救急車の出動は2017年速報値で634万2千件に上り、8年連続で過去最多を更新。今後も増える見込みで、タクシー代わりに呼ぶといった「不要不急」の利用実態を把握する。 出動の増加は高齢化により、病気で運ばれる人が多くなっているためだ。不適切な利用が続くと、緊急時に現場の到着が遅れる事態も心配されている。 2017年の搬送者をみると、48.5%は入院を必要としない「軽症」だった。ただ、119番時点では「激痛で動けなかった」「出血が多く救急車が必要だった」など、出動が必要な事例もある。 このため、消防庁は新たな基準を設定する。搬送後に軽症と分かった人を対象に、①自力で歩けないなど、見た目の緊急性②言語障害といった脳卒中などの疑い③救急隊による応急処置の有無――などを隊員がチェック。すべて該当しない場合は「必要性が低かった事案」として集計する。 一方、出動後、搬送に至らないケースもあるが「明らかに死亡」「搬送拒否」「誤報」など、理由は多岐にわたる。出動の必要性を判断するのは難しく、今回は理由の分類見直しにとどめる。
18、川の水位 データ一括管理(国土交通省)
国土交通省は、全国の自治体が管理する中小河川に新設する水位計のデータの一括管理を始める。水位計は現在、多くの中小河川には設置されていない。水位計がないと豪雨時に水位上昇の把握が難しくなり、住民の避難判断の遅れにつながる可能性がある。同省はデータの一括管理で自治体の運営費負担を減らし、水位計の設置拡大を目指している。 河川法などによると、1級河川は国交省や都道府県、2級河川は都道府県、それ以外は市町村がそれぞれ管理する。自治体が管理する水位計は全国に約5,200か所(2017年時点)あるが、1級や2級河川の設置が中心で、中小河川にはほとんどないという。 川幅が狭く急カーブも多い中小河川では水位が急激に上昇しやすいが、水位計がないと豪雨時に水位の急上昇の把握が難しい。住民を避難させるかどうかを判断するのが遅れ、中小河川が氾濫して犠牲者が出たケースも過去に起きている。 2016年8月の台風10号豪雨では岩手県岩泉町の小本川が氾濫し、川沿いの高齢者施設で入所者9人が死亡した。2017年7月の九州北部豪雨でも福岡県朝倉市の桂川などが氾濫し、死者・行方不明者が41人に上った。水位計がなかったり、監視体制が十分整っていなかったりした中小河川で氾濫が発生している。 国交省は中小河川の周囲に人家や公共施設がある場合は豪雨時に迅速な避難が必要と判断。2020年度までに水位計を今の倍以上に増やし、全国の約1万1千か所に設置することを目指している。ただ、中小河川を管理する自治体にとって水位計の設置費や運営費の負担が課題となっている。 水位計の設置拡大を後押しするため、国交省は自治体が別々に管理している水位計のデータを、国が共通のクラウドサービスで一括管理することで運営費の負担を軽くする方針だ。1台あたり年間約18万円かかる運営費は約1万円に抑えられるとしている。 同省は31道府県と11市町村と協定を結び、まずは今年度から設置する水位計などのデータを一括管理する。水位計のデータは同じホームページ内で公開。自治体にとっては周囲の河川の情報を一度に見られるため、豪雨時に全体状況を把握しやすくなる。 さらに水位計の設置費を抑える取り組みも始める。従来の水位計の設置費は1台あたり2千万円程度かかるが、豪雨時のみに使う簡易型は100万円以下に抑えられるという。
19、災害時派遣へチーム(気象庁)
大雨や地震など災害発生時に気象台から自治体へ緊急派遣する「気象庁防災対応支援チーム(JETT、ジェット)」が発足した。メンバーは自治体の対策本部などで刻々と変わる気象や地震の状況を防災担当者にリアルタイムで分かりやすく解説。自治体が住民に避難勧告や指示などを出す判断を支援する。 これまでも災害時に職員を自治体へ緊急派遣していたが、派遣される職員はその都度、選ばれることが多かったという。 気象庁は大雨や地震、火山など各分野で専門性の高い職員をJETTに登録。現在は職員の約3割にあたる約1,400人で構成している。 メンバーは災害発生時や災害が予想される前、地元の気象台や管区気象台から市町村や都道府県の対策本部などに緊急派遣され、常駐する。例えば、台風の接近で大雨が予想されるケースでは、事前に自治体の対策本部に入り、今後の台風や大雨の状況をリアルタイムで解説し、自治体が避難勧告、指示を出す判断を支援する。 JETT発足前だが、4月に大分県中津市で発生し6人が死亡した山崩れでは、大分地方気象台の職員が現地入り。救助活動の二次災害を防止するため今後の雨の見通しなどを伝えた。 JETTのメンバーには、複雑化し多岐にわたる気象災害関連情報を分かりやすい言葉で自治体の防災担当に解説する役割も求められている。 例えば、火山の場合、自治体の防災担当者が火山活動による地震や微動、傾斜計で観測する地殻変動などの状況を理解するには専門家の意見が必要となる。気象庁の有識者会議でも、同庁から有用な情報やデータは出ているが、自治体の防災担当者がすべて使いこなすのは難しいとの課題が指摘されている。 JETT発足の背景には自治体と地元気象台との連携を強化する狙いもある。勉強会などを通じて洪水警報や大雨警報の危険度分布など専門性の高い情報の活用方法を解説したり、地域防災計画作りなどの助言をしたりする。
20、「臨時情報」対応で初 南海トラフ想定し訓練(国土交通省)
国土交通省は、マグニチュード(M)9クラスの南海トラフ巨大地震の発生可能性が高まったとする「臨時情報」の発表を想定した初めての訓練を実施した。国交相や被災の恐れがある地方の出先機関が参加し、臨時情報を踏まえた対応手順や災害情報の共有方法を確認した。南海トラフの臨時情報はM7以上の地震が起きた時などに巨大地震につながる可能性があるとして気象庁が発表するもので、昨年11月から運用が始まった。 訓練では、金曜日の未明にM7クラスの地震が発生した後、南海トラフ巨大地震が発生する可能性が高まったとして気象庁が臨時情報を発出。土曜日正午にM9クラスの地震が発生したと想定した。 訓練には関東から九州までの各地方整備局や運輸局が参加。臨時情報の発表を踏まえ、各地の水門の管理体制や職員の参集についてテレビ会議で対応手順を確認するなどした。ドローンや整備局のヘリを飛ばし、被災状況の情報を共有する訓練も実施した。政府の中央防災会議の作業部会は、臨時情報が出た際の住民避難や企業活動について議論を進めている。
[防災短信]
- 01、大川小訴訟 石巻市上告へ ~予見「無理がある」~ 2018年5月07日付 日本経済新聞(夕刊)
- 02、商業施設火災37人死亡 ~ロシア ケメロボ~ 2018年3月26日付 日本経済新聞(夕刊)
- 03、中日本NEXCO前社長ら不起訴 ~笹子トンネル事故、嫌疑不十分で~ 2018年3月24日付 日本経済新聞
- 04、災害VR体験車お披露目 ~東京消防庁 全国初~ 2018年4月21日付 日本経済新聞(夕刊)
- 05、高潮 東京23区の3割浸水 ~東京都 スーパー台風上陸で想定~ 2018年3月31日付 日本経済新聞
- 06、地震に備えた保険 ~保障上乗せ、生活再建支える~ 2018年3月29日付 産経新聞
- 07、福島4町村 居住率6% ~避難解除から1年~ 2018年3月31日付 日本経済新聞
- 08、避難者なお73,000人 ~福島県、34,000人が県外に 復興庁調べ~ 2018年3月11日付 日本経済新聞
- 09、警察官の震災出向 2017年度末で終了 ~宮城県警、延べ513人応援~ 2018年3月10日付 日本経済新聞
- 10、ヤフーが「防災模試」 ~東日本大震災から7年~ 2018年3月02日付 日本経済新聞(夕刊)
- 11、入札改革 水害対策に波紋 ~東京都 “一社入札なら中止”が遅れ招く~ 2018年3月20日付 日本経済新聞
- 12、帰還困難区域での除染予定地わずか7% ~町内分断、募る疑心暗鬼~ 2018年3月19日付 日本経済新聞
- 13、空飛ぶ消火ロボ ~東北大 水の力で浮上、建物の中へ~ 2018年3月31日付 日本経済新聞
- 14、「リアス線」2019年3月全通 ~JR東日本から3セクへ、8年ぶり~ 2018年3月29日付 日本経済新聞
- 15、災害FM すべて閉局 ~福島県富岡町 使命終わる~ 2018年3月31日付 日本経済新聞
- 16、復興拠点 95ha申請へ ~福島県葛尾村 帰還困難区域内~ 2018年4月07日付 日本経済新聞(夕刊)
- 17、海難防げ ネットで情報 ~海上保安庁 新システム、五輪までに運用~ 2018年4月20日付 読売新聞(夕刊)
- 18、病院の耐震化率7割 ~厚生労働省 2017年は1.4ポイント改善~ 2018年4月18日付 日本経済新聞
- 19、給油所 過疎地では廃業相次ぐ ~自治体「公設GS」 生活支えるインフラ~ 2018年4月16日付 日本経済新聞
- 20、硫黄山、250年ぶり噴火 ~気象庁 警戒レベル3に上げ~ 2018年4月20日付 日本経済新聞
- 21、土砂ダンプ1万台分 ~大分山崩れ、死者4人に~ 2018年4月19日付 日本経済新聞
- 22、津波「15メートル試算」報告した ~東電旧社員が証言、対策は見送り~ 2018年4月18日付 日本経済新聞
- 23、仮暮らしなお38,000人 ~熊本地震から2年、住宅整備に遅れ~ 2018年4月14日付 日本経済新聞
【参考文献】
- 01、2018年3月12日付 日本経済新聞(夕刊)
- 02、2018年3月13日付 日本経済新聞(夕刊)
- 03、2018年3月15日付 日本経済新聞
- 04、2018年3月19日付 日本経済新聞
- 05、2018年3月21日付 日本経済新聞
- 06、2018年3月22日付 日本経済新聞
- 07、2018年3月29日付 朝日新聞
- 08、2018年3月30日付 日本経済新聞(夕刊)
- 09、2018年4月01日付 読売新聞
- 10、2018年4月01日付 読売新聞
- 11、2018年4月02日付 毎日新聞
- 12、2018年4月04日付 日本経済新聞
- 13、2018年4月04日付 日本経済新聞
- 14、2018年4月07日付 朝日新聞(夕刊)
- 15、2018年4月12日付 日本経済新聞
- 16、2018年4月14日付 日本経済新聞
- 17、2018年4月16日付 日本経済新聞
- 18、2018年4月16日付 日本経済新聞
- 19、2018年5月02日付 日本経済新聞
- 20、2018年5月07日付 日本経済新聞(夕刊)