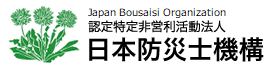防災士の認証と防災士制度の推進で地域社会の防災力向上に寄与する
防災評論(第96号)
山口明の「防災・安全 ~国・地方の動き~」
防災評論家 山口 明氏の執筆による、「防災・安全 ~国・地方の動き~」を掲載致します。防災対策を中心に、防災士の皆様や防災・安全に関心を持たれている方々のために、最新の国・地方の動きをタイムリーにお知らせすることにより、防災士はじめ防災関係者の方々の自己啓発や業務遂行にお役立てて頂こうとするものです。今後の「防災・安全 ~国・地方の動き~」にご期待下さい。
山口明の防災評論
防災評論(第96号)【2018年7月号】
【目次】
〔政治行政の動向概観〕
〔個別の動き〕
- 1、病院 進まぬ耐震化(東京都)
- 2、災害派遣隊 創設10年(国土交通省)
- 3、消防団 免許取得を支援(消防庁)
- 4、地下水で岩盤風化か(地すべり学会)
- 5、官庁横断の災害時通信(総務省)
- 6、気象台業務見直し(気象庁)
- 7、気象台長から首長携帯に 災害警戒「ホットライン」(気象庁)
- 8、商業ビル3割が震度6強で倒壊恐れ(東京都)
- 9、都内23区の3分の1 台風の高潮で浸水(東京都)
- 10、防災の世論調査で「自助」「共助」意識浸透(内閣府)
- 11、都市震わす長周期パルス(京都大学)
- 12、国土強靭化行動計画 流木対策の推進明記(内閣官房)
- 13、南海トラフ巨大地震は1,410兆円 被害額推計(土木学会)
- 14、仮設整備・食品や物資供給など 災害時 指定市に権限(内閣府)
- 15、避難勧告「不要」2割(中央防災会議)
- 16、水害避難「早めに」「自ら」(内閣府・国土交通省・気象庁)
- 17、防災支援チーム初派遣(気象庁)
- 18、15時間先まで降水予報(気象庁)
- 19、要支援者名簿 5市使わず(大阪・被災13市町)
- 20、山岳遭難 死者・不明354人(警察庁)
- 21、洪水の危険性 「線」で把握(国土交通省)
- 22、危険な塀 再三見抜けず(地方教育委員会)
- 23、原発事故時 すばやく避難(内閣府)
- 24、極端な短周期、塀に共振(筑波大)
- 25、30年以内大地震の確率 太平洋側高く(文部科学省)
- 26、広域の大雨情報 図解で(気象庁)
〔政治行政の動向概観〕
7月に西日本ほぼ全域を襲った集中豪雨は、風水害としては平成時代に入ってから最悪の死傷者と被害をもたらした大災害となった。しかもその特徴はこれまでにない傾向が伺える。その主な点は次の通りである。
(1)これまで大規模風水害は台風によるものか梅雨前線の活発化と相場が決まっていたが、今回はどれにも当てはまらないこと
(2)被害の類型が、例えば広島や愛媛では土砂崩れがメインだったのに対し、岡山では河川決壊による大浸水が注目されるなど、1つの災害であるにもかかわらず多様であること
(3)特別警報が10府県にわたって発令されたにもかかわらず、その後の避難措置が徹底できず避難率も数%の地域があるなど、かなりの防災上の緩みがあったこと
(4)大豪雨のあと記録的猛暑が続き、復旧作業に大きなダメージを与えたこと
さらにその後、7月下旬から8月初旬にかけて列島を襲った台風12号は東海から上陸して九州に向かうという前代未聞の「逆走」を演じ、被災地に再び被害を与えた。繰り返し襲う変則的な災害は、地球温暖化が主因とされる気象変動による悪影響と考えられる。今後もますますこれまでのセオリーでは考えられなかった類型の災害が出現する恐れがあり、防災対策はこの現象から大きな脅威を受けることとなろう。
加えて日本では世界でも例を見ない急激な少子・高齢化と人口減少が進行しており、災害に対し二重苦、三重苦の状況が続く。今回の災害を契機に、政府は今後の防災対策を抜本的に見直すとしているが、気候と社会構造の激変の中、やはり一人ひとりの防災力を着実に高めて対応力を強化する以外に方途はなく、そのため防災士制度のより一層の充実・展開と公的支援の検討など思い切った施策も選択肢の1つとされてよいように強く確信する。
〔個別の動き〕
1、病院 進まぬ耐震化(東京都)
1981年5月以前の旧耐震基準で建てられた病院の耐震改修工事が遅れている。東京都は、都内の一部病院が「震度6強以上」の地震で倒壊する危険性があると発表した。ただ患者が絶えず出入りする病院は閉鎖しにくく工事は容易ではない。首都直下地震では災害医療を担う役割なども期待されているが、一部病院は対応に苦慮している。
2013年に改正された耐震改修促進法は、不特定多数が利用する施設側に耐震診断の実施や結果報告を義務づけるが、耐震改修の実施は「努力義務」にとどめる。国や自治体は病院の耐震補強や移転に補助金の交付や低金利での融資を行い、耐震化を促している。
| 建物種別の耐震化率(2017年) | |
|---|---|
| 病院 | 72.9% |
| 公立小中学校 | 98.8 |
| 市庁舎など | 81.3 |
| 社会福祉施設 | 86.5 |
| 警察本部・警察署 | 84.9 |
2、災害派遣隊 創設10年(国土交通省)
大規模災害の復旧を支援する国土交通省の緊急災害対策派遣隊(TEC―FORCE)が創設10年を迎える。東日本大震災や九州北部の豪雨など、頻発する災害の現場に急行し、被害状況の調査や応急的な復旧工事を担ってきた。南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生も懸念される中、人員などの体制強化を進めている。
派遣隊は、道路や河川、土砂災害などが専門の国交省と地方出先機関の職員ら約9,400人が兼務する。事前に任命し、指令系統を整えておくことで、災害発生時の迅速な対応を可能とした。
道路や堤防の損壊状況を調べるほか、衛星通信車の派遣、応急対策の立案などを担い、人材や機材が十分でない自治体を支える。
2008年6月の岩手・宮城内陸地震以来、今年3月末までに81の災害で出動。東日本大震災ではピーク時に500人以上の隊員が現地入りした。国交省の担当者は「物資や救援部隊の輸送ルートの回復や、排水ポンプ車による浸水被害の解消に貢献した」と振り返る。
2017年7月に発生した九州北部の豪雨では、派遣隊が危険な箇所を小型無人機「ドローン」で空撮するなどして、流木の堆積状況をはじめ被害の全体像を効率的に確認し、早期の激甚災害指定につなげた。
被災自治体が、復旧工事の財政負担が軽くなる激甚災害指定を受けるには、被害状況の調査が必要だ。だが、被災直後は住民対応に追われ、手が回らない。被災した福岡県東峰村は「ノウハウがある派遣隊が、被災の規模など必要な調査を代行し、資料にまとめてくれた」と話す。
国交省は、甚大な被害が想定される首都直下地震や南海トラフ地震に備え、各地への隊員の派遣人数などを定めた活動計画を策定済みで、今後は詳細な活動内容や人員配置などを検討する。同省は「最新技術を使って、活動の質をさらに高める。自治体や建設業者とも研修などで連携を深めていきたい」と話している。
3、消防団 免許取得を支援(消防庁)
消防庁は、道路交通法の改正で新設された「準中型免許」について、消防団員が取得するのを本年度から財政支援する。普通免許で乗れた消防車両の一部が、改正後は準中型でないと運転できなくなり、活動に支障が出る恐れがあるためだ。団員に教習所の費用を助成している自治体に対し、金額の一部を交付税で手当てする。
改正道交法は昨年3月に施行。重量3.5トン以上7.5トン未満の車両を運転できる準中型免許を新設する一方、普通免許の対象の上限を、5トン未満から3.5トン未満に引き下げた。このため改正後に取得した普通免許では、3.5トン以上の車両を運転できなくなった。
全国の消防団が所有する5万1,381台(昨年4月時点、消防庁まとめ)のうち、準中型が必要なのは36.5%に及び、普通免許で運転できない車両が大幅に増える。多くがポンプ車だという。
すでに普通免許を持っている人は、これまで通り乗れるが、今後、免許を取る若手を中心に運転者の確保が難しくなると懸念される。消防庁は、普通免許で乗れる小型の車両の導入を、更新の際に検討することも呼び掛ける。
4、地下水で岩盤風化か(地すべり学会)
住民6人が犠牲になった大分県中津市の山崩れで、現地調査した日本地すべり学会(東京)は、地下水によって岩盤が風化し、粘土状になったことで地滑りが起きた可能性があるとの見解を示した。現場周辺では新たな亀裂は見つからなかった。
学会によると、崩落した斜面の規模は推計で幅約160メートル、高さ約120メートル。現場の地質は主に火砕流が堆積した硬い岩盤「凝灰角礫岩(ぎょうかいかくれきがん)」とし、斜面中腹の露出した部分が粘土状になっていた。また、地下水による浸食の影響を指摘した。
同学会は林野庁や大分県と合同で現地調査した。山崩れは4月11日に発生。山裾の住宅4棟が巻き込まれ、うち3棟に住む男性1人、女性5人が死亡した。
5、官庁横断の災害時通信(総務省)
総務省は、官庁や警察、消防といった公共機関が個別に整備・運用している無線システムなどの共用化に乗りだす。災害などの非常時の連絡や情報共有に役立て、被災者の支援や復旧活動などに素早く取り組めるようにする狙いだ。これまでは災害派遣医療チーム(DMAT)などで専用の通信手段を持っていないケースもあり、災害対応の効率化が課題だった。
現在、国内では公共機関はそれぞれ専用の周波数を使った無線システムを持つのが主流だ。海外では米国や英国、フランスなどで携帯電話の通信技術「LTE」を使い、音声や画像をやりとりする共用型ネットワークの構築が進んでいる。
6、気象台業務見直し(気象庁)
市町村の防災対応を支援するため、気象庁が地方気象台の業務や体制の見直しを検討している。気象台と市町村の連携をより密にし、災害への危機意識を共有できる関係づくりを強化する。早ければ2019年度にも関東甲信の気象台から始める。
気象台職員が市町村の気象の特性や防災体制を詳しく把握し、災害時や災害の恐れがある場合、電話連絡や自治体の防災部署に出向いて状況や見通しを説明する。災害への危機感を共有し、避難指示・勧告の発表などを手助けする方針。
見直しでは、地方気象台の天気予報や警報に関する作業の一部を管区気象台や地方の中枢の気象台、本庁に集約。雲の状況など目視観測の一部は、機器で自動化する。
現在、2人一組のシフトで行っている業務を1人で担えるようにし、市町村支援や管区などでの作業の体制を強化する。
大雨や竜巻、突風をもたらす積乱雲は、気象衛星やレーダーを活用して本庁が全国を集中監視することも検討する。
気象庁は、自治体支援を充実させるため、地元の気象台を中心に指定された職員が、避難勧告などの判断に助言をする「気象庁防災対応支援チーム」(JETT)を発足させた。気象台長が市町村長に直接連絡する「ホットライン」も推進している。
7、気象台長から首長携帯に 災害警戒「ホットライン」(気象庁)
各地の気象台長が、災害発生の恐れがある緊急時に市区町村長に直接、携帯電話で避難勧告・指示の発令を促す「ホットライン」が、全国の9割を超す自治体に広がった。過去に気象台の警戒情報などが自治体側に伝わらず被害が拡大した反省を踏まえ、気象庁が4年前から、首長らと24時間いつでも直接連絡できる態勢作りを進めていた。
2013年の災害対策基本法改正で「避難勧告・指示について気象台が助言できる」と定められたが、同年の東京・伊豆大島の土石流災害では、土砂災害警戒情報の発表が町職員に伝わらず、甚大な被害を招いた。2014年の広島市の土砂災害でも避難勧告が発令されたのは土石流の発生後だった。
こうした事例から気象台と自治体の連携強化の必要性が注目され、気象庁は2014年9月から、全国の気象台長と市区町村長とのホットライン作りを呼びかけていた。
気象庁によると、3月1日現在、47都道府県にある56管区・地方気象台の気象台長と2測候所の所長が、管轄地域の市区町村長1,572人と携帯電話番号を交換した。副市長などを連絡先とした163市区町村を含めると、ホットラインが一切ないのは国内1,741市区町村のうち6市町(約0.3%)となった。
気象台長がホットラインを使うのは、特別警報発表時など極めて甚大な災害が発生、あるいは予想される時で、内規では「特に危険度が高い場合に首長に危機感を伝える」と定めた。避難勧告・指示が既に出されていても、洪水や高潮、土砂災害などの恐れが高まれば、より強い警戒を求め、データに基づいて切迫した状況を伝えるという。
一方で、市区町村には防災専門の職員が少なく、気象情報の正確な理解が難しい場合もある。防災対応ではトップだけではなく実務者レベルでの意思疎通も欠かせない。疑問があれば気軽に気象台に問い合わせられる関係を築くことが重要だ。
ホットラインに加え、気象庁は災害発生前後の自治体への支援強化策として、全国の気象台職員を都道府県や市町村に派遣する「防災対応支援チーム(JETT)」を創設した。現地の災害対策本部などに加わり、緊急時の防災対応に対する助言などを行う。
チームには、予報官や土砂災害気象官など防災の知識や経験を持つ職員を中心に、同庁職員の約3割に当たる1,443人を登録。人的被害が予想される災害が主な派遣対象で、捜索開始前に天候状況を解説したり、新たな噴火や大きな余震が起きる可能性を指摘したりする役割を担う。
8、商業ビル3割が震度6強で倒壊恐れ(東京都)
東京都はこのほど、震度6強以上の地震で倒壊・崩壊の危険性が「高い」建物が156棟に上ることを明らかにし、その建物名を公表した。都では、昭和56年5月以前の旧耐震基準で建築された都内の大規模なホテルや商業ビルなど計852棟の耐震診断を調べたところ、危険性が「ある」建物が含めると全体の3割の251棟で倒壊などのリスクがあることが分かったもので、首都直下地震に向けて課題が浮き彫りになったかたちだ。
都の診断結果によると、震度6強~7程度の地震で倒壊・崩壊の危険性が「高い」建物は全体の18%、156棟、危険性が「ある」建物は11%、95棟。「低い」建物は584棟で、改修工事中などの建物が12棟となっている。他に5棟は所有者から報告がなく、報告を命令した。
震度6強以上の地震で倒壊・崩壊の危険性が「高い」とされた主な建物の中で目につくのは、地域のランドマークとなっている建物が多いことである。
9、都内23区の3分の1 台風の高潮で浸水(東京都)
東京都はこのほど、高潮浸水想定区域図から、台風による最大規模の高潮被害に見舞われた場合、沿岸地域を中心に都内19区の約212平方キロが浸水すると想定されることを明らかにした。これは23区の面積の3分の1に相当し、墨田、葛飾、江戸川の3区では9割以上が浸水。江東区では、水深が最大10メートルに達し、浸水被害が1週間以上継続する地域もあるとしている。
10、防災の世論調査で「自助」「共助」意識浸透(内閣府)
内閣府は防災に関する世論調査を実施したが、それによれば、災害時の対応は自分で身を守る「自助」に重点を置くべきだと考える人が39.8%に上り、2013年の前回調査から1.8倍に増えたことが分かった。また、地域住民らで助け合う「共助」を重視する人は24.5%で、2.3倍に増えている。首都直下地震など主に大都市の災害では、物資や避難所が足りなくなると懸念されており、内閣府は、「行政の支援だけに頼れないという意識が浸透して始めている」と分析している。
国や自治体による「公助」を重視する人は6.2%に止まり、「自助、共助、公助のバランスを取るべきだ」とした人は28.8%と大きく減った。
前回調査では、「バランスを取るべきだ」が56.3%で最も多く、自助21.7%、共助10.6%、公助8.3%だった。
大地震にどんな備えをしているかを複数回答で尋ねると、「地震保険加入」が46.1%で最多。以下、「食料や日用品の準備」45.7%、「停電時に作動する足元灯や懐中電灯の準備」43.3%、「家具の固定」40.6%などとなっている。
11、都市震わす長周期パルス(京都大学)
活断層による大地震で発生する「長周期パルス」という特殊な揺れが、高層ビルの新たな脅威として浮上してきた。免震装置を使っていても、この揺れに対して十分に機能しない恐れがある。頻繁に起きるわけではないので過剰に不安視する必要はないが、新たな対策を考える動きも出始めた。
京都大学は、活断層のズレの大きさや震度などから長周期パルスの発生を予測する手法を考案し2018年5月の学会で提案した。長周期パルスに関する情報は少なく、この手法を活用して研究を促したいと考えている。高層ビルへの影響が大きいとみられるため、建築業界も対策を検討し始めた。日本建築学会は2018年9月に仙台市で開く大会で、長周期パルスに関する専用の発表の場を初めて設ける。
長周期パルスは2016年4月、震度7を記録した熊本県西原村で、国内で初めて観測された。長周期パルスの特徴は次の3点。①周期は約3秒と長い②1回だけの大きな揺れ③活断層の表層部の大きなズレで発生。
長周期パルスは周期は似ているが、長時間の揺れがない。
高層ビルなどは特定の揺れに対し共振を起こす固有の周期がある。音の共鳴と同じ現象だ。長周期パルスはちょうどこの固有の周期と重なる。
深刻にとらえる理由は、既存の免震対策が役立たないかもしれないからだ。水平方向の揺れを減らす免震装置として、ビルの下に円形のゴムと鋼板を交互に重ねた積層ゴムを設置する。地下の壁と建物の間は、揺れを見込んで通常50~60センチメートルの隙間を設けている。大きな長周期パルスが発生すると、積層ゴムが壊れるか、建物と壁がぶつかる可能性がある。
発生する仕組みもよく分かっていない。地下の浅い場所にある活断層が大きくずれると出現するとみられる。1995年の阪神大震災では震源近くに計器がなかったこともあり、観測できなかった。
幸い、発生は極めてまれだ。プレート型の巨大地震が数百年の周期で発生しているのに対し、活断層で大規模な地震が起きる回数は数千年から数万年に1回にとどまる。揺れが伝わる地域も活断層近くにとどまる。
だが日本に活断層は数多い。高層ビルの立ち並ぶ都心部を走る活断層もあり、無視できない。手立ては今のところ、揺れを想定し壊れにくい設計を採用するしかない。海外では1999年の台湾大地震や2002年の米デナリ地震で長周期パルスが観測された。デナリ地震ではパイプラインが大きくゆがんだが、余裕を持たせてつなげたパイプは切断されなかったという。
12、国土強靭化行動計画 流木対策の推進明記(内閣官房)
政府は、大規模災害に備えた国土強靱(きょうじん)化推進本部の会合を首相官邸で開き、2018年度版の行動計画を決定した。昨年7月の九州北部での豪雨災害を踏まえ、中小河川による被害を防ぐための流木対策の推進を明記した。
今年2月に北陸3県などで起きた豪雪被害を教訓として、交通網維持に向けた除雪を巡る課題への対応も盛り込んだ。
政府は今回の行動計画で過去4年の取り組みを整理し、年内にも改定する強靱化基本計画に反映させる方針だ。
行動計画では、福岡、大分両県の豪雨災害は中小河川の氾濫によって被害が拡大したことから、緊急点検で抽出した全国約1,200地区で集中的に流木対策を進めるよう求めた。
雪害対策として、車両の渋滞や立ち往生が懸念される場所で、予防的な通行規制や集中除雪を実施する必要性を指摘。除雪業者の担い手確保、融雪につながる技術開発にも取り組むよう促した。
13、南海トラフ巨大地震は1,410兆円 被害額推計(土木学会)
土木学会は、巨大地震や高潮、洪水による被害額の試算を公表した。地震とそれに伴う津波は発生から20年にわたる被害を累計し、南海トラフ巨大地震は1,410兆円、首都直下地震は778兆円と見積もった。政府の想定を基に、長期にわたる国内総生産(GDP)の落ち込みを阪神大震災の経過を参考に推計。従来の政府の試算を大幅に上回る規模となった。高潮と洪水は東京、大阪、名古屋の3大都市圏ごとに試算し、首都圏や大阪では14か月で最大100兆円を超える被害が出ると算出した。一方、公共インフラ整備を進めることで、これらの被害を最大6割軽減できると推計。政府・与党が推進する国土強靱(きょうじん)化計画をさらに強化するよう提言した。
14、仮設整備・食品や物資供給など 災害時 指定市に権限(内閣府)
大規模な災害が発生した時、都道府県が担っている被災者支援の権限を、20ある政令指定都市に移譲できる改正災害救助法が、参院本会議で可決、成立した。来年4月に施行される。仮設住宅の整備や物資の供給が迅速に進むとの期待がある一方、全国知事会は「ほかの市町村との間で不公平が生じるおそれがある」と懸念を示す。
権限が移譲されるのは、避難所の運営など全10項目。移譲を希望する指定都市の財政状況や災害時の対応力を考慮し、知事の意見を聴いた上で、国が「救助実施市」に指定する。
改正の目的は被災者支援の迅速化。救助実施市になれば、都道府県を介して行ってきた業務が単独でできるようになる。都道府県はほかの市町村の支援に集中でき、費用も指定都市が自ら支出するようになる。
権限委譲を求める声は阪神大震災以降強まり、今年4月にも指定都市市長会が国に要望書を提出した。一方、全国知事会は「救助内容の公平性が損なわれる懸念がある」と反発。改正法では、食料や住宅資材の調達供給は都道府県に調整権があると明記されたが、5月の法案提出の際も反対声明を出した。
| 指定都市に移譲される10項目の権限 | |
|---|---|
| ①避難所・応急仮設住宅の供給 | |
| ②食品・飲料水の供給 | |
| ③衣服・寝具等の供給 | |
| ④医療・助産 | |
| ⑤被災者の救出 | |
| ⑥住宅の応急修理 | |
| ⑦学用品の供給 | |
| ⑧埋葬 | |
| ⑨死体の捜索・処理 | |
| ⑩住居やその周辺の土石等の除去 |
15、避難勧告「不要」2割(中央防災会議)
政府の中央防災会議の作業部会は、南海トラフ沿いで異常を観測したとする臨時の情報が出ても、被害の恐れのある自治体の約2割が「住民への避難勧告の発令を検討しない」とするアンケート結果を公表した。理由として「情報の不確実性」を挙げる声が多く、委員からは「ガイドラインを作って自治体に統一的な対応を促すべきだ」とする意見が相次いだ。
内閣府が3月、南海トラフ地震による大規模被害の恐れがある全国707市町村にアンケート調査し、699市町村から回答を得た。
臨時情報が出た際の対応について、36市町村(5.2%)は「どのような場合に避難勧告を発令すべきか既に検討している」と回答。498市町村(71.2%)が「まだ検討していないが検討する必要がある」とした。
一方で、165市町村(23.6%)は「検討する必要はない」と答えた。「情報の確度が高くない」という理由が多く、「情報収集や注意喚起などで対応できる」「解除の根拠や避難期間が不明確」などの回答もあった。避難勧告の発令が続いた場合に住民の健康や経済活動などに影響が出るまでの期間は、約半数の自治体が「1~3日程度」とみている。「1週間程度」を含めると約8割に上った。
「空振りの可能性がある情報を社会としてどうとらえるか統一した方がいい」という意見も出た。作業部会は最終的に「国が指針を示し、各市町村で具体的な避難行動を検討する」方針を確認した。
16、水害避難「早めに」「自ら」(内閣府・国土交通省・気象庁)
近年、温暖化などの影響で集中豪雨が増加傾向にある。発生から来月で1年を迎える九州北部豪雨の被災地は、なお復旧途上で、新たな災害への不安な日々が続く。
国土交通省によると、昨年、全国で起きた土砂災害は、10年前の1.6倍の1,514件で、過去10年で最も多かった。近年は、九州北部豪雨をはじめ、2013年10月の伊豆大島土砂災害や2014年8月の広島土砂災害、2015年9月の関東・東北豪雨など、大きな被害が目立つ。
自治体では通常、気象庁の大雨や洪水に関する警報や、河川の水位、雨量などに基づき、避難勧告や強制力のある避難指示を出す。だが山間部は観測点が少ない。避難指示や勧告が出された時点で、上流の地域では、すでに災害が起きている可能性もある。
朝倉市は、山間部の8地区について、気象庁が警報を発表した時点で直ちに避難勧告を出せるよう、発令基準を見直した。結果的に指示や勧告が「空振り」に終わっても構わない、との考えだ。
観測漏れをできるだけ解消するため、国交省は山あいの中小河川にも設置できる簡易型の水位計を開発、普及に乗り出した。
気象庁は、避難を判断する自治体との連携強化に取り組む。秋田県で昨年7月に起きた豪雨では、当時の秋田地方気象台が直接、大仙市など12市町の首長の携帯電話に連絡して避難を促した。住宅約2,200棟が浸水したが、人的な被害は免れた。
地元気象台とこうした「ホットライン」を構築している首長は今年3月1日現在、全国の9割にあたる1,572人。同庁は今年5月、必要に応じ気象台の職員らを自治体に派遣する「防災対応支援チーム」も発足させた。
2015年9月の関東・東北豪雨被害を受け、国の中央防災会議が翌年まとめた報告書は、住民は行政からの避難勧告や指示だけをよりどころとせず、自発的に判断し避難する「自助」の姿勢が必要と指摘した。
自治体に対しては、危険箇所を示したハザードマップの住民への周知や、避難行動の方法への理解を進めるといった、自助を促す取り組みを求めている。
災害時の避難行動としては、①あらかじめ決めておいた避難所に向かう「水平避難」を考える②自宅周辺が水に浸かり移動できない場合は、自宅の2階以上など高い場所へ移る「垂直避難」を選択する――といった知識を持つことが、住民自らの安全確保に有効である。
気象庁の統計では、国内の雨量観測点が整備された1976年以降、集中豪雨の年平均回数は増加する傾向にある。
1時間に50ミリ以上の「非常に激しい雨」が降った回数は、2008~2017年で年平均238回。1976~1985年と比べると、約1.4倍に増えた。1時間に80ミリ以上の「猛烈な雨」を観測した回数も増加している。一方、年間の降水日数は減少傾向だ。
雨のもとになる雲は、大気中の水蒸気が冷やされて生じる。気温や海水温が上がると、雲にならない大気中の水蒸気量が増えるため、雨は降りにくくなるが、降る時は大雨になりやすい。
日本の年平均気温は、19世紀末から100年あたり1.19度のペースで上昇している。気象庁は、温暖化が日本の豪雨増加や降水日数の減少をもたらしている可能性があるとみる。
温暖化は台風にも影響する。発生数は減るが、勢力が強い台風の数が増えるという予報が示されている。
気象庁は、温暖化で熱帯での大気循環が弱まり、台風の移動速度が遅くなる傾向が、日本に接近して長く停滞すると、前線を刺激するなどして豪雨をもたらしやすくなると指摘する。
17、防災支援チーム初派遣(気象庁)
大阪府北部で起きた最大震度6弱の地震で、気象庁は気象台の職員でつくる「気象庁防災対応支援チーム」(JETT)を初めて派遣した。大阪府と兵庫県、近畿地方整備局にそれぞれ1人が常駐する。
JETTは現地で情報収集し、各自治体の防災担当者にリアルタイムで天気や地震の状況について解説する。
気象庁によると、今後自治体の要望や被害状況に変化があれば、増員も検討する。
18、15時間先まで降水予報(気象庁)
気象庁は、雨量の分布予想を示した「降水短時間予報」を6時間先から15時間先まで延長して発表する運用を始めた。気象庁のホームページ(HP)で公開し、スマートフォン(スマホ)でも見やすくHPを改良した。明け方の雨量が前日夕方の時点で分かるほか、大雨が予想されるときに自治体がより早く避難勧告などの発令を判断できるようになる。
雨量の分布はHP内の「今後の雨」のページで確認できる。従来は地方ごとに表示されていた画面を自由に動かせるようになるほか、同じ画面上で土砂災害や浸水害の危険度分布への切り替えができる。スマホで見る場合には位置情報を取得することで、自分のいる地域を自動で表示する。
運用を始めたスーパーコンピューターによって延長して予測が可能になった。気象庁は「今後もスパコンを利用し、気象情報のさらなる改善に取り組む」としている。
19、要支援者名簿 5市使わず(大阪・被災13市町)
大阪府北部を震源とする最大震度6弱の地震で、法律に基づく要介護者や障害者ら災害時に支援が必要な「避難行動要支援者」の名簿を使って安否確認を進めた自治体が、被災13市町のうち8市町にとどまることが分かった。3市は安否確認自体を実施せず、自治体で対応に差が出ていた。
国は「災害弱者」が多く亡くなった東日本大震災を教訓に改正した災害対策基本法で、要支援者の名簿作成を市区町村に義務づけた。災害時は名簿を活用した安否確認の実施も求めている。13市町すべてで計約27万人分の名簿が作成されていた。
今回の地震を受けて内閣府は6月18日から、災害救助法が適用された府内13市町に安否確認するよう周知。ただ名簿を元に安否確認を進めたのは、大阪、豊中、守口、茨木、寝屋川、四條畷、交野の各市と島本町の計8市町だった。高槻、摂津両市は名簿は使わず障害福祉事業所への連絡や独自の独居高齢者名簿などで安否を確認。一方、吹田、枚方、箕面の3市は安否確認自体をしていない。吹田市の担当者は「避難準備情報や避難勧告が出されていないため、安否確認しなかった」と説明している。
名簿を活用した自治体でも、個人情報の提供に同意した人のみ安否確認の対象とした自治体もあった。寝屋川市は「被害状況を見て、全員の確認は必要ないと判断した」と話している。
国が避難行動要支援者の名簿作成を義務づけたのは、2011年の東日本大震災がきっかけだ。震災では犠牲者の約6割が65歳以上で、障害者の死亡率も被災者全体の約2倍だった。
国は2013年の法改正で名簿作成を義務づけ、指針で無事が確認されていない要支援者は名簿を活用して安否確認するよう求めた。ただ、実行するかは自治体任せなのが実情だ。
20、山岳遭難 死者・不明354人(警察庁)
2017年に起きた山岳遭難事故は2,583件で、死者・行方不明者は354人だったことが警察庁の集計で分かった。件数は前年より88件増加、死者・行方不明者は35人増加。いずれも統計が残る1961年以降で最多を更新した。死者・行方不明者の6割超が60歳以上だった。外国人の遭難も増えている。
遭難者は計3,111人。年代別では60歳代(23.8%)、70歳代(21.5%)、50歳代(14.6%)など、登山ブームの担い手である中高年が目立った。都道府県別の発生件数は北アルプスや八ケ岳がある長野県が292件で最も多く、北海道(236件)、山梨県(161件)と続く。
遭難事故の原因は「道迷い」(40.2%)と「滑落・転落・転倒」(35.1%)が多かった。8人が死亡した栃木県那須町の雪崩事故を含め、雪崩による遭難も65人に上った。
遭難事故全体の3分の1が単独での登山だった。死者・行方不明者に限ると6割近くを占め、単独登山の事故が深刻な結果につながりやすい実態がうかがえる。
外国人の遭難も増えている。2017年に遭難したのは121人。前年より28人増え、4年前の2.8倍になった。訪日客の増加に伴い、登山やスキーを楽しむ外国人が増えている。外国語で安全対策を呼びかける自治体もあり、警察庁は「情報がきちんと届くよう自治体などと連携していきたい」と話す。
21、洪水の危険性 「線」で把握(国土交通省)
水位計のある場所の「点」でしか伝えられなかった河川の水位情報を「線」で伝えるシステムを国土交通省が開発した。流域の自治体や住民が洪水の危険性を的確に把握し、迅速な避難につなげられるようにするのが狙い。一部の河川でテスト運用を始めており、流域自治体に対する情報提供を始める。
2015年9月、関東・東北地方を襲った豪雨で鬼怒川の堤防が決壊。茨城県常総市では、避難が遅れた住民ら1千人以上がヘリコプターで救助された。
浸水地区の一部では決壊時点でも避難指示が出ておらず、同市の検証報告では「避難勧告・指示の決定にあたって依拠すべき判断材料に事欠いてしまった」とされた。
こうした経験を踏まえ、国交省の国土技術政策総合研究所(国総研)は2015年から、水位計のある場所以外の水位情報も提供するシステムの開発を進めていた。
新システムでは、河川事務所が数年に一度、約200メートルごとに測量する川の断面や堤防の情報を活用し、水位計がない場所の水位もコンピューターで推測。「危険水域まで1メートル」「堤防の高さを超えている」などと、地図上の河川を色分けして水位の状況を分かりやすく伝える。データは10分ごとに更新する。
堤防が決壊した場合の浸水域もハザードマップのデータを基に表示し、危険な地域がどこか一目で分かるようにする。
このほか、水位計のある場所では6時間先までの水位変化の予測も示す。
荒川(東京都など)、山国川(大分県など)、川内川(鹿児島県など)の3河川については、6月から地方整備局でシステムのテスト運用を開始。国交省は台風シーズンに向けて7月下旬にも、3河川流域の自治体に対する情報提供を開始する。2019年4月からはインターネットでの一般公開も目指す。
国が管理する他の1級河川についても、各地の整備局などが河川情報の入力を進めており、2019年秋の公開を目標にしている。
当面は河川事務所が持つ水位計データを基に水位を推測するが、将来は自治体などが豪雨に備えて設置する「危機管理型水位計」のデータも取り入れて精度を高める。
22、危険な塀 再三見抜けず(地方教育委員会)
大阪府北部の地震で倒れ、女児が死亡する原因となった小学校のブロック塀を巡り、学校に外部から危険性が指摘されながら、教育委員会は見過ごし、3年に1度の法定点検もすり抜けていた。同様のブロック塀は全国の学校にあり、影響は各地に広がっている。
高槻市側がブロック塀の危険性を把握するいくつもの機会があったことが、改めて浮き彫りになった。ひとつは3年に1度、業者によって実施される法定点検だ。
市教委は会見で、法定点検でブロック塀の「違法状態」が見逃されていたことを明らかにした。直近の法定点検は2017年1月。倒壊した塀は「指摘なし」とされた。市の説明によると、業者は目視で点検したが違法性を見逃したという。その前の2014年2月には、当時の業者は塀の点検すらしていなかった。
建築基準法施行令では、ブロック塀の高さは2.2メートルを超えてはならず、1.2メートルを超す場合は補強のための「控え壁」が必要になる。倒壊した塀は高さ3.5メートルで控え壁もなく、どちらの基準も満たしていなかった。
外部からの指摘に耳を傾ける機会もあった。
市教委は2015年11月、講師に招いた外部の防災アドバイザーから、ブロック塀の危険性を指摘された。翌年2月、校長の依頼を受けて市職員が目視や打診棒で塀をたたいて音の変化を調べたが、ひび割れや傾きがなく、「問題なし」と判断された。
ブロック塀の危険性は、かねて指摘されてきた。1978年6月の宮城県沖地震では、死者28人のうちブロック塀などの犠牲が18人で、子どもが多かったという。1981年の建築基準法施行令の改正につながり、高さや厚さ、補強の控え壁の設置などが定められた。
多くの「見逃し」の末、女子児童の命が失われた。国土交通省近畿地方整備局の応急危険度判定士が、高槻市内の計31の小中学校で、塀の検査を始めた。専門知識を持った人が検査をすれば、どう考えてもおかしいと思ったはずだ。
ブロック塀は文科省による耐震化の調査対象になっておらず、危険な塀がどれほどあるか分かっていないのが現状だ。同省は、学校内の緊急点検と安全対策を求めたが、全国には小中学校だけで3万校ある。通学路まで含めたら、作業はさらに膨大になる。
一方、すでにブロック塀の撤去に乗り出した自治体もある。大阪府池田市は市立中学校のプール南側を囲うブロック塀の撤去に着手した。富山県内でも法令違反や危険なブロック塀が見つかり、滑川市内の小学校のブロック塀を撤去した。同様のブロック塀は和歌山市内や長野県佐久市でも確認され、撤去が進む。
南海トラフ地震に備える高知県。昨年夏に県内の公立小中学校のブロック塀490か所を調べ、46か所を「危険」と判定した。うち37か所を占める高知市は今年度から、フェンス柵に替える工事を始めている。
今回の地震では、民家の塀でも倒壊事故が起きた。国土交通省は、塀の所有者が点検するポイントをホームページ上で公開。全国の自治体に、所有者に点検実施を周知するよう求めている。大阪市は、所有者がコンクリートやれんがなどでできた塀をフェンスに置き換える際の補助制度を検討している。
23、原発事故時 すばやく避難(内閣府)
内閣府は、原子力発電所事故時の住民避難の円滑化に向け、原発周辺地域の避難経路の道路改修費などを補助するモデル事業として、福井、京都、愛媛の3府県の計4事業を選んだと発表した。本年度は計4億9千万円を交付する。
原発の立地、周辺自治体が避難経路の整備に関する財政支援を国に求めており、内閣府が今年度から予算化した。原発の再稼働が進む中、避難対策を強化し、住民の不安解消につなげる狙い。
福井県は関西電力高浜原発がある高浜町で狭い道路を拡幅する事業などが対象。愛媛県は、伊方町の四国電力伊方原発が細長い半島の付け根にあり、避難経路が限定されるため、土砂崩れで通行止めにならないようのり面保護対策などを行う。
京都府では2事業が選ばれた。宮津市で観光客らの一斉避難による渋滞を緩和するため、車両がすれ違えるように待機スペースを整備したり、南丹市で避難時に放射性物質の付着を調べる検査場周辺に案内板を設けたりする計画。こうした改善策で住民避難がどの程度スムーズになるか効果を検証し、効果が確認できた対策を、ほかの原発周辺地域でも実施する。
24、極端な短周期、塀に共振(筑波大)
大阪府北部で震度6弱を観測した地震が、0.5秒以下の極端に短い周期で強く揺れるタイプだったことが分析で分かった。ブロック塀や家具の棚などは短い周期の揺れに共振しやすく、6月18日の地震では複数箇所で倒れ犠牲者が出た。建物被害は揺れの周期が長いほうが深刻化するといい、周期の短さが倒壊した家屋が少なかった要因の1つとみられるという。
筑波大が防災科学技術研究所(茨城県つくば市)などによる観測データから分析した。
周期は揺れが1往復するまでの時間で、周期が短いと小刻みな揺れ、長いとゆったりした揺れ方になる。構造物は一般的に大きく高いものほど長い周期の揺れに共振しやすい。
0.5秒以下の周期の揺れでは塀や家具が倒れやすく、周期が1~2秒と長い場合は家屋が倒壊する恐れが強まる。
揺れる周期と強さを調べたところ、周期が0.5秒以下と短い「極(ごく)短周期」で強く揺れたことを示す結果が出た。家屋の被害が甚大だった阪神大震災(1995年)や熊本地震(2016年)はいずれも1秒を超える周期の揺れが強く、違いが明確という。
大阪府警によると、今回の地震で死亡した5人のうち、高槻市立寿栄小4年生(9)を含む3人はブロック塀や部屋の棚が倒れたことが原因とみられている。
消防庁によると、地震による住宅被害は25日時点の判明分で近畿4府県の8,089棟に上る一方、99%は一部損壊で、全壊(3棟)や半壊(14棟)は少なかった。
25、30年以内大地震の確率 太平洋側高く(文部科学省)
政府の地震調査委員会は、全国各地で30年以内に震度6弱以上の地震に見舞われる確率を示した2018年版の「全国地震動予測地図」を発表した。震度6弱では耐震化されていない木造家屋の多くは倒れる。2017年版と同様、首都圏や中部から四国地域の太平洋側、近畿地方などで確率が高く、大都市圏の震災リスクが改めて浮き彫りになった。
今回の評価は2018年1月1日時点で、6月18日に発生した最大震度6弱の大阪北部地震の影響は織り込んでいない。同地図は過去の地震記録などから全国各地で揺れに見舞われる確率として政府が毎年1回公表する。
公表した地図では、南海トラフ巨大地震が平均約90年間隔で起きる前提で計算しているため時間の経過で発生リスクが高まった。前回調査に比べ、同地震の影響を受ける恐れのある都道府県の確率がわずかに上昇した。
県庁所在地別では、最も確率が高いのは昨年版と同様に千葉市が85%。発生確率は前回調査と同じ。続いて横浜市が82%、水戸市が81%、高知市が75%、徳島市が73%、静岡市が70%となっている。
三大都市圏では東京都庁が48%と前回より1ポイント上昇。名古屋市は46%、大阪市は56%でいずれも前回と同じだった。
26、広域の大雨情報 図解で(気象庁)
気象庁は、台風の接近や大雨などが予想される場合にホームページで臨時発表する気象情報について、全国や地方レベルで危険度の高い場所や時間帯を図解で分かりやすく示すことを始めた。
これまでは図解での詳しい説明は府県レベルだったが、広域情報の提供で自治体や住民に早めの判断をしてもらうのが狙いという。
例えば、大雨で河川が氾濫しそうな場合、広域の地図で河川の危険度を色分けし、注意報や警報の予想時間帯などを表で示す。台風が予想される場合には土砂災害の危険度を色分けして情報提供したり、雨量分布図を用いて大雨のメカニズムを解説したりする。
これまで広域レベルの臨時情報の内容は、防災への注意喚起や予想雨量など文章のみだったが、図解化により一目で広域の気象状況が把握できるようになったという。
気象庁が現在発信している大雨災害に関わる情報は、市町村ごとに発表する注意報や警報、特別警報のほか、大雨や洪水の危険度分布など多岐にわたり複雑化している。広域の臨時気象情報にもこうした情報を盛り込み、防災に役立ててもらうとしている。
[防災短信]
- 01、「消えた」立川断層帯 ~データ不足 意見分かれる、文部科学省~ 2018年5月14日付 日本経済新聞
- 02、大川小訴訟 上告案を可決 ~石巻市議会、県も同調へ~ 2018年5月07日付 日本経済新聞
- 03、警察の災害専用訓練施設が完成 ~東京都内全国2か所目、堺市につぎ立川市に 警察庁~ 2018年5月10日付 日本経済新聞(夕刊)
- 04、防災訓練にゲーム性取り入れ ~官民連携 避難誘導で得点ゲット LINE、防災科学研究所~ 2018年4月02日付 毎日新聞
- 05、「復興精神」を発信 ~中国 四川大震災10年、研修を誘致~ 2018年5月12日付 日本経済新聞
- 06、「対策取れば原発事故起きず」 ~東電役員訴訟 元原子力規制委員が証言~ 2018年5月10日付 日本経済新聞
- 07、復旧工事 秋以降に ~大分県山崩れ1か月、大分県~ 2018年5月11日付 日本経済新聞(夕刊)
- 08、人のつながり、関連死防ぐ ~熊本地震「理想の避難所」~ 2018年5月01日付 日本経済新聞
- 09、都市機能AIで高度化 ~NTT 防犯・防災まず米国で~ 2018年5月03日付 日本経済新聞
- 10、災害救援にドローン ~多摩14市とNPO 空撮で被害把握~ 2018年4月26日付 日本経済新聞
- 11、島根西部 震度5強 ~5人ケガ、落石・崖崩れ~ 2018年4月09日付 日本経済新聞(夕刊)
- 12、浦安の液状化対策中止へ ~着工後に直面した住民合意の壁~ 2018年4月23日付 コンストラクション誌
- 13、被災外国人に仲介役 ~総務省 避難生活を支援~ 2018年4月10日付 日本経済新聞
- 14、役場の職員 消防団に ~福島県浪江町 住民帰還願い新分団が奮闘~ 2018年5月11日付 日本経済新聞
- 15、被災者の食事・健康研究 ~国立栄養研 国際災害栄養研究室創設~ 2018年6月04日付 日本経済新聞
- 16、被災3県 応援派遣職員減 ~東日本大震災~ 2018年6月04日付 日本経済新聞(夕刊)
- 17、庁舎解体阻止へ再び監査請求 ~岩手県大槌町の住民団体~ 2018年6月04日付 日本経済新聞(夕刊)
- 18、火山火災 25人死亡 ~中米グアテマラ、フエゴ火山~ 2018年6月05日付 日本経済新聞
- 19、土砂災害の訓練 参加急増 ~昨年164万人、5年で13倍~ 2018年6月06日付 日本経済新聞(夕刊)
- 20、老朽化水道管 断水招く ~大阪北部地震 一時9万戸、大阪府内更新遅れる~ 2018年6月24日付 日本経済新聞
- 21、大阪北部地震1週間 市民生活への影響続く ~住宅被害6,700棟超~ 2018年6月25日付 日本経済新聞
- 22、空き家対策 所有者不明で撤去費負担も ~空き家法に基づく措置、全国で1万件超~ 2018年6月18日付 日本経済新聞
- 23、大阪府内の学校384施設で損傷確認 ~ブロック塀や外壁~ 2018年6月20日付 毎日新聞
- 24、空き家倒壊 懸念広がる ~大阪北部地震 所有者特定が壁~ 2018年6月28日付 日本経済新聞(夕刊)
- 25、ガス復旧途上 生活に影 ~大阪北部地震 9万戸停止~ 2018年6月22日付 日本経済新聞
- 26、震災復興事業の窓口NPO買い取り利権狙う ~東日本大震災、熊本地震も標的に~ 2018年6月08日付 毎日新聞
- 27、避難先で犠牲 和解へ ~釜石津波訴訟 釜石市責任認める~ 2018年6月09日付 日本経済新聞
- 28、BCP遅れる近畿 ~策定率13% 中小企業に普及せず~ 2018年6月22日付 朝日新聞
- 29、児童引き渡し後津波で犠牲 ~東松島市敗訴確定~ 2018年6月01日付 日本経済新聞
- 30、地滑り拡大 住民不安 ~福島県喜多方市 一部に避難勧告~ 2018年6月09日付 日本経済新聞
- 31、気象変化「成層圏」も関係!? ~QBO現象 海洋研究開発機構が発見~ 2018年7月08日付 日本経済新聞
- 32、保育所混乱 防災に課題 ~大阪北部地震~ 2018年6月21日付 日本経済新聞(夕刊)
- 33、エレベータ復旧まだか!! ~大阪北部地震 閉じ込め339件~ 2018年6月23日付 日本経済新聞
- 34、手荷物検査実施は困難 ~JR会社 対策は強化、新幹線内で死傷事件~ 2018年6月10日付 日本経済新聞
- 35、コンビナート事故252件 ~消防庁 前年と同数~ 2018年5月30日付 日本経済新聞
- 36、大災害時、現地で情報集約 ~内閣府 官民チーム来年度運用~ 2018年6月13日付 日本経済新聞
- 37、洪水、豪雨に学ぼう ~防災授業教材にカードゲーム~ 2018年6月16日付 日本経済新聞
【参考文献】
- 01、2018年4月23日付 日本経済新聞(夕刊)
- 02、2018年4月24日付 日本経済新聞
- 03、2018年4月25日付 日本経済新聞
- 04、2018年4月30日付 日本経済新聞
- 05、2018年4月30日付 日本経済新聞
- 06、2018年5月10日付 日本経済新聞(夕刊)
- 07、2018年5月26日付 読売新聞
- 08、2018年5月号 UGMニュース
- 09、2018年5月号 UGMニュース
- 10、2018年5月号 UGMニュース
- 11、2018年6月03日付 日本経済新聞
- 12、2018年6月05日付 日本経済新聞
- 13、2018年6月08日付 Yahoo!ニュース
- 14、2018年6月09日付 朝日新聞
- 15、2018年6月12日付 日本経済新聞
- 16、2018年6月17日付 読売新聞
- 17、2018年6月18日付 日本経済新聞
- 18、2018年6月20日付 日本経済新聞(夕刊)
- 19、2018年6月21日付 朝日新聞
- 20、2018年6月21日付 日本経済新聞(夕刊)
- 21、2018年6月22日付 日本経済新聞
- 22、2018年6月23日付 読売新聞
- 23、2018年6月23日付 日本経済新聞
- 24、2018年6月26日付 日本経済新聞(夕刊)
- 25、2018年6月26日付 日本経済新聞(夕刊)
- 26、2018年6月28日付 日本経済新聞